UFO=空飛ぶ円盤を世界に認識させた 「ケネス・アーノルド事件」/羽仁礼・ムーペディア
UFO、UMA、心霊現象から、陰謀に満ちた事件まで、世界には不可思議な事象や謎めいた事件があふれている。ここでは毎回「ムー」的な視点から、それらの事象や事件を振り返っていく。今回は、「UFO事件史の幕
記事を読む

常識崩壊!? あまりにも非合理的で奇想天外な事例の数々! UFO遭遇ハイ・ストレンジネス・ミステリー!
UFO研究に、「プロバビリティ」と「ストレンジネス」というふたつの指標を持ち込んだのは、かのジョセフ・アレン・ハイネック(1910〜1986)である。ハイネックといえば、1948年、アメリカ空軍が最初に設立したUFO研究機関「プロジェクト・サイン」で科学顧問を務めて以来、その後の「プロジェクト・グラッジ」「プロジェクト・ブルーブック」を通じて、アメリカ空軍のUFO調査に協力した天文学者だ。

ハイネック本人は当初、UFOについては懐疑的な立場を取っていたが、数々の目撃報告に接する中で見解を変え、1968年のプロジェクト・ブルーブック終了後も、自ら「UFO研究センター」を設立し、個人的にUFO研究を続けた。UFOを科学的に研究しようとしてさまざまな分類や概念を定めたハイネックは、「UFO界のガリレオ」とも呼ばれることがある。
彼はまず、世界中から無数に寄せられるUFOの目撃報告を「遠距離からの目撃」と「近距離からの接近遭遇」とに整理した。
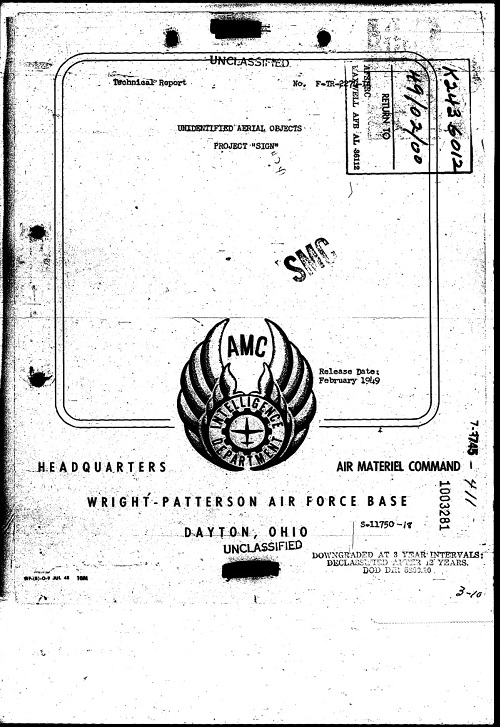
遠距離からの目撃については、形態別に「ノクターナル・ライト」「デイライト・ディスク」「レーダー・ヴィジュアル」という3種に分類。接近遭遇についても、単に飛行体や光点の目撃のみで、目撃者および環境への影響を伴わない「第1種接近遭遇」、何らかの物理的痕跡が確認された「第2種接近遭遇」、そしてUFOとともに搭乗員などの生命体らしき存在が目撃された「第3種接近遭遇」という3種類を定めた。
スティーヴン・スピルバーグ監督の映画『未知との遭遇』は、原題がまさに「第3種接近遭遇」で、ハイネック本人も科学者役で出演している。
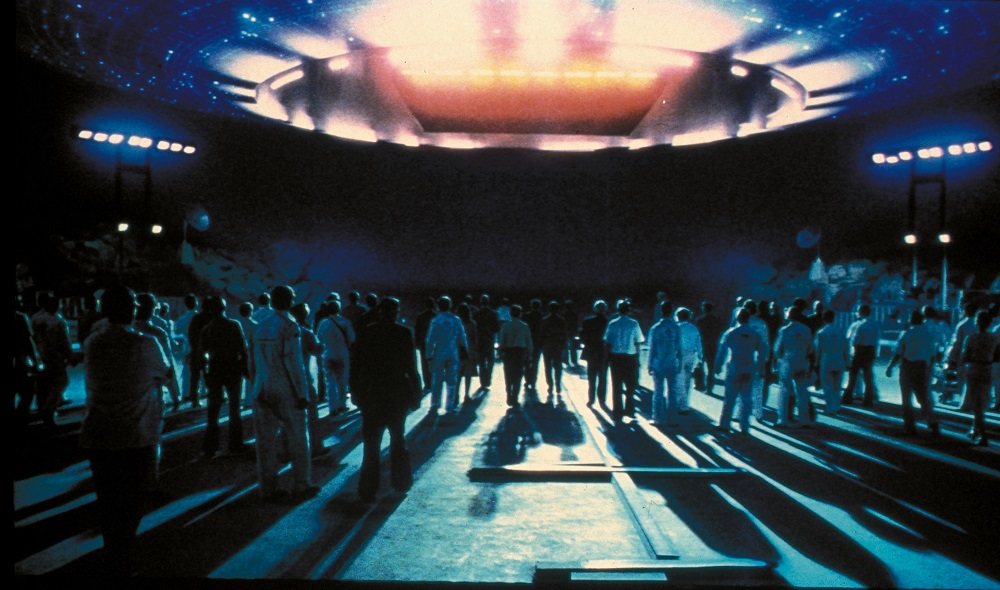
そのハイネックが、個々のUFO事件を評価するにあたって導入したのが、プロバビリティとストレンジネスという指標であった。
プロバビリティは日本では「可能度」と訳され、ハイネックはこれを10段階の数字で評価しようとした。その度合いは英単語の頭文字をとって「P値」と呼ばれるが、実際にはそれぞれのUFO目撃報告がどれだけ信用できるかを数字で示そうとするものであり、むしろ「信用度」というべきものである。
たとえば、目撃者がひとりしかいなかったり、証言が幻覚であったり、ウソであったりする可能性が高い場合にはP値は低くなる。逆に、複数の目撃者がいたり、物理的な証拠が見つかる場合はP値が高くなる。同様に、ストレンジネスは「奇妙度」と訳されている。つまり、報告の中に風変わりな要素がどれだけ含まれるかを評価したもので、やはり10段階で評価され、その度合いは「S値」と呼ばれる。
ハイネックは、鳥や飛行機など通常の飛行体とは異なるパターンで飛ぶ飛行体が目撃された場合、奇妙な点は不思議な飛び方だけになるが、目撃と同時に車のエンジンが止まったり、地面に痕跡が残ったりすれば奇妙度は高くなるとした。
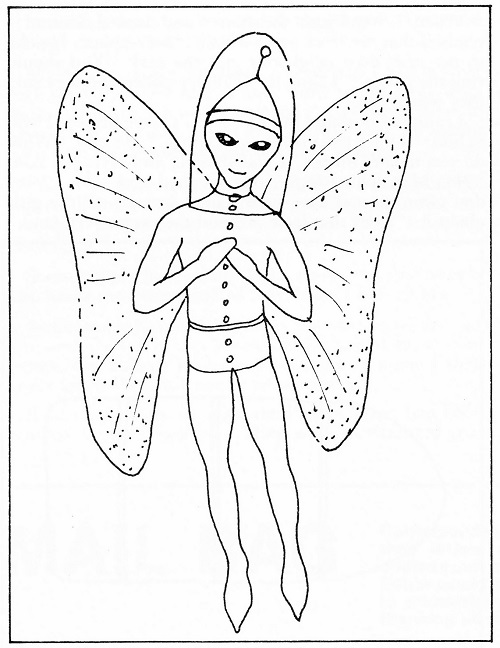
当然ながら、UFOとともに異星人らしき生命体が目撃される第3種接近遭遇の事例は、一般にS値が高くなるが、中でも特に奇妙で、不可解な要素の多いものは「ハイ・ストレンジネス事例」と呼ばれる。
ハイ・ストレンジネス事例の中には、異星人などの生命体が突然現れたり消滅したり、アブダクションされた人物が空を飛んでいくなど、日常の合理性がほとんど崩壊し、心霊体験や夢の世界にも通じる非現実的な内容のものもある。人類より遙かに知能が高いはずの異星人たちが、われわれの常識ではまったく理解できない非合理な、ときには滑稽ともいえる行動を示したりするのだ。
S値がどれくらいであればハイ・ストレンジネス事例と呼ぶべきか、明確な基準はないようだが、イギリスのマイク・ダッシュはそのような事例として、1977年にブラジルで起きたアントニオ・ラ・ルビアの事件や、1979年にイギリスで起きたヒングリー夫人の事件、MIB事例などを取りあげている。
しかし、南アフリカのシャーマン、クレド・ムトワが語る経験は、奇妙度においてこれらの事件に劣るものではない。

ムトワは1921年、南アフリカの最大部族・ズールー族の家庭に生まれた。父親がカトリックに改宗していたため、子どものころはミッション・スクールに通ったが、母方の祖父がシャーマンだったことから、その後祖父に弟子入りしてシャーマンとしての修行を積んだ。その過程で、「サンゴマ」と呼ばれる奥義に通じたシャーマンにしか伝えられない数数の秘密の知識を得た。
そうした知識の中には、古くから地球に住む「チタウリ」というレプティリアンの存在も含まれていた。
チタウリという名称自体は、2012年のアメリカ映画『アベンジャーズ』にも仇役で登場したから覚えている方も多いだろうが、本来はムトワのいうレプティリアンの一種であった。

そのムトワは、自らアブダクションされてジンバブエの地下にある秘密基地に連れていかれた経験や、グレイタイプの異星人の肉を食べたことがあるなどとも述べている。
ムトワによれば、グレイもじつはレプティリアンの一種で、チタウリの部下ということだが、アフリカ南部の小さな国レソトにあるラリベ山には、グレイの乗ったUFOがしばしば墜落し、グレイの死体が見つかることがあるという。そして一部のアフリカ人は、彼らを神とも信じており、その力にあやかって儀礼的にその肉を食べることがあるというのだ。
ムトワ本人は1998年、レソトの友人からその肉を分けてもらい、その友人夫妻と一緒にそれを食べたことがあるという。その効果はてきめんに現れた。
次の日、肉を食べた者の全身に激しい発疹が無数に生じ、舌は腫れて、数日の間瀕死の状態になってしまった。しかし、4、5日が過ぎると発疹はおさまり、全身の皮膚がはがれはじめた。その様子は蛇が脱皮するようでもあったという。
この回復期が始まると、まず精神状態に影響が生じた。だれもが些細なことで何時間も笑うようになり、その期間が過ぎると、今度は感覚が非常に鋭敏となった。ムトワによれば、水を飲んでもワインのような味を感じ、同時に自分が宇宙の中心にいるように思えたという。どうやらグレイの肉には強力なドラッグのような作用があるらしい。こうした状態は2か月以上続き、やがて通常に戻ったというが、グレイの肉を食べて死んだ者もいるという
フランスのUFO研究家ジャック・ヴァレが報告するロシアの事件も、かなりストレンジなものである。
ヴァレは1990年1月初頭、「グラスノスチ」で西側に対しても情報公開を行うようになったソ連を訪れ、ウラジミール・アジャジャやアレクサンドル・カザンツェフといったロシアのUFO研究家とも意見交換を行った。

訪問の主要な目的は、1989年に起きたヴォロネジ事件に関する情報収集であったが、ほかにも多くのUFO情報を集めて帰国した。以下に紹介するのは、このときヴァレがソ連で採取した事例のひとつである。
事件は、モスクワの東890キロほどのところにあるウリヤノフスクという町で起きた。事件の当事者はNという仮名で紹介されている。
その日、Nの家庭では妻と子が先に家を出てしまっており、彼自身もまさに仕事に向かおうとしていたときのことだった。だれかがドアのベルを鳴らした。Nは妻が忘れ物を取りに戻ったのだろうと思い、疑うことなくドアを開けると、そこには見知らぬ男が立っていた。
男の身長は2メートル10センチほどもあり、銀色のつなぎとブーツを身につけていた。男は「自分は異星人なのだが、食べ物を必要としている」と述べた。
Nはあまりに驚いたので、何も考えることもできないまま男を台所まで案内し、そこにある食品を新聞紙にくるんでやった。しかしもう出かけないと仕事に遅れてしまう。Nがそのことを告げると、相手は特殊なアクセントのある、低いしわがれた声で「わかった」といった。
そこでふたりは家を出て、Nはドアの鍵を閉めた。異星人を名乗る男は、そこまで食料を包んだ古新聞を抱えて一緒にいたが、Nがバスに乗ったときには、姿は見えなくなっていた。
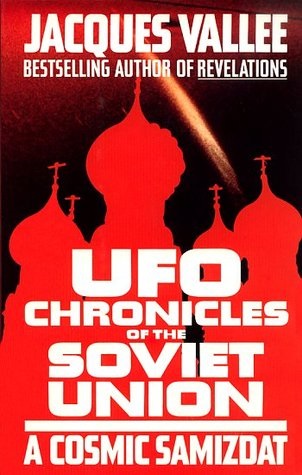
こうして仕事場に着いたNだが、どうにも胸騒ぎがしてならない。家に帰らなければならないという気持ちがどんどん強くなり、ついには理由を見つけて早めに帰宅した。帰って台所に入ると、信じられない混乱状態になっていた。
床の至るところに空の紙袋や箱、包装紙が散らばっており、米やキビといった穀物の粒、塩などがひびわれの中に残っていた。冷蔵庫や食料棚を確かめてみると、空だった。夕食の材料はもちろん、蓄えていたはずの食品類がまったくなくなっていたのだ。
呆然としているところに、Nの妻も帰ってきてこの惨状に気づいた。当然のごとく、彼女はいったい何が起こったのかとNに激しく詰め寄った。Nも最初はなんとかごまかそうとしたのだが、とうとう最後に、謎の異星人について話した。もちろん妻がそんな話を信じるはずもない。その後、N夫婦は離婚の瀬戸際まで行ってしまったようだ。
ヴァレは、そのようなことは接近遭遇の経験者にはよくあることだと締めくくっている。
このようなハイ・ストレンジネス事例で、特にP値が低いものについては、ありえない戯言として相手にしようとしない研究者もいる。しかし、案外こうした不可思議な事例こそ、UFO問題の本質を解明する手がかりになるのかもしれない。
羽仁 礼
ノンフィクション作家。中東、魔術、占星術などを中心に幅広く執筆。
ASIOS(超常現象の懐疑的調査のための会)創設会員、一般社団法人 超常現象情報研究センター主任研究員。
関連記事
UFO=空飛ぶ円盤を世界に認識させた 「ケネス・アーノルド事件」/羽仁礼・ムーペディア
UFO、UMA、心霊現象から、陰謀に満ちた事件まで、世界には不可思議な事象や謎めいた事件があふれている。ここでは毎回「ムー」的な視点から、それらの事象や事件を振り返っていく。今回は、「UFO事件史の幕
記事を読む
アメリカUFO歴史記録センター誕生へ! ハイネック資料も収蔵し、ブルーブック計画の機密情報も完全公開か?
古今東西のUFO情報を完全収集・一元管理する画期的プロジェクトが立ち上がった。近未来のUFO研究環境にもたらされる劇的変化とは――!?
記事を読む
太古の大地が宇宙生命体を呼んだ!?「四国カルスト」の奇妙なUFO写真/寺田真理子
太古の地形「四国カルスト」上空にUFOが出現?! 天体写真家が収めた一連の「奇妙なもの」は、成層圏に潜むプラズマ生命体か?
記事を読む
ペンタゴンの「バグダッドファントム」UFO流出! 熱を発しない円筒型物体を隠蔽する調査組織の闇
UFOの調査部署を立ち上げ、情報も続々と公開する姿勢を示していた米国防総省。しかし実態は――!?
記事を読む
おすすめ記事

