61年間寝ない“不眠人間”の謎! ショートスリーパーの研究・実践の最前線に迫る
不眠人間やショートスリーパーと呼ばれる人たちの身体ではいったい何が起きているのか? 健康への影響は? 研究・実践の最前線に迫る!
記事を読む

2021年4月24日、アメリカで、森林に姿を消す巨大な獣人を女性が目撃するという衝撃の事件が起きた。獣人とは、もちろんビッグフットである。アメリカに限らず、古くから報告が続くビッグフット、そしてその近縁と考えられる獣人とは、いかなる生物なのだろうか?
目次

それはアメリカ合衆国オハイオ州アシュランドの東郊外にある、古い倉庫を改造して3年前に開業された終日無休の「ウエアハウス24時間ジム」のすぐ近くで、だしぬけに起こった。
今年の4月24日、まだまだ肌寒い陽気ながら空はすがすがしく晴れ渡った真夜中過ぎ、ジムの機械で心地よくひと汗かき終えて外へ出てきた地元在住のジーン・マージョリー(仮名、20歳)さんは、照明のあかあかと明るい駐車場に置いてある自分の車のほうに向かいかけて、ふと足を止めた。
右手の大森林の中から、地上の枝木をバキッバキッと踏みしだく音がしたので思わず振り向くと、30メートルほど離れた倉庫の脇あたりにそいつがいる! 全身灰色がかった毛むくじゃらで、背丈がゆうに2メートル半、体重200キロはありそうな巨大な獣人が、太い両腕を大きく前後に振りながら、人間より明らかに早い足取りで森林の中へすたすた入っていく。
まっすぐ前を向いていて、ジーンを襲ってきそうな気配はなかったが、それでもジーンは声にならない悲鳴をあげた。
恐怖のせいかその後のことはよく憶えていないが、とにかくジーンは近くの終夜営業レストランに飛び込んで助けを求めた。全身の震えがいつまでも止まらず、自分ではとても運転できそうになかったので、両親に電話して迎えにきてもらった。
後日、目下の段階では一番最近(そうではないことがすぐ判明するが)の“ビッグフット接近遭遇”事件を調査したカリフォルニア在住の専門家マシュー・マネーメーカー氏によれば、彼女はこの恐怖の体験を友人や勤め先の同僚に隠さず打ち明けたところ、予想に反してみなに揶揄されたり笑って首を振られたりしたため、結局、実名での公表を拒むようになった。
マネーメーカー氏はかれこれ30年以上も前から、アメリカからカナダにかけた一帯が主要棲息地と想定される未知動物、ビッグフットないしサスカッチ現象の実地調査と科学的研究に取り組んできた民間のアマチュア学者だ。
1990年代に自ら創設したBFRO( ビッグフット野外調査者組織“フィールド・リサーチャーズ・オーガニゼーション”)を率いる在野のベテラン未確認動物学者(クリプトゾオロジスト)──もっと平たくいえばUMA学者で、この研究調査の分野では、アメリカとカナダを含む北米大陸中につとに知られる人物だろう。
ただし、ここでUMA(未確認神秘動物の頭字語)とは、UFOに倣ったあくまでも和製英語で、日本以外では通用しない用語だ。僭越ながら実は本稿の筆者(南山)が1976年に必要があって考案した新造語で、それ以降日本ではマスメディアで使用されることが多く、またインターネット上でも日本語のウィキペディアに限っては、この用語の項目が立つようになっている。



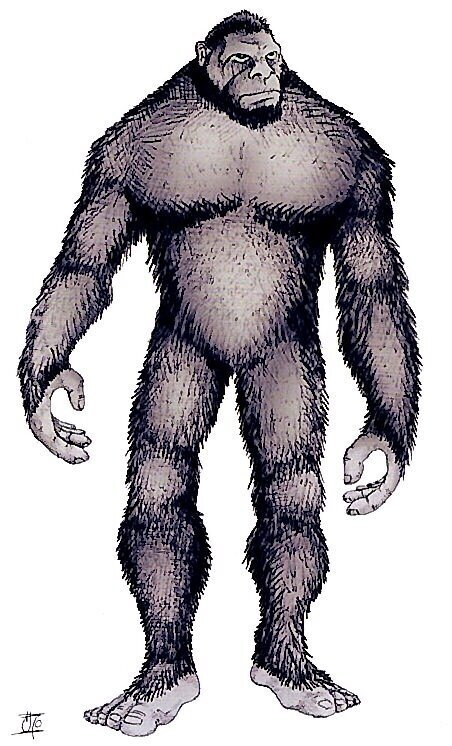
その未確認動物学上(ク リプトゾオロジー)で現代における3大ミステリーとされるのは、時が止まったかのようなニューギニアや中央アフリカの原始林地帯に出没する中生代から生き残った恐竜や翼竜、海洋で船舶がときに遭遇するシーサーペントやネッシーに代表される世界各地の湖沼怪獣、そしてビッグフット/サスカッチのように険しい山野に隠れ棲む類人動物(擬人動物)だろう。
このうち前二者に関しては別の機会に譲るとして、残るビッグフットはもちろん英語で“大足男"を意味する。
これは特に北米のビッグフットの棲息地と目される地帯では、水辺の軟弱な砂地や山野の雪原に、全長40から50センチもある文字どおり“大きな足跡”を点々と残して去る正体不明の巨人を意味している。
サスカッチのほうは、語源が今ひとつはっきりしないが、主としてカナダのとりわけ北西太平洋沿岸部に太古から住んでいた先住民(いわゆるアメリカインディアン=略称アメリンド)諸部族中のハルコメレム族語で、“野生人(ワイルド・マン)”を意味する“セスクワチ”が語源というのが、ビッグフット研究者の間ではほぼ定説とされている。
成獣はゴリラのような巨体だが、体形はもっと人間に近く、全身長い体毛に覆われ、直立二足歩行する類人動物で、目撃報告による限りでは、姿形も大きさもビッグフットとほとんど変わらない。
このほか未確認動物学者やUMA研究家たちの間では、アメリカのフロリダ半島を中心に広く目撃されるスカンクエイプ(高温多湿の亜熱帯のせいか、目撃地点にいつも強い悪臭を残すのでこの名がある)、似たような気候のインドネシアの獣人オランペンデク、マレーシアのオランマワス、それとは真逆な寒冷気候のコーカサス地方やパミール山脈中に棲息する猿人アルマス、北方ヨーロッパ伝承の怪人ウデワサ、やはり寒冷な中国奥地やモンゴルの野イエ人レン、さらには遠くオーストラリア東部の山野で目撃される両腕の長いヨーウィ、そしてこの種の多毛の怪物としてはもっともよく知られるヒマラヤの“ おアボミナブル・スノウマンぞましき雪男”イエティなどなど、すべてビッグフットの同類か近縁種と見なされている。
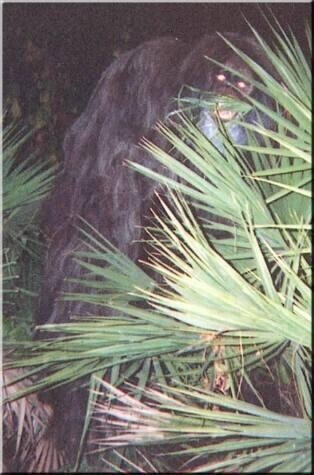

1967年10月21日の午後遅く、米カリフォルニア州ユーレカの原始林地帯を今日も馬の背に揺られて進んでいくロジャー・パターソン(34歳)とボブ・ギムリン(29歳)は、6年も続いた実りのない大捜索の苦労がとうとう報われた。
枯れ川の砂地の中で、馬が前方100メートルあたりを歩いていく毛むくじゃらの巨人に驚いて、突然棒立ちになったのだ!
「ボブ、銃で掩護するのを忘れないでくれよ‼」
ロジャーは前進しながら、夢中でコダックの16ミリカメラを回した。撮影対象はがっしりとした体格で、全身が光沢のある黒く短い剛毛に覆われている。ゴリラに似てなくもないが、歩き方は人間特有のものだった。
長年捜していた“アメリカの雪男”ビッグフットにとうとう出遇えたのだ!
こちらの気配を感じたのか、怪物は不意に足を止めて、ゆっくり振り返った。その顔も、大きな鼻と頬のあたりを除いて、一面黒い毛に覆われている。
一瞬、ふたりはヒヤリとしたが、怪物は別に怒りも驚きも見せず、ほんの数秒間、黒い目でこっちを見つめただけだった。そして、再びプイと顔の向きを戻すと歩き出し、やがて川床から岸に上がると、森林の中へと分け入って姿を消した。
ふたりともすぐ気づいたのは、怪物の胸に大きな両の乳房が垂れ下がっていたことだ。やはり黒い毛に覆われていて、歩くたびにユサユサと揺れていた。あれは雌のビッグフットだったのだ。
もうひとつ気づいたのは、怪物が立っていた付近に近づくと、胸のむかつくような悪臭が漂っていたことだ。
「ちょうど犬が雨に濡れたときに発散するあの臭いを、100倍強めたみたいな──」とふたりは口を揃えた。
目撃後しばらくしてから、ふたりはまだ用心しながら森林の中へ踏み込んだ。人間より何倍も大きい足跡が点々と地面に印されていたので、こんなこともあろうかとかねて用意してあった石膏でその足型も注意深く採取し、さらにメジャーで足跡の寸法と歩幅も計測した。歩幅は川床より森の中のほうが1.6倍以上も長く、明らかに走り出したことを物語っていた。
「伝説の怪物“大足男”ついに世界初の撮影に成功!」
このビッグフット撮影に初成功という未確認動物学史上画期的な事件は、地元ユーレカの「タイムズスタンダード」紙の一面トップを飾り、アメリカ・カナダ両国の動物学界や人類学界に、本物かイカサマかと激しい論争を巻き起こした。




大半の学者の反応は否定的だったが、ごく少数ながら全米沿岸測地局の生態学者ジョゼフ・レイト博士、スミソニアン研究所霊長類部長ジョン・ネーピア博士、ブリティッシュコロンビア大動物学部イアン・コーワン教授など、興味を示した科学者もいた。
彼らを代表してエモリー大学ヤーキス地方霊長類研究センターのオスマン・ヒル博士は、こう断定している。
「霊長類なのはまちがいない。しかも類人猿などではなく、ホミニッド(ヒト科動物)だ。歩行の際の直立姿勢、歩き方、体の動かし方、骨盤から胸部、四肢へかけてのプロポーションなど、すべてがヒト的である」
ただちょっと疑問なのは、従来の古人類学的観点から見ると、少なくともこれまでのところ北米大陸では、類人猿はおろか猿の骨ひとつ化石として発掘されたことがないのに、そのようなホミニッドがはたして存在可能だったかという点だ。
だが、この疑問に対しても、生態学者のレイト博士は肯定的にこう推定してみせる。
「類人猿も猿類も本来は熱帯性動物だから、そのような北部の寒冷な高地にまで進出してくるとは考えられない。しかし、ホミニッドはもともとみな寒冷気候の土地に棲んでいた。たとえばネアンデルタール人などは、氷河地帯にまで進出していた証拠がある。
こうした毛深い巨大なホミニッドが、北米大陸とアジアの間に形成されたと考えられる陸橋、たとえば、海面が今より低かった氷河期に、現在のベーリング海峡に架かっていた陸橋などを渡って、アジア大陸から移住し、サスカッチやビッグフットの祖先となったという可能性も大いにあるだろう」
一般にわれわれ黄色人種の祖先が、アジアからベーリング陸橋を渡って北米大陸に進出し、さらに中米・南米と南下していって、先住民アメリンド(前出)となった──というのは古人類学上の定説だが、もし異端派学者のレイト博士の主張が真実を衝いているとしたら、まったく同じルートをアメリンドの祖先たちよりひと足お先に、ビッグフットの祖先たちが辿ったことになるわけだ。
ここでちょっと脱線するが、もしアジアにいたビッグフットの祖先の一部がいわば寄り道して、まだ部分的に大陸と地続きだったかもしれないのちの日本列島に上陸した可能性を前提にすれば、日本に棲息するとされるいささか都市伝説的なあの“獣人ヒバゴン”も、合理的に説明がつくかもしれない。
1970年7月20日、広島県比婆郡西城町(現庄原市西城町)でトラックの運転男性が走行中、人型の怪物が目の前の道路をゆっくりと横切るのを目撃した。身長1.6メートルぐらいで小柄なタイプだが、体つきはがっしりとゴリラ似で、全身が黒い毛むくじゃらだったという。74年には不鮮明ながら写真にも撮られ、さらに80年にもわずか10メートルの近距離で、水道局員が睨み合ったそうだ。




しかし、世界のさまざまなビッグフット型類人動物の中で、われわれ日本人にいちばん馴染み深いのは、やはりなんといっても本家ともいうべき“ヒマラヤの雪男”イエティだろう。
「世界の屋根・ヒマラヤの最高峰エベレストの標高は、衛星を使った最新精密計測の結果、これまでの公認記録より86センチ高い8848メートル86センチ、とこのほど判明した!」
昨年12月8日、ネパール政府と中国政府がそんな合同発表を行ったのはまだ記憶に新しいが、そのヒマラヤの名物のひとつとして知らぬ者はないあの雪男の存在が文明世界に知られるようになったのは、150年ほど前に白人の登山家や探検家が現地で実物の雪男を目撃したり、雪面に点々と印された大型の“人の足跡”らしきものにしばしば出くわすようになってからだ。
近年の日本人登山家・探検家に限るなら、ダウラギリ4峰を征服した大ベテランの服部満彦氏が、1971年にヒマラヤ山中で思いがけず遭遇して、後日こう証言した。
「ヒッピーのような長髪で猿に似た顔の、人間のように二足歩行する背の低い雪男にバッタリ出くわした。向こうのほうが慌てて逃げ去ったが、15メートルほどの近距離だったので、こっちも驚いた」
成人ではなくまだ未成年の雪男だったのか、それとも背の低い短躯型の別種の雪男が存在しているのだろうか。“雪男の足跡”の日本人発見者としては1959年、小川鼎三(ていぞう)東大教授が率いる日本初の“ヒマラヤの雪男”探検隊、そして福岡大学ヒマラヤ・ネパール探検隊が最初となった。1968年には、玉川大学教育学部の学生だった三瓶(みへい)清朝氏が、チュギマゴ峰の東側で発見して写真に撮っている。
また翌1969年の1月末、九州大学理学部の大学院生で山岳部OBでもあった高山哲信氏が、ランタンヒマールとカトマンズの中間付近で、雪男のものとおぼしき大きな足跡の列を雪面に発見。写真に撮って持ち帰り、朝日新聞4月26日付朝刊に掲載されて、エヴェレスト登山や雪男探検を目指すロマンチストたちの憧憬をいっそう掻き立てた。
もっと最近では1991年5月、札幌市在住のデザイナー・小山哲氏が、インドからネパールまで放浪の旅を続ける途中、ヒマラヤ中腹の原生林をトレッキングしていて目撃した。
「ふと左後ろを見たら、10メートルぐらい後方に前屈みで2本足で立ち、両手をぶらんと下げ、全身黄褐色の毛に覆われた生き物がいたんです。顔にも毛が生えていて、体長は150センチほどでした」
そのときの小山氏は、相手が小柄なので雪男とは思いもよらず、てっきり新種の珍しい猿か何かだろうと憶測した。
「目と目が合って、お互いビックリして固まりましたね。でも、その直後、そいつはピョーンピョーンと力強く跳びはねながら、林の奥へ消え去りましたが、今ではあれがイエティだったんだと確信しています」
先の服部氏の目撃談と共通点が多いのが、まことに興味深い。

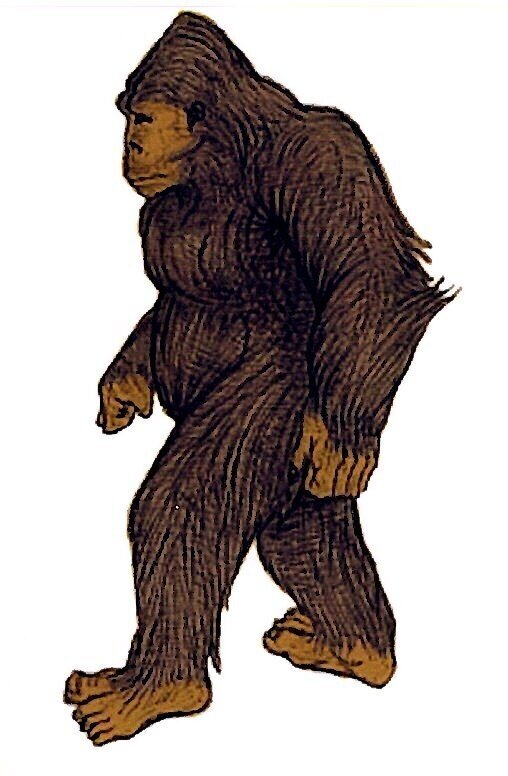






第2次世界大戦終結直後から始まったアメリカとソビエト連邦(現ロシア)の東西冷戦(政治的・軍事的対立)とはおそらく無関係だろうが、旧ソ連とその支配下の旧共産圏諸国の“雪男学”は、アメリカのビッグフット/サスカッチ研究とはまったく交流関係のないまま、独自の発展を遂げてきた。
実際、アメリカよりもはるかに広大なロシア領土は、大部分が未開の土地で、地理的にも気候的にも雪男がひっそりと隠れ棲むにはうってつけだし、目撃事件もヒマラヤや北米大陸以上に数多く報告されているようだ。
ロシア語では雪男のことをスネズニー・チェロベック(文字どおり“雪男”の意)というが、一般的にはモンゴル語のアルマスないしアルマスティ(獣を殺す者の意)が好んで使われることが多い。
もっとも、ロシアの領土内には少数民族がたくさん住んでいるので、コーカサスではカプタル(山を登る人)、パミールではクシギーク(黒く嫌らしい奴)などのほか、ミチェー(熊人間)、ズーテー(牛熊)、ミゴイないしミゴー(野生人)、ブンマンチ(密林の人)、ミルカ(野生人)、カンアドミ(雪男)、フエレン(雪人)などなど、20種類以上のさまざまな呼び名が使われている。
1950年代以降、そうした情報にきわめて詳しいロシアきっての“雪男通”として知られた歴史学者のボリス・ポルシュネフ博士は、さしずめ旧ソ連時代に活躍したいわゆる“雪男学”の確立者といえるだろう。
博士は当時の「ソ連科学アカデミー」内に公式に設置された“雪男特別調査委員会”を率いて、積極的にデータの収集にあたり、2000件を超える目撃事件や関連事件の記録が集められた。
博士によれば、それらの記録の中には、住民が“雪男を捕えた”という驚くべき事件が10件以上もあるという。いずれもロシア領内と、ロシアと国境を接する中国の山岳地帯で起きている。
もっとも古い記録のひとつは、1910年にモスクワ大学の若き動物学者V・A・カークロフ博士が、中央アジアのズンガリア地方でふたりのコサック人から取材聴取した事件だ。
雪男は村人に捕えられて飼われていたが、背が低く、全身を毛で覆われ、膝まで届く長い両腕を持ち、脚はがに股で膝が曲がっていた。顔は眉が目の上に突き出、鼻は小さいが鼻の穴は大きく、耳たぶのない尖った大きな耳をしていた。足型はヒトそっくりだが、横幅が異常に広くて、足の指と指の間が大きく離れていたという。
カークロフ博士は、同じように捕えられた雌の雪男(雪女?)を見た、という別の証人にも出会った。この雌はマナス川近くの農夫に捕えられて、数か月間飼われたが、その姿形は前記の雪男とよく似ていたという。
彼女はめったに声を出さなかったが、ただ近づくと歯を剥き出して威嚇し、眠るときは頭を抱え、膝を折り曲げ、うつ伏せに頭を床につけるという風変わりなポーズで眠った。初めのうちは生肉しか食べなかったが、慣れるにつれてパンにも手を出すようになった。また虫が近くにくると、ひょいと取って食べたりした。水を飲むときは腹這いになり、器に顔を突っ込んだり、手を濡らして口に垂らし込んで飲んだ。
哀れに思った村人が縛ってあった鎖を解いてやると、彼女は長い両腕をだらりと垂らしたままよたよた歩き出し、すぐに走って近くの森の中に姿を消したという。
後年、ポルシュネフ博士がこれらの証人たちに、チンパンジーとゴリラと化石人類(ネアンデルタール人)の復元図を見せたところ、3人とも躊躇せずにネアンデルタール人を指さしたそうだ。
博士はこうしたデータに基づいて、雪男の存在を説明する大胆な仮説として、雪男=ネアンデルタール人説を立てた。
博士の仮説によれば、ネアンデルタール人は今から数万年前に2種類に分化し、一方は脳と神経系が発達してわれわれ現生人類の祖先となり、もう一方は肉体は強大になったものの、知能は退化してしまった。アルマス型の雪男は、後者の種類の遠い末裔である可能性が大きいというのである。
ポルシュネフ博士は旧ソ連時代におけるロシア国家公認の“雪男学者”だが、国家的スケールの公認“雪男学”なら、隣国の中国も負けてはいない。
第2次世界大戦後、国共内戦(国民党軍と共産党軍の戦い)で後者が勝利して共産主義体制となった中国(中華人民共和国)国内では、ビッグフットかその近縁種の目撃事件が、それも実際には太古の時代から、北米大陸以上に多発していたように見える。


中国では一般に雪男は“野人”と呼ばれ、目撃事件はおおむね中央部の湖北・陝西(せんせい)両省、東南部の浙江省、それに西南部の雲南省とチベット自治区に集中している。
とりわけ1970年代に入って、湖北省西北部の神農架山付近の原始林開発が大々的に始まると、それとともに“野人”目撃騒ぎも飛躍的に増え、北京の中国科学院にはその目撃報告がぞくぞく寄せられるようになった。
1977年1月には、湖北省共産党委員会と中国科学院の肝入りで結成された“奇異動物調査隊”が、神農架地区に乗り込むまでになり、81年8月には中国人類学会が発起人となって、「中国野人調査研究会」という学術団体が正式に発足した。
アメリカでビッグフットの目撃騒ぎが始まったのは、第2次世界大戦後になってからだが、中国における野人目撃騒ぎの最古の記録は、なんと紀元前にまで遡る。
それによると、紀元前830年ごろ、周の宣王の世に、現在の湖北省西北部の神農架地区で“野人”ふたりが捕獲され、王に献上されたとその記録にはあるのだ。以後、2300年前の楚の憂国詩人・屈原が作った『九歌』中の“山鬼”の詩を始め、おびただしい数の古書古籍に“山人”“山大人”“山丈”“山精”“人熊”“毛人”“大毛人”“多毛人”から(人に似て人でない)“獲(おおざる)”“羆(ひぐま)”“ 狒狒’(ひひ)まで、時代と作者によってまちまちな呼称で登場する。
房県紅塔の西暦1世紀後漢の墳墓から出土した鋳銅製装飾物の残片には、“毛人”の姿が鋳込まれているし、ずっと下って17世紀清代に編纂された地理学書中には、こんな特異な記述が見られる。
「房県房山、山険しく石洞多し。多毛人、身の丈丈余、全身に毛生え、ときに人、鶏、犬を噛む──」
ちなみに1 丈の長さは、約3.3メートルに相当する。この“多毛人”はそれほど体がデカかったということだ。
ひょっとしたらこれもユング心理学でいう集合的無意識がもたらす、いわゆる“シンクロニシティ( 意味ある偶然の暗合)”というべきなのだろうか。
超常現象・超自然現象研究家である筆者は、自意識をもちはじめた幼年期から高齢期の現在に至るまでに、これまで何度となくこのシンクロニシティを経験しては、そのたびにわれわれが存在するこの無限の時空連続体に秘められた、目には見えない不可思議な“エネルギー場”の相互作用を、意識無意識に実感してきた。
だが、そろそろこの原稿も予定の枚数に近づいたので、どのように締めくくろうかと思案しはじめたとたん、またまたそのシンクロニシティが起きたのだ。
“ビッグフットとの遭遇”という本稿のテーマにぴったり沿った最新の目撃事件が、アメリカ合衆国南部で報告されたという最新情報が、インターネット経由で手元に飛び込んできたのである。
ついこの間の2021年6月10日、まだまだ日の高いうだるような暑さの厳しい真っ昼間、米アリゾナ州アパッチ郡チェンバーの5キロ西方、有名な化ペトリファイド・フォレスト石森林国立公園の32キロ東方に延びている2車線の幅広いハイウエイ、州間道路40号線上を、モーターホームに乗り込んで走行していたキャリー&ビル・ウエルドン夫妻は、にわかには信じられぬような眼前の光景に茫然となった。
ギラギラと明るい陽射しのなか、幅の広い2車線道路を悠然と横切っていくひとりの(1頭の?)ビッグフットを目撃してしまったのだ。もともとこのあたりはビッグフットの遭遇例が多いのは知っていたが、本物を見るのは初めての経験だった。
ウエルドン夫妻が取るものもとりあえず、カリフォルニアのビッグフット専門研究家マネーメーカー氏に、緊急報告のメールを送ったのは、もちろんいうまでもない。



南山宏
作家、翻訳家。怪奇現象研究家。「ムー」にて連載「ちょっと不思議な話」「南山宏の綺想科学論」を連載。
関連記事
61年間寝ない“不眠人間”の謎! ショートスリーパーの研究・実践の最前線に迫る
不眠人間やショートスリーパーと呼ばれる人たちの身体ではいったい何が起きているのか? 健康への影響は? 研究・実践の最前線に迫る!
記事を読む
UFOアブダクション現場で続く発光飛翔体と獣人UMAの遭遇……米アパッチ・シトグリーブスの謎
アメリカ最大のミステリースポットは先住民の聖地にして米軍が暗躍する禁足地だった!?
記事を読む
2023年のネッシー“公式”目撃事例「第1号」は10代少女の快挙! 本物認定に必要な条件とは!?
少女が目撃したネッシーが今年「第1号」として公式に認定された! 本物と偽物の意外な違いとは!?
記事を読む
正体は巨大オオウナギか、未知の水棲生物か? 池田湖の怪獣「イッシー」の基礎知識
毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、巨大な怪生物が棲むという伝説のある鹿児島県の池田湖で、多くの目撃報告が相次いだ水棲UMA
記事を読む
おすすめ記事

