干し首モコモカイや食人儀式、死後の世界をめぐるマオリの霊性文化とは……「マオリ怪談」を現地取材!
南半球の島国、ニュージーランド。そこにもさまざまな怪談が伝えられ、人々のあいだに息づいていた。怪談作家・田辺青蛙が現地レポート。
記事を読む

あなたに忍びよる異界。死者の骨に刻まれた禁忌の恐怖。
骨こぶりとは、葬式において火葬された親しい人の遺体の骨の一部を食べる風習で、「骨嚙み」「骨かじり」などともいう。これは死者の一部を体内に取り入れることで、その生命力や生前の能力にあやかったり、愛情、哀惜のために行うもので、恐ろしい前近代的な風習というわけではない。
ただし怪談として「骨こぶり」という言葉が使われる場合、この風習とは異なる食人行為にまつわる話が語られることが多い。この怪談にはさまざまなパターンがあるが、その内容はおおむね以下のようなものだ。
ある小学校での林間学校でのこと。生徒たちは山の中にある宿泊施設にて、3人ひと部屋を与えられていた。
そんなある日、ひとりの少年が尿意を催して夜中に目を覚ました。トイレは部屋の中ではなく、廊下を行った先にあるため、眠い目をこすりながらトイレに行って用をすまし、また部屋に戻ろうとすると、外から奇妙な音が聞こえてくることに気がついた。窓を覗くと、何かが暗闇の中で動いていて、ぼんやりと明かりが灯っている。
なんだろうと興味を抱いた少年は、こっそりと外に出てそれを見にいくことにした。足音を立てないように静かに近づくと、何者かが地面にうずくまっている。ぼりぼり、がりがりという音がしたため、それが何かをかじっているのだということがわかった。
少年がもっとよく見ようと草陰から身を乗りだすと、突然それが少年のほうを振り向いた。
それは人間の男だった。しかしその手に土だらけの白い何かをもっており、目は血走っていた。少年が恐ろしさのあまり慌てて逃げだすと、男は手元にあった懐中電灯を引っ摑み、「待て!」と叫びながら追いかけてきた。
少年は素早く宿に逃げ込み、自分の部屋に入って布団を被った。そして寝たふりをした直後、男が戸を開けて部屋に入ってきた。男は静かに少年たちの足元に近づいてくると、まず少年のふたつ隣に寝る同級生の胸に耳をあてた。
「お前じゃない」
そういうと、男は次に少年の隣に眠る同級生の胸に耳をあてた。
「お前でもない」
そして最後に少年のもとにやってきて、彼の胸に耳をあて、それから少年に向かっていった。
「鼓動が早い。お前だな」
直後、少年が悲鳴をあげると、男は慌てた様子で逃げていった。しかし宿泊施設は大騒ぎになり、男はあえなく捕まった。
後で聞いた話では、この宿泊施設のすぐ近くに土葬の風習が残る墓地があり、男は夜な夜なその墓地に行っては墓を暴いて遺体の骨を食っていた。男は不治の病にかかっており、その病を治すのに人骨が有効だという噂を聞き、そのようなことをしていたのだというーー。
話の舞台は病院だったり学生寮だったりして、同室のひとりが夜な夜な部屋を抜け出してどこかへ行くため、後をついていってみると墓を暴いて骨を食っていた、というパターンも多い。
また、目撃者を特定する方法として、心臓の鼓動ではなく、ほかの人間は布団の中で寝ていたため足が温かいが、目撃者は外に出ていたため足が冷たいとして足の体温を使って特定する話も見られる。
骨を食っていた理由は先述のように病を治すため、とされるものがほとんどだが、単純に人の骨や肉を食うのが好きなため、というパターンや、そもそも遺体を食っているのが人間ではない何かというパターンも存在する。
このように多様な形で語られる怪談だが、現代になって生まれた怪談というわけではない。実は近代以前にも同じ怪談が語られていた。そして、やはりその目的も病を治すためだった。

たとえば田中貢太郎の『新怪談集実話篇』(1938年)に収録された「死体を喫う学生」は北海道の大学を舞台にして語られる話だ。
主人公のMが寄宿舎で同室になった別の学生が真夜中に外に出ていくのを見かけ、こっそりとついていく、その学生が寄宿舎の近くにある墓場に向かった。Mが墓場に着いたところ、学生はひとつの石碑の下でうずくまっており、彼がMのほうを振り向くと、その口の周囲には、微かに赤いどろどろとしたものがついていて、そのために口が耳元まで裂けているように見えた。
Mは驚いて逃げだし、寄宿舎に戻って布団を被ったが、突然その布団の端をさっとまくられ、あの学生がMに向かって「見た、貴様見たのだな」と青ざめ、ひきつった顔でいうのが見えた。
Mはそのまま気絶したが、意識を取りもどすとすでにあの学生はいなかった。後になって、彼が癩病(ハンセン病)を患っており、死体がその薬となるという迷信から墓で人の死肉を食っていたのだという噂を耳にした、というところで話は終わる。
ほかにも松谷みよ子著『現代民話考7』にも戦前や昭和前期の寄宿舎を舞台にして同様の怪談が語られていた例が複数記録されている。同書では治療の対象となる病気は結核などとされている。
人の死体が生薬になるという迷信は古くから世界中にあり、古代エジプトのミイラが万能薬になるとして中近世のヨーロッパではミイラ取りが流行って盗掘が問題になった。日本でも江戸時代にはエジプトのミイラが薬としてオランダから輸入されていた記録がある。
このほかにも人間の体の一部を薬として使うことで病を治療するという考え方は広くあり、明治時代には薬の材料として人体の一部を使うことを目的とした殺人事件も起きている。
もちろん、現在では人間の体が不治の病に効くという話は医学的に否定されている。何より自分勝手な理由で死者の眠りを妨げる権利を、われわれはもっていないのだ。
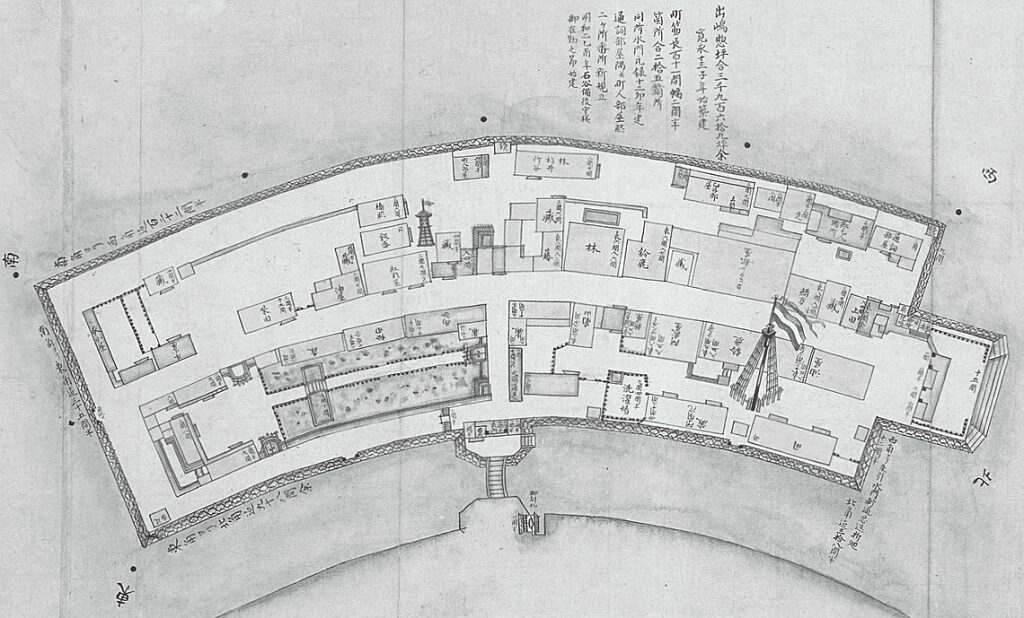
(月刊ムー 2025年1月号掲載)
朝里樹
1990年北海道生まれ。怪異妖怪愛好家。在野で都市伝説の収集・研究を行う。
関連記事
干し首モコモカイや食人儀式、死後の世界をめぐるマオリの霊性文化とは……「マオリ怪談」を現地取材!
南半球の島国、ニュージーランド。そこにもさまざまな怪談が伝えられ、人々のあいだに息づいていた。怪談作家・田辺青蛙が現地レポート。
記事を読む
興奮と幻想に包まれるインドネシア・トラジャ族の葬式に潜入! 究極の「死と生の共存」/小嶋独観
珍スポを追い求めて25年、日本と世界を渡り歩いた男によるインドネシア、トラジャ族の葬式と墓を巡る旅!(第3回)
記事を読む
トイレで聴こえる「カミをくれ」と異形の手/朝里樹の都市伝説タイムトリップ
都市伝説には元ネタがあった。「カミをくれ」 日常の一瞬が異界への扉を開く。
記事を読む
泣いて笑って、悪事をそそのかす? 「雛人形」の怪/黒史郎・妖怪補遺々々
今回も季節ものシリーズ! 3月の代表的イベントといえば、もう過ぎてしまったけど3月3日、ひな祭りですね。そこで欠かせない「雛人形」にまつわる怪異譚を補遺々々しましたーー ホラー小説家にして屈指の妖怪研
記事を読む
おすすめ記事

