タクシー幽霊と消えるヒッチハイカーと、帰ってくるおきくさん/朝里樹・都市伝説タイムトリップ
都市伝説には元ネタがあった。タクシー運転手がバックミラー越しに後を見るとそこには……。
記事を読む

昭和を彩った懐かしくも怪しい話を懐かしがりライターが回想。自動車、クルマが恐怖の対象だった、時代の心理を振り返る。
今回のテーマは少々漠然としているのだが、以前から「子どもの頃は自動車に関する怪談をよく耳にしたなぁ」といった感慨があって、それがずっと気になっていた。「怪談」と呼べるもの以外でも、昭和の時代はクルマにまつわる「怖い話」「不思議な話」「変な話」がアレコレあったはずなのだ。
そのあたりのことをちょっとまとめてみたいなと考えていたのだが、なんだかあまりにも散漫な話で、一本の原稿にはなりそうもないのでほったらかしにしていた。が、今回はちょっと試しにやってみようと思う。断片的でボンヤリとした考察にしかなりそうもないが、要するに「あの頃の子どもたちにとって、クルマは今よりも濃密な意味を持った“なにか”だった」といったことについて考えてみたいのである。
さて、まずは昭和世代なら誰にとってもおなじみのネタからはじめてみよう。
「霊柩車を見たら親指を隠せ!」というジンクスである。
親指を隠さないと親(僕が育った地域では「父親」とされたが、これにはバリエーションがあるらしい)が死ぬ(もしくは「死に目に会えない」)とされており、小学生時代、僕の周辺では「一般常識」だった。誰もがこの教え(?)を忠実に守っていたのだ。もちろんほとんどの子が「単なる迷信」と考えていたが、登下校中に霊柩車を見かければたいていの子は反射的に拳を握って親指を隠したし、僕などは「馬鹿馬鹿しい!」と思いつつも、うっかり親指を露出したまま霊柩車とすれ違ったりすると「うわっ、しまった!」と狼狽したりしていた。中には人前でやたら強がろうとするバカもいて、霊柩車が来るとわざわざ親指を突き立てた片手を上げて「ヤ~イ! ヤ~イ! ほら呪ってみろ~!」などとバチアタリなことを叫んだりもしていたが、こういうお行儀の悪いガキも含めて、結局のところほぼすべての子どもが「親指隠し」のジンクスに取りつかれていたのである。
思えば、あのころは下校中によく「霊柩車」を見かけた。もちろん、あの異彩を放ちまくるド派手な「宮型霊柩車」である。まさに荘厳な「走る“死”」といった感じで、子どもの想像力を思いっきり刺激するデザインだった。
昨今は「宮型霊柩車」は都心部ではほぼ見かけなくなり、黒いワゴンが主流になっている。あの異様なデザインが敬遠され、町中を走ると近隣住民から「怖い!」「不吉だ!」という苦情電話が寄せられることも多いらしい。そうしたことに配慮し、今では多くの火葬場が「宮型霊柩車乗り入れ禁止」になっているそうだ。いやはや……
以前、『般若心経講話』(鎌田茂雄・著/講談社学術文庫/1986年)という本を読んでいて驚いた。次のような一文があったのだ。
昔の老人は途中で葬式の行列にあったら、両手の拳を固く握り、歯をかみしめ、下腹部に力を入れて行き過ぎるがよいと教えたという。
なんと、「親指隠し」のジンクスは「霊柩車」が普及するはるか以前、「葬式行列」の時代からあったそうだ。それどころか、調べると江戸時代後期には広く知られていたようで、もともとは「死霊が親指の爪の間から入って生者に憑く」ことを防ぐための仕草だったのだとか。鎌田茂雄が書いている「歯をかみしめ、下腹部に力を入れ……」も、「丹田」に気を集めて全身に力を漲らせることによって、体内に侵入しようとする亡者を、「悪霊退散!」とばかりに跳ねのける意味合いなのだろう。

アホらしい昔話が続くが、もうひとつ、さらにアホらしいクルマにまつわるジンクスを。
「特定の色のフォルクスワーゲン・ビートルを目撃するといいことがある! もしくは死ぬ!」というジンクス、というか一種の遊びについてである。
この奇妙なゲーム(?)が流行したのは僕が小学校の低学年のころ(1970年代なかば)で、当時は自分たちの仲間内で考案されたローカルな遊戯だと思っていた。これが全国規模のブームであり、しかも70年代の一時期だけのものではなく、80年代以降も広く子どもたちに受け継がれていたことを知ったのは、インターネットが普及してさまざまな人の思い出話を俯瞰できるようになってからである。
この遊びのルールにも地域や時代によって無数のバリエーションがあるが、それらを列挙してもたいした意味はないだろう。うろ覚えだが、僕の周辺では次のようなものとして流布していた。
・黄色のビートルを見ると幸福になる。
・黒のビートルを見ると死ぬ。
・一日に3台のビートルを見ると幸福になる。
・一日に4台のビートルを見ると死ぬ。
「幸福になる」と「死ぬ」の極端な結果しか用意されていないところが、いかにも小学校低学年が考案した占いじみているが、実際はもう少し複雑で、ほかにも色や台数の組み合わせであれこれの占い結果のバリエーションがあったと思う。しかし概ねこのパターンが基本で、他の地域で流行したものも色と台数が違う程度だ。また女子の間では「恋占い」的なルールも知られており、「〇色のビートルを見ると意中の人との恋が叶う」「〇色だとフラれる」といった遊びも普及していた。
なんでこんなアホらしいことが全国規模で流行ったのかはよくわからない。起源も由来も不明だ。ネット上にはさまざまな説が挙げられているが、僕としてはどれもまったくピンとこない。
「70年代はまだクルマが少なかったので、当時の子どもたちはクルマを物珍しがった」などといった荒唐無稽な歴史修正的言説は論外だとしても(都心部の交通量が飛躍的に増加した60~70年代は「交通戦争」の時代であり、子どもが犠牲となる交通事故が「社会問題化」していた)、「当時はまだ外車が珍しかったので……云々」というのもまったく当たらないと思う。
あくまで体感だが、ビートルを見かける頻度は、現在の僕らがニュービートルに遭遇する頻度よりも高かったように思うし、ワーゲン以外にも様々な外車が走りまわっていた。そもそもビートルがそれほど珍しかったらこの遊びは成立しない。むしろ「やたら見かける」からこそ考案されたのだろう。「ビートルはナチスの影がちらつく不吉なクルマであり……云々」にも説得力はない。当時の大半の子どもは、ビートル誕生の背景にヒトラーの意図があったことなどは知らなかっただろう。
また、「この遊びを楽しんでいたのはほとんどが男子だった」というのも、僕の体験とはまるで食い違う。女子たちも盛んに楽しんでいたどころが、あくまで僕の推論だが、そもそもが女子発信の遊びだったのではないのか、という気がする。
この種の「占いごっこ」が男児文化から生まれるケースはあまりなく、たいていは女子たちが考案して夢中になり、それが男子に波及するというパターンが多いのだ。「なぜ対象がビートルだったのか?」ということについても、ものすごくアホっぽい仮説だが、単に「カワイイから!」だったのではないだろうか? 他のクルマと違って女子の琴線をも刺激するキュートなデザインだからこそ、ことさらビートルがセレクトされたのかも知れない。さらにまったく裏が取れないまま無責任に推察すれば、何らかの元ネタが当時の少女マンガ誌、あるいは「いちご新聞」などに掲載されていたのではないかとも思う。当時は小学生女子たちの間でさまざまな「ジンクス遊び」「おまじないごっこ」が流行しては消えていったが(誰かと同時に同じ言葉を口にしたときに「ハッピーアイスクリーム!」と叫ぶ、とか)、多くが少女マンガ経由で普及している。そうしたもののひとつだった可能性が高いと思うのである。

さて、肝心の「クルマにまつわる怪談」である。先述の通り、そもそもこうしたことを書こうと思ったのは、最近は「クルマ怪談」をあんまり聞かなくなったなぁという曖昧な感慨があったからなのだ。以前、この連載で「タクシー幽霊」を取り上げたが、ここでいう「クルマ怪談」はあの種のものとは違う。誰かが運転中に霊を見たといった話ではなく、クルマそのものが「霊的」なものとして登場する怪談、「クルマそのものが怖い!」といった怪談なのである。
かつてはこの種の話にも無数のバリエーションがあって、よく子ども向けの「心霊本」などで目にしたのは「世界的に有名な呪われたクルマ」を紹介する記事。定番ネタとして頻繁に登場していたのがジェームズ・ディーン所有のポルシェだ。彼はこのクルマの事故で死亡したが、俳優仲間のアレック・ギネスはディーンに「そのポルシェに乗ると一週間以内に死ぬ」と警告していたといわれている。ポルシェは事故後もディーンの遺品として展示されたり、一部のパーツが販売されたりしたが、それらに関わった人々も奇妙な事故の犠牲になったという後日談もあるらしい。
またオーストリアの皇位継承者である大公がパレード中に妻ともども射殺された「サラエボ事件」。このときに夫妻が乗っていたベンツも「呪われたクルマ」として名高い。事件後、このクルマは次々と人手に渡ったが、その後の所有者のうち十数人が不可解な交通事故などによって死亡したそうだ。
……という怪談も定番なのだが、実はこのベンツは実在しない。そもそもクルマはベンツでもなく、もちろん呪いのエピソードも後世の作り話なのだが、呪いのベンツとして語られてしまっている。

どこまでが事実なのかわからないような逸話のオンパレードだったが、子どものころはこうした記事を読みながら鳥肌を立てていた。過去の事故によって無機物が「穢れ」てしまい、後々の所有者に「祟り」続けるという当時の「クルマ怪談」のパターンは、現在の「事故物件怪談」のフォーマットに近いのかも知れない。
もっと切実に怖かったのが、より身近な国内の「クルマ怪談」だ。特に「買った中古車がヤバかった!」という類の話には強烈なリアリティを感じた。これにも無数のバリエーションがあり、『あなたの知らない世界』の「再現フィルム」で毎年のようにさまざまなバージョンを紹介していた記憶がある。
過去に悲惨な死亡事故を起こした中古車を悪徳ディーラーに格安で売りつけられるというパターンが多く、運転中にハンドルやブレーキが利かなくなったり(単なる整備不良という気もするが……)、クルマが勝手に暴走して人混みに突っ込んだり、耳元で声が聞こえて驚いた瞬間に事故を起こしてしまったりと、さまざまな怪異が起こる。また、そのクルマのハンドルを握るとなぜか意味もなく凶暴な気分になって、自分の意思とは関係なく危険運転を繰り返してしまう、というような話も多かった。
そのほかの典型的「クルマ怪談」としては、事故で大破したはずのクルマが夜な夜な事故現場付近に出没するとか、こちらのクルマを追い越した途端にスッと消えてしまう幻の自動車とか、姿は見えないのにすさまじいエンジン音だけでうしろから煽ってくる透明自動車とか、あげていけばキリがないが、ともかく昭和の時代には多種多様な「呪われたクルマ」や「幽霊自動車」が、各地の道路を走りまわっていたらしいのである。
現在もクルマを題材にした怪談は一応は細々と語り継がれているようだが、「クルマが怖い!」という奇妙な感覚は、どうもあの頃の方がよほど強かったような気がする。
次回は、当時の子どもたちの間で語られていた「クルマをめぐる都市伝説」や「クルマが主役のホラー映画」などを紹介しつつ、当時の世の中にうっすらと漂っていたらしい「クルマが怖い!」という「気分」について考察してみたいと思う。
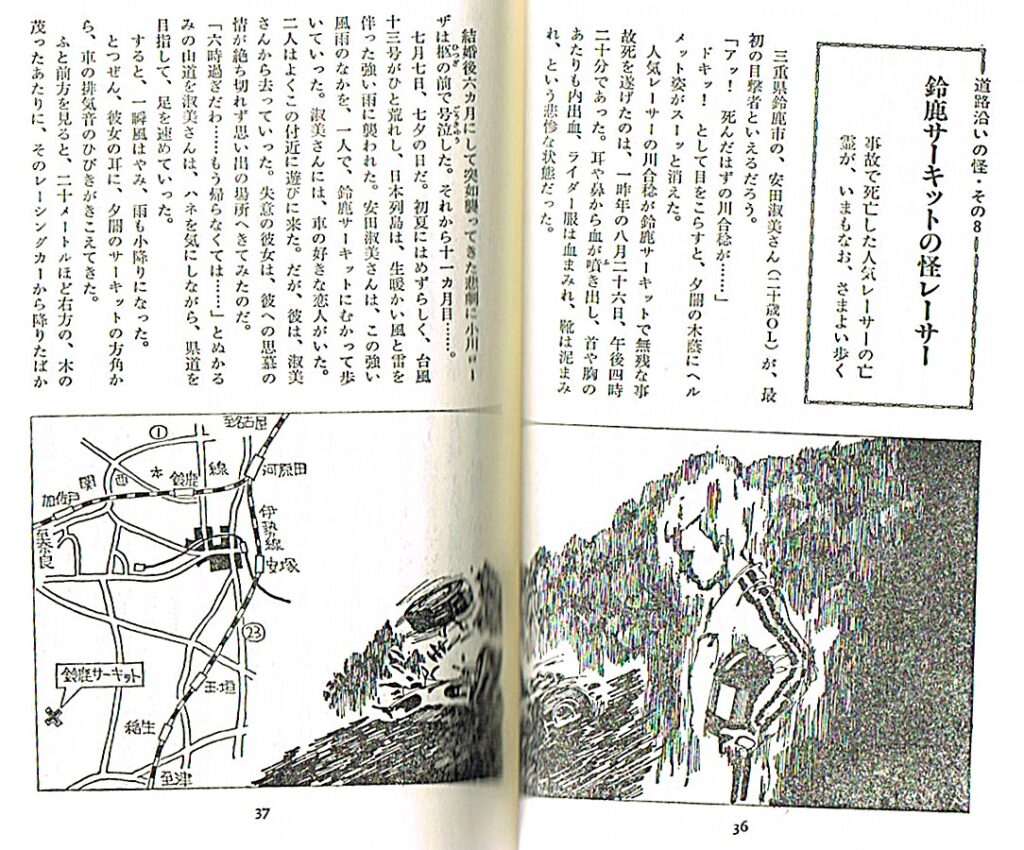
初見健一
昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。
関連記事
タクシー幽霊と消えるヒッチハイカーと、帰ってくるおきくさん/朝里樹・都市伝説タイムトリップ
都市伝説には元ネタがあった。タクシー運転手がバックミラー越しに後を見るとそこには……。
記事を読む
人がクルマが、まるごと消失! そして再出現!? 世界の「異次元消滅事件」ミステリー/南山宏
2019年12月30日、その日、走行中の自動車が断崖から転落、あろうことか跡形もなく姿を消していた‼ 本誌読者ならばおわかりだろう、これもまた、いわゆる異世界消滅事件のひとつである、と。こうした事件は
記事を読む
昭和の夏、8月の「戦争怪談」/昭和こどもオカルト回顧録
夏休みは、子供たちがお盆と戦争という定番テーマを振り返るタイミングでもあった。筆者の戦争にまつわる怪談とともに、当時を振り返る。
記事を読む
都市伝説「タイムリープ現象」の謎 ムー2026年01月号のカバーアート/zalartworks
「ムー」2026年01月号カバーアート解説
記事を読む
おすすめ記事

