業績好調の会社には「オフィスわらし」が潜んでいる?/朝里樹・都市伝説タイムトリップ
都市伝説には元ネタがあった。今回は、あなたのそばにもきっといる、おかっぱ頭のあの子ども。
記事を読む
文=初見健一

昭和オカルトブームを語るときに欠かせない妖怪「座敷童子」。民俗学的見地からその正体に迫る!
前回は70~80年代の昭和オカルトブーム期において、「座敷童子」がメディアなどでどのように扱われ、当時の子どもたちがそれにどんな印象を抱いていたのかを概観した。今回は第一次「座敷童子ブーム」(?)が起こったとされる20世紀初頭に遡り、ブームを先導した民俗学の分野の文献を参照しつつ、「そもそも『座敷童子』とはなんなのか?」といったことを見ていきたい。
言うまでもなく「座敷童子」を全国レベルで知らしめたのは、1910年に発表された柳田國男の『遠野物語』である。日本の民俗学の端緒となったこの説話集の文化的影響は絶大で、これにより文学の領域などで、さらにはその外側のよりポップな領域でも一大「怪談ブーム」が巻き起こる。幽霊、妖怪、各種祟りに神隠し、あれこれの土着神、山神・山人伝説に狐憑き……などなどの話題が大流行するわけだ。

ほぼ時を同じくして、日本では欧米のオカルトブーム、というか近代スピリチュアリズムの幕開けに呼応する形で降霊、催眠術、超能力(千里眼)などが流行し、世間にあれやこれやの波風が立っていた。いずれにしろ「座敷童子」も、この20世紀初頭の極東の島国における破格な規模のオカルトブームの流れに乗って旬のネタになったようだ。
ただ、民俗学的怪談ブームにおいて「座敷童子」が主役級のキャラとなっていくのは『遠野物語』刊行直後ではなく、その10年ほど後、あれこれの文化人が「座敷童子語り」をこぞってはじめた頃らしい。『遠野物語』のソース提供者であった伝承研究の大家、「日本のグリム」といわれた佐々木喜善が1920年に発表した『奥州のザシキワラシ』がブームの起爆剤だったという説もあるし、この本に触発されて宮沢賢治も『ざしき童子のはなし』を書いている。
ちなみに本連載では以前、この賢治の「座敷童子語り」をネタに、僕ら世代の子どもたちが楽しんだ降霊術ごっこ「スクエア」という遊びと「座敷童子」の関連を考察している。お暇があればご一読いただきたい。
民俗学において「座敷童子」は基本的に「零落した神」と考えられており、つまりは「妖怪」である。これは柳田國男の「妖怪観」の基本にあるもので、かつては民衆に恩恵をもたらしていた「神」が人々の信仰心の喪失とともに「聖」から「怪」へと属性を変え、「堕ちた神」=「妖怪」として再起動するという考え方だ。キリスト教的な「堕天使」=「悪魔」と誕生プロセスは似ているが、「妖怪」には邪悪一辺倒というイメージは薄く、悪行もすれば気まぐれに善行もする。いたずらに人を殺すこともあれば人を救うこともあり、そうした属性から民間伝承における「妖怪」は、畏れとともに愛嬌のある「いたずらっ子」として語られる場合が多い。気まぐれな殺人を「いたずらっ子のご愛嬌」で済ませていいのかという問題もあるが、ともかく「妖怪伝承」とはそうしたもので、その典型のひとつが例えば「河童」だ。子どもを溺死させることあれば溺れた子を救うこともあり、ときには子どもらと仲睦まじく相撲などを楽しみ、キュウリをやれば無邪気に喜ぶ異形の「堕ちた水神」。一般的な「河童」のイメージはそのようなものだろう。
さて、折口信夫に師事した民俗学者、池田彌三郎の著作『日本の幽霊』(1962年)には、岩手県の一部に「座敷童子の正体は河童だ!」という説があった、と記されている。遠野の町を流れる猿ヶ石川に棲む「河童」は気まぐれに人間の家に居つくことがあり、それが「座敷童子」と呼ばれるようになったという見解である。ともに「いたずらっ子」の典型的な「妖怪属性」を備えているが、「居ついた家に富をもたらす。去ればその家は退転する」というのも「河童」と「座敷童子」に共通する属性だという。池田によれば「河童が富をもたらす」という逸話は西の地方に多く、特に北九州にはそうした話が数多く伝承されているという。
某氏の家に「河童」が出入りするようになると、その家は急速に栄えはじめた。しかし「河童」が家の中を歩きまわるたびにそこら中が水浸しになってしまう。これに腹を立てた家主がつい叱ってしまうと「河童」はプイと出て行って、それ以来姿を見せなくなった。家はあっという間に落ちぶれ、見る影もなくなった……。こうした逸話が北九州の「家の守り神としての河童」の伝承の類型なのだそうだ。遠い西の国に伝わる「河童観」がどのように東北へ伝播したのかは不明だというが、川からあがった「河童」が頭の皿を取り外し(外せるどうか知らないけど)、着物を着こんで人の家に居すわると「座敷童子」になってしまう、というイメージはなんともユーモラスである。
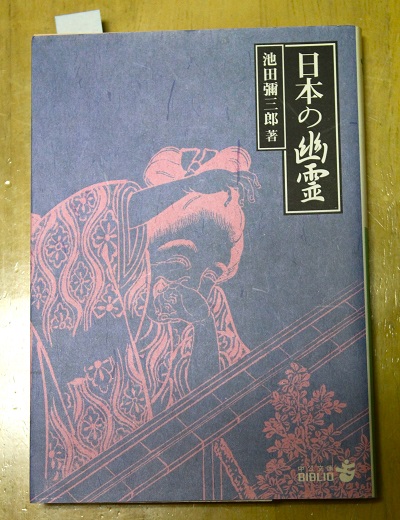
「座敷童子」を単なる「妖怪」とする見解から、さらにもう少し突っ込んだ考察も民俗学初期の段階に盛んに行われている。柳田國男も「座敷童子」を「妖怪」とカテゴライズする一方で、その起源は「護法童子」「心得童子」などの系列にあるのではないかと指摘している。つまりは「式神(職神)」だ。一般には陰陽師が使役する「鬼神」とされ、西洋のオカルティズム世界でいえば、魔女が魔物、精霊、動物(主に黒猫)を材料につくる「使い魔」(使霊・使役霊)のようなもの。要するに「術者」の命を受けて奔走する実行部隊、忠実な「使いっ走り」である(以下に書く通り、まったく「忠実」でない場合も多いらしいが)。
柳田が「座敷童子」のルーツとして指摘する「護法童子」とは、中世の修験僧、なかでも相応の高僧がつくる(あるいは呼び出す)使役霊だという。民俗学者・小松和彦の『憑霊信仰論』(1982年)によれば、「髪赤く、俊足、怪力。よく仕事をする童子ではあるが、神というより神の眷属である鬼に近く、それゆえ節度なく、ときに残酷な行為にも及ぶ。高僧のみがこれを管理・コントロールすることができ、扱い方をひとつ誤れば他者を死へも導く危険な存在」とのこと。確かにこの善悪二面性という属性(というより善悪の判断能力の欠如)からは「座敷童子」の「暗い部分」、「かわいくない側」の顔が透けて見えるようだ。

さらに柳田が指摘する「心得童子」はもっと不吉で危うい。これも上記『憑霊信仰論』によれば、「高僧が天から『護法童子』を呼ぶのと同様、俗世間の巫女(つまり神仏に繋がらない民間のフリーオカルティスト、野良術者といった意味合い)も秘法をもって童子をつくる。これが『心得童子』。巫女が旅行をする際は、童子の体から魂だけを引きはがし、これを同行させる。この見えない魂は自在に使役することができ、さまざまなものに宿らせたり、ときに他人の中までも往来させる(憑依させる)ことができる。ただひとつの不便は、すでに不用となっても自分の体を具えぬ霊魂であれば、他には行所がない。それ故にいつまでも術者の家に泊り住んでいる」という。
つまり神仏に担保されていない(モラルの束縛を受けない)術者が独自に製造するインディペンデントな「使い魔」であり、術者が遠方に赴く際はその体から魂のみを取りだし、「不可視の携帯用使い魔」にして持ち運ぶことができるというわけだ。スパイ、工作員、略奪者、あるいは暗殺者にとって、これほど便利な「道具」はないだろう。物騒なことこの上なし、である。「道具」としての唯一の欠点は、一度取り出された霊魂を「帰す・戻す」というシステムは存在せず、いらなくなっても捨てる方法はなく、捨て場所もない。もちろん霊魂なので死とは無縁で永久に存在し続ける。プルトニウムのようにやっかいなのである。
この「心得童子」の霊魂の「帰れない」という属性、いつまでも術者の家に留まるという要素が、旧家に「憑く」とされる「座敷童子」と関連しているのではないか、との主張も多い。僧侶で民俗学者の筑土鈴寛も同様の指摘をしている。
「ザシキワラシという童子もまたこれ(護法童子や心得童子)の分身である。人の運、不運はいかにこうした童子を扱うかで別れたのである。童子の追放(帰す)ということは、高僧によってこそ可能であったが、凡人の生活では童子自ら気に入らなければ去ってしまうので(つまり、相応の修行を積まぬ者には使役はできるが退場はさせられない)、家の衰退は同時に成り行きのままになってしまうのであった。役行者(ハイレベルの術者)の如く前鬼後鬼(修験道開祖の役小角に従う赤鬼青鬼の夫婦)を駆使することができぬ以上、これを敬わねばならなかった神であり、かつ使い神であるという二重の印象が、これら世間の童子にはあった」
さて「河童」「式神」の話からようやく「座敷童子」の本質部分にまでたどり着いたが、紙幅が尽きてしまった。当初は前後編でまとめるつもりが、相変わらずの構成力不足で、やむを得ず三部作とさせていただく。あと一回だけお付き合い願いたい。

上記の筑土鈴寛の言葉はすでに「童子」(「座敷童子」に限らず、術者に呼ばれ、そして帰れなくなった「童子」の霊魂全般)が家の衰退(及び繁栄)に関わることが前提となっている。
次回はこの部分、「座敷童子」の属性として最も大きな「富(と退転)をもたらす」というポイントを掘ってみたい。これは我々がなにげなく口にする「ついてる」「ついてない」という「つき」(luck)の話であり、さらには「憑き」についての話であり、そうなれば当然、悍ましいケダモノ(動物霊)の話となるのだが、この獣道から少しそれたところに、ケダモノよりもさらに悍ましく絶望的な民衆=ヒトによって構成される凄惨な光景が広がっている。僕のようなド素人が付け焼刃的に文献を漁った限りでは、「そこ」こそが「座敷童子」の「故郷」に思えて仕方がないのだが……。
初見健一
昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。
関連記事
業績好調の会社には「オフィスわらし」が潜んでいる?/朝里樹・都市伝説タイムトリップ
都市伝説には元ネタがあった。今回は、あなたのそばにもきっといる、おかっぱ頭のあの子ども。
記事を読む
座敷童子の宿「菅原別館」で金縛りに遭うも、目覚めはスッキリ!/辛酸なめ子の魂活巡業
今回は、「座敷わらしの宿」として有名な旅館、菅原別館(岩手県盛岡市)を辛酸なめ子さんが来訪。宿泊中に体験した不思議な出来事をレポートします。
記事を読む
恐怖と戦慄の「東京タワー蝋人形館」のトラウマ! 消えた拷問人形たちは今いずこ……/初見健一の昭和こどもオカルト回顧録
かつての東京タワーで展望台よりも人気を博した「蝋人形館」をあなたはご存じだろうか。猥雑で迷宮的だった“魔塔”東京タワーの実態を紹介!
記事を読む
地球外知的植物生命体を目撃した話など/南山宏のちょっと不思議な話
「ムー」誌上で最長の連載「ちょっと不思議な話」をウェブでもご紹介。今回は2025年3月号、第491回目の内容です。
記事を読む
おすすめ記事

