ヴァイキングの守護神が豊かさをもたらす!/ヘイズ中村の「オーディンの開運魔術」第1回
かつて北欧の海を船で駆けめぐり、さまざまな富を得たヴァイキングたち。じつは、彼らは素朴で強力な魔術の使い手でもあり、その力の源泉となるのが北欧神話の最高神オーディンでした。日本を代表する魔術師にして魔
記事を読む

四国・高知の山奥に残る幻の民間陰陽道「いざなぎ流」の呪術世界を案内する。
四国・高知の山奥に、すでに絶えてしまったと思われていた陰陽道の世界が脈々と息づき、その術法を伝える者たちが現存していた──。それが「いざなぎ流」であり、太夫(たゆう)と呼ばれる宗教者である。
長年にわたり現地でのフィールドワークを重ね、その奥義を知る神話・伝承学者の斎藤英喜氏(佛教大学教授)にロングインタビューを行い、多様な神々とその伝承、驚きの祭祀、そして禁断の呪法にいたる、いざなぎ流呪術世界の奥の奥へとご案内いただいた。
目次
香美(かみ)市物部(ものべ)は、高知空港近くで河口に至る物もの部川(べがわ)沿いの国道195号を、上流目指して北東に進んだ先にある。
かつての物部村の中心地・大栃(おおとち)は、上韮生川(かみにろうがわ)との合流地点にあり、そこからさらに物部川をさかのぼる流域が「いざなぎ流」の信仰圏といわれる。
深いV字谷を形成する地形、そこにへばりつくように点在する家々──。いわゆる限界集落である物部川上流域の最奥地区に、最後の伝説的太夫・中尾計佐清(なかおけさきよ)太夫の住まいがあった。

斎藤英喜氏は、1987年以来、十数回にわたり、今は鬼籍に入られた中尾太夫のもとを訪ね、いざなぎ流祭祀の現場──地域の氏神や地神(じじん)、旧家の屋敷神の祭りごとや神楽、山や川の鎮め祈禱、霊的な病に対する病人祈禱など──に立ち会い、膨大な時間を費やして聞き取り調査と手紙のやりとりを行った。そして、研究者としては異例な形でその奥義を授かったただひとりの学者となった。

「僕の専門は古代文学なのですが、『古事記』や『日本書紀』などの文字に書かれた神話世界がある一方で、文字以前の神話があります。当時、それが沖縄に行けばあるといわれていたのだけど、沖縄の口承文化は女性が中心で、男性の研究者はなかなか入り込めなかった。
ところが、高知の『いざなぎ流』では、古代のものではないものの、神の由来やお祭りの起源が語られる豊富な『祭文』が残されている。太夫という専門の宗教者もいて、実際にお祭りの現場で誦まれているという。これは見てみたいと」(斎藤氏)
折りよく祭りが行われるタイミングに恵まれ、斎藤氏ははじめて現地に赴いた。そこで紹介された中尾太夫は、「自由に見てもいいし、写真を撮ってもいい。録音しても構わない」と気さくに応じてくれたという。しかし──、「あとで気づくのですが、それは『見ても何もわからないよ』ということだったんですね」
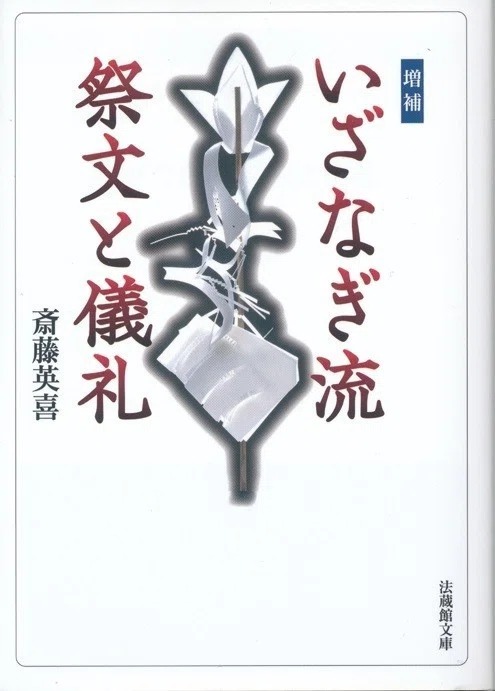
「いざなぎ流」とは、端的にいえば、高知県香美市物部(旧物部村)に伝わる民間信仰である。
それがなぜ注目されたのか。理由のひとつは、かつて日本の各地で展開されていた信仰の多くがすでに失われ、文書の中にのみとどまっているなか、「いざなぎ流」は、古くからの祭祀・祈禱が独立した信仰の体系としてそっくり保持されていたからである。
しかしそれだけではなかった。
「最初に研究者が入ったときは、いざなぎ流は修験道の一派だと思われていたようです。ところが見ていくと、どうも違うらしい。すると今度は、式王子(しきおうじ)という存在がクローズアップされて、だったらこれは陰陽道なんじゃないか、となったのです」(斎藤氏)
式王子とは何かについては後述するが、「式」とは、「用いる、使役する」の意で、陰陽師はさまざまな精霊を「式しき神がみ」として用い、使役して、病気を治したり、呪法を行ったりするといわれてきた。つまり、式王子は式神に通じるとして、その法を駆使するいざなぎ流太夫は、現代に生きる陰陽師として注目を集めたのである。
こうして、1990年代後半にはじまる陰陽師ブームと相まって、いざなぎ流にはアカデミズムの枠を越えた関心と好奇の目が注がれるようになった。
しかし、その全体像にアプローチすることは容易なことではなかった。
「いざなぎ流は、ひとつのことが解きほぐせたかと思うと、即座に新しい疑問点にぶつかるという、まさに『謎』の永久運動のような世界」なのだと斎藤氏はいう。


少し歴史をおさらいしてみよう。
安倍晴明で知られる陰陽師は、もとは奈良の平城京以前にさかのぼる、占術を職掌とする官職に由来する。古代律令制における中務省(なかつかさしょう)に属する部署のひとつ「陰陽寮(おんようりょう)」に所属し、天文を観測し、地相を読み、吉日凶日を判じることを職務とした人たちである。
そして平安時代に入ると、旧来の天文と陰陽の知識に加え、道教由来の方術・呪術や祓(はら)えの呪法などを駆使する霊的コンサルタントとして天皇や摂関家と結びつき、晴明に代表される伝説的陰陽師も登場した。
鎌倉時代以降、武家が台頭すると、陰陽師は幕府の将軍お抱えの存在となる。とくに足利時代には、安倍晴明の末裔(のちの土御門家(つちみかどけ))の地位が引き上げられ、天文・暦の職掌を独占するようになっていく。
もとよりその知識と術法は、天皇・貴族や将軍などの権力者によって独占され、管理される性格のものだったが、実情は必ずしもそうではなかった。
平安時代にはすでに陰陽寮に属さない民間の陰陽師がいて、法師(ほうし)陰陽師などと呼ばれていた。そのシンボルが、晴明伝説に登場するライバル(たいてい悪役として扱われる) 蘆屋道満(あしやどうまん)で、生国の播磨(兵庫県)には、法師陰陽師らの拠点もあったといわれる。彼らはおもに治病のための呪術祈禱や祓えに携わったと考えられているが、その歴史的な実態はよくわかっていない。

こうして、中世(平安末から室町時代)の謎多き500年を経て、在野の陰陽師は、諸国を行脚し、霊媒や口寄せ(降霊術)をもとに祈禱や占いを行う一方、地域の祭祀や神楽の担い手として各地に根づいていた。他方、江戸時代に幕府のお墨つきを得た土御門家は陰陽道宗家として全国の陰陽師の支配・任免権を独占していた。
いざなぎ流の場合はどうだったか。
太夫らは、「式法」を駆使するなど、陰陽師由来の業を濃厚に受け継いでいるが、斎藤氏によれば、いざなぎ流の太夫らはみずからを「巫博士(かんなぎはかしょ)」と呼んでいたらしい。
博士とは、江戸時代の地誌にも記された槇山村(まきやまむら)(旧物部村)の宗教者集団で、彼らは土御門家から禁じられていた弓ゆみ祈祷(ぎとう)を行い、口寄せや憑き物もの落としを担っていたという。
それだけではない。彼らが伝えるテキスト(祭文)や祭りごとのディテールには、修験道や密教、吉田神道などの流儀も流れ込んでいるともいわれる。
いざなぎ流の来歴を正確にたどることはもはや無理であろう。つまるところ、それは近代日本が切り捨ててきた在野の信仰(とりわけ呪術的な祈禱)を貪欲に呑み込みながら独自の歩みをつづけた、膨大な知識の体系というほかないのだ。だからこそ、いざなぎ流は「『謎』の永久運動」なのである。

研究者としては、複数の取材源をもとに客観的なデータを抽出するのが常道のやり方だろう。しかし、斎藤氏はそうしなかった。
「いざなぎ流の深奥へと分け入ること。必要なのは、『太夫』の側に限りなく近付き、彼らの側からのみ見えてくる世界を記述していくことにある」(『いざなぎ流 祭文と儀礼』より、以下*印も)と考えたからだ。
斎藤氏の〝いざなぎ流体験〟の最初は、旧物部村別役(べっちゃく)の小松神社で行われた4日間にわたる臨時祭だった。そのメインは、拝殿内で営まれた氏神への本神楽だったのだが、それと並行して、社殿近くの林の中で、もうひとつ別の祈禱が繰り広げられていた。
「木の枝で二段の棚が組み立てられ、棚の後ろには山の神、大荒神(だいこうじん)、新木、古木、水神といった神々を祭る御幣(ごへい)がくくりつけられる。中の棚には十二膳の餅、菓子、酒、蜜柑、酒、米粒などが供えられた。さらに棚の下には道六神(どうろくじん)、四足、すそ、山みさき、川みさき、六道神(ろくどうしん)などの小さな御幣が地面に直接差し込まれ、その前にも供えがされる。この臨時に作られた、地面を含めて三階の棚こそ、山の神の祭壇である」(*)
まず、山の神に対して、これだけの神霊が祀られることに驚く。御幣は神々の依り代にして、そのお姿をあらわすもので、その多様さはいざなぎ流の特徴でもある。それにしても、棚の下に祀られているモノたちは何なのか。
斎藤氏の解説によればこうだ。
「道六神」(道の神、道祖神、道路で事故があると必ず祭られた)
「四足」(山の動物たちの魂こん魄ぱく)
「すそ」(人の憎しみ、妬みのあらわれ。その魂魄)
「山みさき・川みさき」(大川、小川が合流しているところに棲息する山川の魔物)
「六道神」(山や川での不慮の事故で死んだ者の魂魄、無縁仏)
動物霊や魔物たち、死霊、生き霊まで祀らなければならないのは、それらが山の神の眷属(けんぞく)であり、災いや病などをもたらす原因となるものだからだ。
「だから、まずは場を清めなければならない。人間の行いによって生じた見えない世界の混乱状態をいったん整理して、山のものは山へ返し、川のものは川に返し、『すそ』があったら鎮める」
──それがいざなぎ流の基本だと斎藤氏はいう。この祭儀は「取り分け」と呼ばれ、いざなぎ流のあらゆる祭儀の最初に行われる儀礼である。


「気付かされたのは、いざなぎ流の祭祀・神楽が、太夫たちの口から発せられる多種多様なコトバによって成り立っている事実である」(*)
いざなぎ流の最大の特徴は、祭祀儀礼のさまざまな場面で誦まれる祭文にある。端的には神を祀(祭)るときに誦む文のことだが、主要な神々ごとに祭文があり、神々の由来や、どのように祀られたのかなどの由緒が説かれている。のみならず、儀礼においてはその目的を神々にいい聞かせ、神楽においては神々を喜ばせ、祈禱の場面では神霊と渡り合い、さらに意志のままに操作し、ときに調伏くする呪法として、祭文は機能するのだという。
「だから祭文はぜったい現代語に訳してはならない。現代語にすると神々とコトバが通じなくなってしまう」
「祭文をきちんと誦むことができれば、どんな病人の祈禱をしても治すことができる」
「祭りや祈祷のなかで不明なことがあれば、祭文に書いてあることを確かめてみれば、たいていのことはここに書いてある」(*)
それが中尾太夫の教えだったという。
では、「山の神の祭文」を例に、その世界観をのぞいてみよう。
その冒頭はこうだ。
「山の神の父の御名は、ら天の権ぜの王と申す、母の御名は、まき(槇)大権(黄金)如来の王と申す、之天地久(てんじく)(天竺)もくろが御山へ天や上らせ給ふてござれば、三人のごうきんだち(御公達)がいでき初まり申してござれば、太郎のごうきんだちは、東々(とうとう)方がた花ぞが山をりよ(領)じ持せ給ふて御わします……」(*)
カッコ内は斎藤氏が補ったもの。当て字や意味不明なワードも混じっているが、要するに、山の神は「ら天の権ぜの王」と「槇黄金如来の王」との間に生まれた3人兄弟で、その長男である太郎は天竺の山で、「東々方花ぞが山」を領地として与えられた(が、それを不服として、日本を領地とすべく日本に天降りし、山の神になる)という内容だ。


ちなみに、「天竺」とはインドの古名で、「如来」は仏教のホトケの名称。日本神話とも仏教説話とも異なる、中世的といわれる異様な世界観がここに開陳されている。
そもそも、いざなぎ流の「いざなぎ」は、日本神話のイザナギ命とはまったく別の存在である。「天竺いざなぎ様」といい、祭文に天竺に住まう不思議な術の達人として語られており、いわばいざなぎ流の始祖に位置づけられる。

ともあれ、右につづく「山の神の祭文」のあらすじを抄訳してみたい。
──山の神は虫や鳥獣を自分の眷属とし、その羽休め木を設定した。ところが日本の氏子らはそれとは知らず木を伐採し、病を得た。氏子らはその原因を知るために「天竺星のじょもんみこ殿」なる者を雇い、占ったところ、山の神の木を伐ったお叱りだと判明した。そこで氏子らは「じょもんみこ殿」に山の木々の伐採を許可してもらう「受け約束」の交渉を依頼。山の神は「月々日々」「終夜の」神楽を要求したが、それでは氏子らの生活もままならないとして、「じょもんみこ殿」は交渉を進め、特定の日の神楽奉納を約束して伐採を許してもらった……。
ざっくりといえば、もとは山の神のものだった樹木が人々に譲渡された起源を物語るストーリーである。
注目すべきは、「星のじょもんみこ殿」なる人物である。「殿」は占いをし、山の神と交渉をし、神と人とを仲介している。斎藤氏によれば、この「殿」こそ、異国(天竺)から来訪し、かつ山の神の祭祀を行う太夫自身の始祖・原像であるという。
つまり、いざなぎ流太夫は、「星のじょもんみこ殿」に成り代わって祭儀を執行するわけである。そして太夫は、祭りの目的に応じて、祭文には書かれていない効果的な文言(これを「りかん」という)を発し、神々を統御する。
たとえば、「山の神の祭文」を取り分け儀礼で誦む場合、こんな「りかん」が語られる。
「御部類、御眷属、山の神、川の神、六面王(むつらおう)に八面王(やつらおう)、夜行神、山スズレ、川スズレ、しそく狐、狸、サンカの四足二足、魔群化性(けしょう)の者が、御縁を掛けてござろう共ども、御縁を切らって、御縁を放はないて、黄金花べら花ミテグラへ、諸願成就、集まり影よう向ごう成り給たまへ」
これは、山の神に「六面王に八面王、夜行神……」といった魔物を引き連れ、取り憑いた縁を切って祭壇のミテグラ(神霊の依り代)に集まるように促すメッセージなのだ。
この「りかん」は、基本、太夫がその場に即して編み出す言葉とされている。「りかん」をきちんといえるかどうかが、その太夫の宗教者としての能力をあらわしているという。

後篇へ続く
本田不二雄
ノンフィクションライター、神仏探偵あるいは神木探偵の異名でも知られる。神社や仏像など、日本の神仏世界の魅力を伝える書籍・雑誌の編集制作に携わる。
関連記事
ヴァイキングの守護神が豊かさをもたらす!/ヘイズ中村の「オーディンの開運魔術」第1回
かつて北欧の海を船で駆けめぐり、さまざまな富を得たヴァイキングたち。じつは、彼らは素朴で強力な魔術の使い手でもあり、その力の源泉となるのが北欧神話の最高神オーディンでした。日本を代表する魔術師にして魔
記事を読む
預言を遺した聖母が出現した現場「ファティマ」の歩き方/ムー的地球の歩き方
ムーと「地球の歩き方」のコラボ『地球の歩き方ムー 異世界の歩き方』から、後世に残したいムー的遺産を紹介!
記事を読む
巨大龍、魚の鳥居、可愛すぎる本尊…すべてがカオスな全国珍寺紀行!/小嶋独観
珍スポ巡って25年、すべてを知る男による全国屈指の“珍寺”紹介!
記事を読む
戦火の拡大と核兵器に注意!?/Love Me Do の「ミラクル大予言」2024年5月
アイドルの電撃婚や活動休止から大統領選の行方まで、さまざまな大事件を予言し、的中させてきたLove Me Doさんが、2024年5月9日から6月6日までの日本と世界を占います!
記事を読む
おすすめ記事

