赤マントに青ゲット……怪事・怪人はなぜ色をまとうのか/学校の怪談
放課後の静まり返った校舎、薄暗い廊下、そしてだれもいないはずのトイレで子供たちの間にひっそりと語り継がれる恐怖の物語をご存じだろうか。 学校のどこかに潜んでいるかもしれない、7つの物語にぜひ耳を傾けて
記事を読む
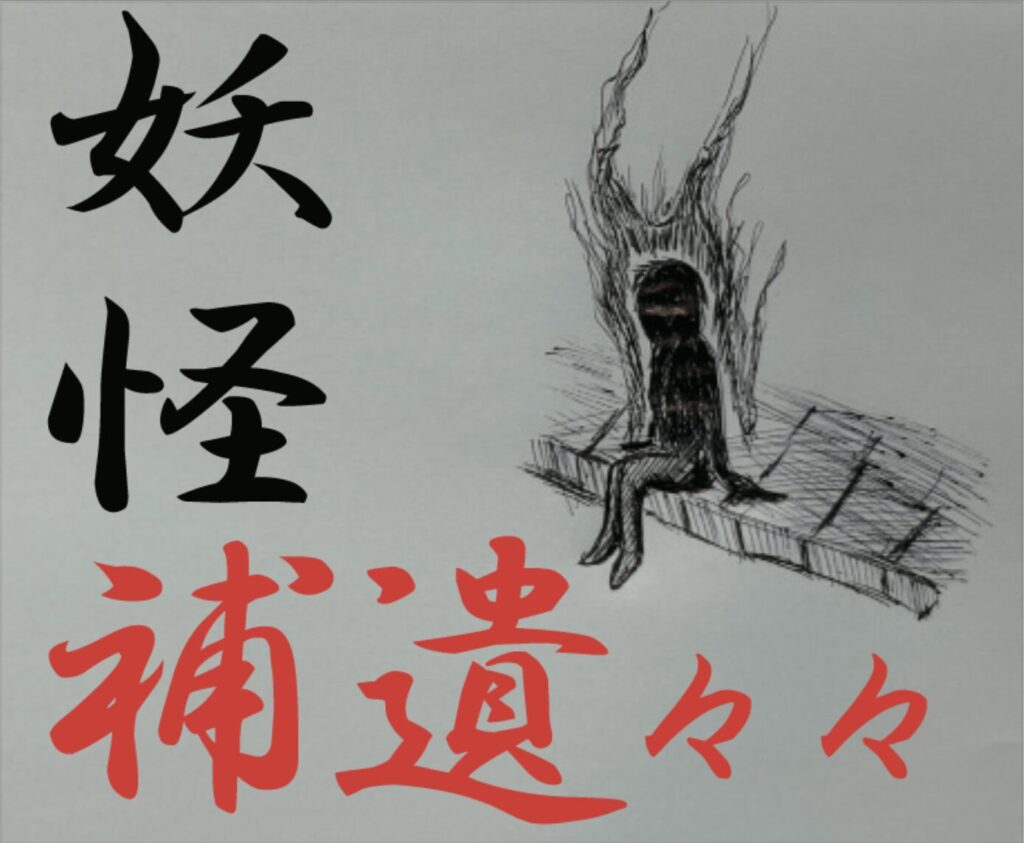
ミステリー記念日に合わせて、行動も存在もミステリーな各地に伝わる怪異譚を補遺々々しました。ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から“忘れ去られた妖怪”を発掘する、それが「妖怪補遺々々」だ!
10月7日はミステリー記念日です。
1849年10月7日に小説家エドガー・アラン・ポーが亡くなったことから、彼の功績を讃えて作られた記念日のようです。
そこで今回は、ミステリーなモノたちをご紹介したいと思います。〈ミステリー〉を辞書で引きますと、「神秘」「不思議」「霊妙」と出てきます。妖怪なんですから、不思議で神秘的なのは当たり前……なのかもしれませんが、中でも行動や存在がミステリーな、ちょっと変な怪しいものを集めてみました。
岐阜県金山町(現・下呂市)の田淵に橋がありました。
ある時から、この橋の上に毎日、ひとりの男が座るようになりました。
なぜ座っているのかはだれもわかりません。ただ、座ってじっとしているのです。
そのまままったく動かないのかと思うと、人が橋を通りかかると、なぜか男は川の中へ飛び込むのです。そして、人が通り過ぎると、男はまた橋の上に座ってじっとしています。
村人は男のこの行動に呆れていました。意味がわかりませんし、なんだか気味が悪いです。村人たちは、この男を金山から追い出してしまいました。
すると今度は、上沓部に架かるチンドリ橋に男は現れました。
何をするのかというと、また同じです。
毎日、橋の上にただ座っているのです。
ここの土地の人たちも男の無意味で気味の悪い行動に呆れ、追い出してしまいました。
そんなことがあった数年後。
群上(ぐんじょう)の地に【鬼】が現れました。
人々は恐れおののきましたが、ある武士がこれを退治してくれました。
その鬼は、橋の上に座っていた男に違いなかったそうです。
沖縄県、屋我地島(やがじしま)の我部村(がぶむら)に暮らす、15歳の少年の身に起きた出来事です。
ある日の夜、少年は自宅を出てから、そのまま行方不明になってしまいました。
村では大騒ぎになり、海辺や森を捜索しましたが、どこにも彼の姿はありません。
見つからないまま、1週間が経ったころでした。
諦めず、今度は墓場を捜索しようということになり、みんなで少年の家の墓を開けてみたのです。すると、なんということでしょう。
墓の中に、少年が座っているではありませんか。
どうも何かに憑かれているようで正気ではなく、振る舞いなども異常であったということです。
このように、村人が夜間、何者かに墓場に連れていかれるような事件が、昭和の初期ごろまで、よくあったそうなのです。
鹿児島県出水郡に、一郎、次郎、太郎という3人兄弟がありました。
ある日、紫尾山(しびざん)に山登りに行った人が帰ってこないので、村人たちで話し合い、3兄弟が捜しに行くことになりました。
一番先に長男が向かいました。
えっちら、おっちら、山に登って、日が暮れだしたころ。
お宮を見つけたので、そこに泊まっていくことにしました。
しばらくして、「ごめんなさい」と、盲目の坊主がお宮に入ってきました。
坊主は出し抜けに、「じゃんけんぽんをしよう」と長男にいうのです。
じゃんけんで負けたほうの頭を打つ、そんな遊戯をしようじゃないかというのです。
大変つまらなそうですが、よほど退屈だったのでしょう、長男は承諾しました。
「じゃん、けん、ぽん」
長男が負けてしまいましたので、坊主が長男の頭を打ちました。
すると長男は、ころりと死んでしまいました……。
いくら待っても長男が戻ってこないので、次は次男が向かいました。
しかし、次男も同じように殺されてしまいます。
ふたりとも帰ってこないので、今度は三男が向かいます。山の中にお宮を見つけたので、もう遅いからと泊まっていきますと、しばらくして「ごめんなさい」と、盲目の坊主が訪ねてきました。坊主は、じゃんけんぽんをしよう、といいます。負けたら頭を打たれる遊びをしようというのです。三男は受けて立ちました。
「じゃん、けん、ぽん」
あっ。三男も負けてしまいました……。
すかさず坊主は三男の頭を打ちました。
チリン、ガラン。
長男も次男も、この一発で死んでしまったのに、三男は無事でした。実は、彼はじゃんけんをする直前、近くにあった釜を頭にかぶっていたのです。釜はパッカリと割れてしまいましたが、三男の頭は無傷です。
次は三男が坊主の頭を打つ番です。近くにあった鉈を掴んだ三男は、それで坊主の頭を思い切り殴りました。坊主が慌てて逃げだしたので、三男はすぐに追いかけます。
やがて、三男は洞窟に着きました。中に入っていくと、大きな蜘蛛の巣の真ん中に、先ほどの坊主がいます。近くには、兄が持っていった刀が落ちていました。
この坊主は、蜘蛛の化け物だったのです。
三男は蜘蛛の化け物を退治し、無事に山を下りて帰ったのでした。
大酒飲みで暴れん坊の【武兵衛】という男がいました。
どんな寒い日でも裸でいるので、村人たちは彼を【裸武兵衛】と呼びました。
大酒飲みで暴れん坊で裸ん坊の彼ですが、性根は善人のものだったそうです。
ある夜、お宮の拝殿の床下で寝ていると、そこに白髪の老人が現れました。
老人は、【疫病の神】だと名乗りました。
老人姿の疫病の化身は、武兵衛と兄弟分になりたいと言うのです。
「お前が来れば、俺は逃げる。お前は、この疫病神を追い払う役目をするのだ」
それだけいうと、老人は消えてしまいました。
その後、武兵衛の仕事仲間のひとりが熱病にかかりました。
どんどん熱は上がっていき、とても危険な状態です。
しかし、武兵衛が患者に触れると、どういうわけか、あっという間に熱が下がります。
そうなのです。
常に裸のこの男は、不思議な力を持っていたのです。
その後、笹洞村で傷寒(しょうかん)という疫病が発生しました。
村人たちは白山権現にお百度参りで願掛けをしましたが、悪疫の触手はどんどん伸びて広がっていき、被害は拡大していくばかりです。
そんな絶望的な状況の時——。
ふんどし一丁の裸の男が、村を訪れたのです。
武兵衛です。
彼はさっそく、医者に見放された熱病患者のもとに行き、その肌に触れました。
患者の熱はたちまち下がっていきました。この力で疫病の神を村から追い払った武兵衛は、苦しんでいた村人をみんな元気にしていきました。
村人たちは、いつも裸の武兵衛の神通力を「疫病追い払いの神」として祀りました。
『金山町誌』によると、岐阜県下呂市金山町菅田笹洞(すがたささほら)にある神社の境内に、【はだか武兵衛】と刻まれた石があるといいます。今でも、この石碑に向かって願うと、どんな病でも全快するそうです。
ある炭焼きの男が、炭焼き小屋で白炭をいじっている時でした。
突然、隠居がやって来て座り込んだかと思うと、自分の金玉を広げ始めました。
それがいくらでも広がるので、これは包み込まれたら大変だと怖くなった炭焼きの男は、石を焼いたものを、隠居の広げたモノのなかに放り込みました。
隠居は大慌てで逃げ出しました。
その後を追っていくと、谷川の淵で【ひひざる】が死んでいました。
香川県綾歌郡綾上町に伝わるお話です。

【参考資料】
『綾上町民俗誌』〈1982年〉
『金山町誌』〈1975年〉
『川内地方を中心とせる郷土史と伝説』〈1936年〉
黒史郎
作家、怪異蒐集家。1974年、神奈川県生まれ。2007年「夜は一緒に散歩 しよ」で第1回「幽」怪談文学賞長編部門大賞を受賞してデビュー。実話怪談、怪奇文学などの著書多数。
関連記事
赤マントに青ゲット……怪事・怪人はなぜ色をまとうのか/学校の怪談
放課後の静まり返った校舎、薄暗い廊下、そしてだれもいないはずのトイレで子供たちの間にひっそりと語り継がれる恐怖の物語をご存じだろうか。 学校のどこかに潜んでいるかもしれない、7つの物語にぜひ耳を傾けて
記事を読む
眩しく光る山中の怪人「赤頭」は神か妖怪か、宇宙人か? 高知県の怪異伝承を考察
高知県の山中に出現した「赤い顔」の怪異。その正体は妖怪か怪物か、または宇宙からの……?
記事を読む
香川県の飯野山にいた! 足跡を残した巨大な愛され妖怪「オジョモ」/妖怪補遺々々
香川県に伝わる巨人妖怪オジョモ。ちょっと聞き慣れないかもしれませんが、地元では意外な愛されキャラ。しかも各地に異なる伝承も。そんなオジョモの怪異を補遺々々しました。ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・
記事を読む
都市伝説「消えるヒッチハイカー」を生んだ事故現場で発生する「白い女」との遭遇/アーカンソー州ミステリー案内
超常現象の宝庫アメリカから、各州のミステリーを紹介。案内人は都市伝説研究家の宇佐和通! 目指せ全米制覇!
記事を読む
おすすめ記事

