神の機械「ニュー・モチーブ・パワー」が無限のエネルギーをもたらす!? 19世紀心霊テクノロジーの到達点
人間の女性と接続して無限のエネルギーを得る!? 神の御業に挑んだ、とある機械について。
記事を読む

創造論の最前線では”科学”と”神”を共存させる試行錯誤が育まれている。創造論を追うシリーズ第3回!
目次
創造論の枠組みの構造は複雑で、一種類の色合いでは決して説明できないことを前回までに示した。話はここからさらなる方向に伸びていく。今回は、有神的進化論という考え方について詳しく見ていくことにする。
基本の部分だけを見るなら、有神進化論は前回触れたOEC(Old Earth creationism=古い地球説)の一形態としてとらえるのが正しい。ただ、その定義はさらに複雑化する。
——進化は起きたが、それは神が計画し、導いた過程である。
——そして神が森羅万象を計画し、創出した過程においては、他の影響が作用できる余地は一切なかった。
このような有神的進化論では、進化論がヒステリックに否定されることはない。むしろ進んで認め、盛り込み、互換性がある要素としてとらえているのが事実だ。
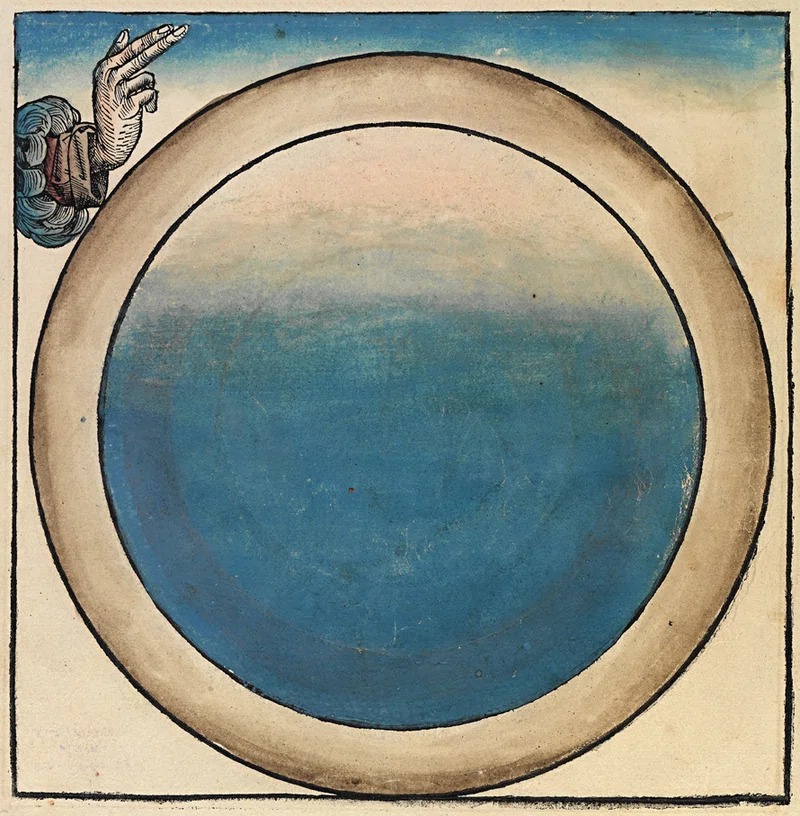
有神進化論において進化の出発点にあるのは、神によって創り出された”地球生命の共通の祖先”として存在していた生命体だ。仮に“オリジン”と呼ぶことにしよう。人類を含め、地球のすべての動物はこのオリジンから進化を遂げた。神はその後、大きな創造の構図の一部として、間接的に関わりながら地球生物の進化の過程を見守っていった。そして神は、一番大きな関与をする。最初の人間に魂を与えたのだ。
有神的進化論者たちのコンセンサスは、強調されるべきは“創世記”の全体的なメッセージであり、一つひとつの言葉を意味通りに受け取るべきではないという考え方だ。
まず、「創世記」1章および2章に記されている人々と、類人猿の祖先は同じであると考える。その理由は、すべての生物がオリジンから進化したという大前提があるからにほかならない。この時点で、ほかの創造論とは全く異なる性質の思想ということになる。そしてまさにこの部分が創造論の各セクター、特にYEC(Young Earth creationism=若い地球説)の標的となっている。有神的進化論の論拠は物証に基づく考察ではなく、感情論にすぎないというのだ。
聖書には、森羅万象に関する知識が記されて”いない”。これを認める人々は、進化論がキリスト教の教義に大きな問題をもたらすものではないと考えているようだ。神が語るのは「自分が森羅万象を創り出した」ということだけであり、方法については何も触れていないし、その必要もないからだ。聖書、特に『創世記』の目的は森羅万象のメカニズムについて語ることではなく、神がメカニズムを創り出した事実をあまねく知らしめることだ。
これに近い考え方の人は科学者の中にもいて、“キリスト教的進化論者”と呼ばれることもある。ただ混乱が生まれないよう、この原稿では有神的進化論という言葉だけを使って話を進めていくことにする。
有神的進化論の基本的な部分をさらに確かめていこう。
進化は事実として起き、その過程には創造主の知性が絶対的な形で関わっていた。
多くの有神進化論者が進化の過程において創造主の直接的な関与があったと信じているが、関与の度合いに限って言うなら、かなり幅があるように感じられる。有神進化論とは、基本的に進化論と創造論の間に位置するものであり、進化論寄りの思想も創造論寄りの思想もある。黒から白へと至るグラデーションのように、無数に存在すると言っていいだろう。
たとえばこういう考え方もある。
神は森羅万象を形作る物質を創り出し、それが単細胞生物となり、すべての生命体がそこから進化していく過程を導き、見守った。その過程を経て存在しているのがわれわれ人間だ。進化の過程は、神が森羅万象の姿を今のようにするために方向づけていく方法論だった。
有神的進化論では、人類が原始的な形の生命体から長い時間をかけて進化したと考える。これを踏まえた上で、以下を読み進めていただきたい。
アダムが生まれる前の時代の地球では、“人間以前”あるいは“人間直前”と形容すべき生物の集団が暮らしていた。こうした集団の中からアダムが生まれた時、神は自ら彼を選び出し、息吹を与え、これによって本当の意味での人類の父祖が誕生した。こうしてアダムは、人類の最初の一人となった。
いわゆる化石人類や他の種類の類人猿と人類の関係については、何の問題もない。なぜなら、今の人類は神の息吹を受けて初めて人間となったアダムから続く系譜なので、それ以前の人間に似た存在とは一線を画すからだ。
神はもちろん、他の類人猿に対しても同じように、彼らなりの進化を遂げていく道筋をつけた。類人猿は類人猿で、そして結果的に現生人類になる生き物のグループもそれぞれの系統で進化を続けた。こう考えれば、すべての生物が一種類の単細胞生命体を源にしているという大原則が破綻することもない。「森羅万象の源、そしてすべての命は、神の命令により創り出された」という教義が基盤となるからだ。
こういう言い方もできるかもしれない。
アダムに息吹=魂を与えたことこそが、神と人間との間に交わされた最初の契約であり、それについて語る『創世記』が含まれた旧約聖書は、まさに契約を示す記録にほかならない。

『創世記』の最初の3章は、史実と寓話的な物語を組み合わせた構成になっている。
前述の通り、有神進化論においては、他の種類の創造論のように、創造物語に記された一つひとつの言葉を文字通り受け取ることはしない。すべての生命は、それぞれの系統に沿って進化し続けた。しかし、かつての地球に生きていた人間に近い生き物は、神と思いをやり取りする能力に恵まれていなかった。そこまで成熟していなかったという言い方もできるかもしれない。そこで神は一人の男子を選び出し、息吹を与えた。さらに彼にふさわしい女性を探し、やはり息吹を与えて魂を宿し、人類の源とした。
ちなみに、神の言葉に背いて禁断の果実を口にしたアダムとイブが楽園から追放される逸話は、人間の精神性の死を象徴するものとされている。楽園追放という罰は代々伝えられ、キリストの磔刑という具体的な形でも実現することになった。
もう一度記しておきたい。有神的進化論では、進化論を完全かつ絶対的に否定することはない。むしろ、進化論を神が用いた仕組みとしてとらえ、それゆえ進化論という仕組みを抜きに創造論を語ろうとする姿勢を問題視する。
聖書の記述に進化論を盛り込むスペースを積極的に作ったことが有神的進化論の第一の特徴であり、同時に最大の問題点でもある。
有神的進化論を改めて筆者なりに定義するなら、次のような言い方になる。
神は、進化という方法論を用いて、人間を含むすべての生き物を生み出した(創造した)という考え方。そしてその考え方を説明するにあたっては、いわゆる進化論まで盛り込んで考えることにも抵抗感を示さない。
というものだ。
有神的進化論という名称は、1877年にはすでに認知されていたようだ。ということは、この時代から議論が交わされ続けてきたことになる。新しい概念を示すこの言葉が初めて使われたのは、カナダの地質学者ジョン・W・ドーソンが書いた『The Origin of the World』(『世界の起源』:1877年刊)という本だった。
有神的進化論の論理的な枠組みは『創世記』の記述を検証していくというアプローチから成る。『創世記』では、5日目に水中の生物と鳥が創造された。ドーソンは次のように語っている。
“下等動物についての記述には、makeあるいはformという「作成」のニュアンスを感じさせる言葉が使われているのに対し、人間に関してはcreateという「作成」よりも一段上の「創造」のニュアンスを感じさせる言葉が使われている事実を指摘しておきたい”
それに、創造という言葉には自発的進化という要素が含まれない響きがある。このあたりに、生物の進化に物理的要因以外の力が関与していたという考え方が感じ取れないだろうか。
生物が環境に適するように器官を変化させていった事実の背景には、進化の過程における創造的な方向での介入があった。こうした方法で介入したのが神だったということになるのだろう。
有神的進化論そのものも、少しずつ変化していった部分があることも否めない。顕著なものをひとつ挙げるなら、“biologos=バイオロゴス”という概念だ。遺伝学者フランシス・コリンズが、有神的進化論の枠組みの中での自分の立場を表す言葉として用いた。
ヒトゲノム計画を率いたフランシス・コリンズは、かつては無神論者だった。『The Language of God』(『神の言語』)という本で、キリスト教的教義と科学(特に進化論)の共調について書き、無神論者からキリスト教徒への自らの変容について詳しく記している。この本を読んだ人々から、科学と信仰の親和性について多くの質問を受けるようになり、専門的に対応するため、2007年にバイオロゴス基金という組織を立ち上げ、2009年に議論の主な場をネットに移して、様々な年代の人々を巻き込むことに成功した。
“バイオロゴス”という言葉自体は、生命を意味する“Bio”と、学問や理由、あるいは言葉という意味の”logos”二つのギリシャ語をつなげた造語だ。
『ヨハネによる福音書』は、「初めに、ことば(ロゴス)があった。ことばは神とともにあった。ことばは神であった」という一文で始まる。文章はさらにこう続く。「このことばは初めに神と共にあった。すべてのものはこれによってできた。できたもののうち、一つとしてこれによらないものはなかった。このことばに命があった。そしてこの命は人の光であった」
コリンズがバイオロゴスという造語に込めた意味、その概念の立ち位置は明らかだ。地球の生命体は神の意志の表現にほかならない。まさに有神的進化論のエッセンスを体解する造語だったのだ。
一方、神学および物理学で博士号を保有する福音主義神学者デニス・ラムローは、“エボリューショナリー・クリエイション”‘(EC=進化的創造)という言葉を選ぶ。言葉としての重要性が“進化的”という形容詞よりも“創造”という名詞に置かれるべきであると信じているからだ。“Theistic Evolution”(有神的進化論)という言い方では足りないと思っている。このあたりにも、生物の進化に神という要素を何とかして盛り込み、その正当性を主張しようとする姿勢が見て取れはしないか。
有神的進化論の論者で圧倒的な存在感を放つと言われるジョージ・マーフィーも、有神的進化論という言葉自体に対してある種の疑念を明らかにする。しかし広く浸透しているため、その点にあえてこだわる姿勢は見せていない。また、基盤部である「進化論とは神による創造の方法である」という考え方には100パーセント同意している。
ここで指摘しておきたいのは、論陣の中心的人物でさえ、トレードマークとしての有神的進化論という言葉になんらかのマイナス感情を抱いている事実だ。自らのリーズニング=理由付けが希薄であることを実感していて、それによって目に見えない強迫観念が生まれているのではないか。そんなうがった見方をしてしまう。
有神的進化論グループにセクト的なものが存在するなら、それは背景となっているキリスト教の構造がそのまま投影された形になっていることも考えられる。そしてそれが事実なら、純然たる科学の枠組みの一部である進化論を盛り込もうとする有神的進化論の本質は、創造論よりも宗教的であると言えないだろうか。
有神的進化論に問題があるとするなら、前項で触れたとおり、進化論を認めながらも本質は創造論より宗教的、あるいは原理主義的である可能性を感じさせる一面にほかならない。さらに論を進めていくために、思想の骨子となる要素をここでもう一度リストアップしておく。
・聖書は、地球と森羅万象の起源、そしてそこに生きる生物に関する科学的知識を記したものとして信頼が置けるものではない。そもそも、科学について説くための書物ではないからである。
・聖書は、神と精神的なものごとに関する知識においては、信頼のおける書物である。
・科学的物証は、科学的な書物ではない聖書の内容とは無関係である。
・「創世記」第1章に記されている創造の物語は、真の創造主による信仰の告白である。目的は、汎神論および多神教に対する反証を示すことであり、神が実際に世界を創った方法を示すことではない。
・聖書は神が創造したことを伝えるためのものであり、どのように創造したかを伝えるためのものではない。
科学の枠組みの一部である進化論を盛り込むことを辞さない姿勢は、キリスト教機構全体を俯瞰すれば、異端以外の何物でもないはずだ。いや、異端という表現はソフトすぎるかもしれない。有神的進化論を“イスカリオテのユダ”と形容する人もいるのが事実だ。正統派という言葉の定義となると別次元の議論になるだろうが、少なくとも正統派キリスト教徒の目に、有神的進化論を信奉する者たちが裏切り者に近い存在として映っても決しておかしくはない。
当然ながら、科学界からも冷ややかな視線が向けられている。
アメリカ、ブラウン大学の生物学教授ケネス・R・ミラー博士は、次のように語る。
「有神的進化論という言葉には、神によって前もって定められたものが大前提になっている響きが否めない。進化の過程の結果はあらかじめ決まっていた上で始まったというニュアンスだ。進化の過程において及ぼされた外的要因はさまざまあるが、神という存在を中核的に位置づける態度は、科学に対する信頼を意味も理由もなく貶めるものにほかならない」
筆者は、こういうコンセンサスが存在するのではないかと思っている。
科学から見れば、創造論はあまりにも原理主義的で、科学と対極に位置する思想であるため、あえて論じる場を作る必要はない。宗教界から見れば、全く同じ理由で進化論と対峙する必要はない。
ところが、有神的進化論は、その本質がむしろ宗教、つまりキリスト教の原理的な思想であるにもかかわらず、前述のとおりキリスト教機構から裏切り者扱いされている。そしてミラー博士の言葉からもわかるとおり、科学界でも批判の的となっている。
かといって、まったく支持されていないかと言えば決してそうではない。ざっくりとくくった創造論という範囲における有神的進化論の立ち位置は、主流派科学の枠組みの中のID(インテリジェント・デザイン)理論のあり方に似ているのではないだろうか。

有神的進化論は、そのID理論が否定する「ダーウィニズムを含めた進化論」を受け容れている。ダーウィン進化論をより大きなスコープから見れば、星が進化し、太陽系が生まれ、その中で地球が誕生し、植物や動物が進化を遂げて、やがて人間が現れるまでの過程にほかならない。
有神的進化論は、人類を含め地球のすべての生物の進化の出発点となった生命体の存在を大前提としていて、神はその後、創造の一部として間接的に関わりながら進化の過程を見守った。地球が生まれる以前の時代に関しては、『創世記』の冒頭に記された“ことば”の概念だけに頼り切ったようなところがある。
こういう性質が、主流派科学からもID理論からも、そして、若い地球理論をはじめとする、神の存在を中核に据えたより原理主義的な宗教的思想からも敵視されるのではないだろうか。冒頭部分で、YEC(若い地球説)陣営から「有神的進化論の論拠は物証に基づく考察ではなく、感情論にすぎない」という批判があると書いた。その理由がこのあたりにあると感じる人も決して少なくないはずだ。
シリーズ3回までで、ID理論から始まって創造論、そして有神的進化論という3つの考え方について記してきた。それぞれの論陣が擁する地球の歴史、人類の進化に関する思想について見てきたが、これですべてを語ることができたとは思っていない。地球生物の進化の過程に何らかの影響を与えた要素として、地球外由来の存在を示唆する意見もある。それは「古代の宇宙飛行士説」と呼ばれている。
主流派科学、そしてオーソドックスな宗教論の枠組みからも外れたところで存在する古代の宇宙飛行士説にまで触れてこそ、地球生命の進化に関わってきたデザイナーという概念についてのID理論の検証がより完全な形になると思うのだ。
(2020年8月25日記事を再編集)
宇佐和通
翻訳家、作家、都市伝説研究家。海外情報に通じ、並木伸一郎氏のバディとしてロズウェルをはじめ現地取材にも参加している。
関連記事
神の機械「ニュー・モチーブ・パワー」が無限のエネルギーをもたらす!? 19世紀心霊テクノロジーの到達点
人間の女性と接続して無限のエネルギーを得る!? 神の御業に挑んだ、とある機械について。
記事を読む
ハワイ神話の小人族メネフネはムー大陸の末裔か? ポリネシア各地の遺跡と小さな人類の謎
南洋に伝わる、小さきものの神話。それは伝説のムー大陸と、消えた古代人類を結ぶ存在かもしれない。
記事を読む
人間の寿命はどんどん短くなっている!? 「太古の昔は900歳」聖書の記述と“神のプログラム”の謎
全知全能の神は不老不死であるほうがしっくりくるが、神に近い人々もまた驚くほど長生きであったことが聖書に記されている。しかし、なぜか年を経るごとに登場人物の寿命が短くなっていくのだ――。
記事を読む
予言者ババ・ヴァンガの遺言と謎の古代遺跡/MUTube&特集紹介 2024年7月号
未来を見通した、偉大なる女性がいた。世界の指導者がアドバイスを求めるほど正確に未来を語った予言者=ババ・ヴァンガ。その彼女が残した「遺言」は、未知なる古代遺跡の存在と、そこへ至るための道のりを示すもの
記事を読む
おすすめ記事

