「ファラオの呪い」の正体を最新科学で考察! 古代エジプト人によって放射線の罠が仕掛けられていた説
かつてエジプトでツタンカーメン王の墓の開封に携わった20人以上が、後に不可解な体調悪化でさまざまな病状を発症して死亡した。「ファラオの呪い」として恐れられていたこの出来事が最新研究によって科学的に解明
記事を読む
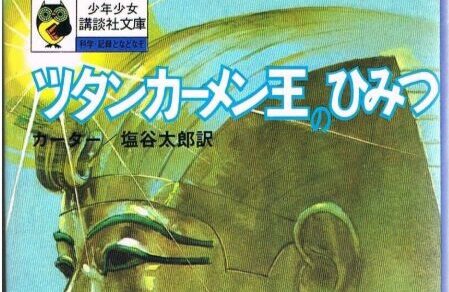
王の眠りを妨げるものは呪われる……! 「ファラオの呪い」が、現代の世界を震えさせた。懐かしくも恐ろしい怪奇譚を今、見つめ返す。
(2021年6月25日記事を再編集)
2021年春、70年代オカルトブーム世代にとって、なんとも懐かしいフレーズがメディアに氾濫した。「ファラオの呪い」である。70年代なかばあたりに続々と刊行された「ピラミッドの謎」「王家の谷の探検」「ツタンカーメンのひみつ」など、エジプト関連の児童書を読み漁った元・オカルト少年少女たちは、忘れていた小学生時代の戦慄や興奮を久しぶりに思い出したのではないだろうか?
この「ファラオの呪い」騒ぎのきっかけは、エジプトで2021年3月下旬に起こった事故の連鎖だった。
世界中が注目する大騒動となったスエズ運河のコンテナ座礁、ソハグ県の列車衝突事故、そしてカイロで起こった10階建てビルの倒壊……。これらの惨事の原因は、翌月3日に予定されていた「ミイラの移送」にあるのでは? という噂が現地で広まったのだ。
その日、老朽化した「エジプト考古学博物館」に展示されていたラムセス2世などのミイラ22体を、5キロほど離れた「エジプト文明博物館」に移送するパレードが大々的に行われることになっていた。この「王家の眠りを妨げる行為」が「ファラオの呪い」を発動させている、というわけだ。
特にスエズ運河の座礁事故の処理には、なんとあのユリ・ゲラーまでが参戦した。TwitterやInstagramで「3月27日の午前と午後の11時11分にみんなで念力を送り、あの船を動かそう! マインドパワーのエネルギーで運河を開放しよう! 船が動くイメージを頭のなかで映像化してくれ! 私はみんなの力を信じている!」と世界の「同志」たちに呼びかけたのだ。

そして27日当日、各国のメディアは半笑いで「超能力作戦は失敗した」と報道したものの、ユリ本人は「動いたぞ! ほんの少しだが船は動いた!」と報告。実際、ユリが指定した時刻にタンカーが「0.4度ほど南に動いた」のだそうだ。「タグボードで牽引作業をしていたのだからあたりまえ」という意見もあるようだが、ともかく「ファラオの呪い」という懐かしネタをめぐって、70年代オカルトの貴公子までが大活躍ということで、我々世代にとっては「懐かしオカルト祭り」のような様相を呈した騒動だった。
心配されていていた当日の移送パレードだが、結局は何事もなく盛大に行われ、現在では「呪い」の噂は鎮静化している。
ちょっとびっくりしたのは、エジプト考古学の最高権威、ザヒ・ハワス氏が「呪いなど存在しない。あれらの事故とミイラ移送はなんの関係もない」などと噂を一蹴する声明をわざわざ出したことだ。この人は一部のオカルト好きには非常に評判が悪いようで、「古代エジプト文明に関する研究の権利を独占し、他国の研究者を排除している」と目されることも多く、「なにか重大な秘密を隠蔽しているんじゃないか?」とまでいわれていた。それはともかくとして、彼があえて「呪い」に関する声明を出さねばならないほど、一時期は噂が現地の人々の間で蔓延していたのだろう。
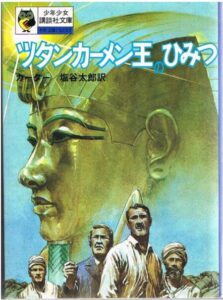
そもそも「王家の墳墓を発掘した者は呪いによって怪死する」という昭和っ子におなじみの逸話は、1920年代、英国の調査隊がツタンカーメンの墓を暴いたことをめぐってマスコミが書きたてて広まったものだった。「発掘にかかわった者が次々に謎の死を遂げた」というストーリーには、かなりのこじつけやでっちあげがあったようだが、その不気味さやリアリティに昭和の子どもたちは一発で魅了され、「ファラオの呪い」は各社のオカルト児童書の定番ネタとなっていく。
こうした「オカルト的古代エジプト観」(?)が僕ら世代の日本の子どもたちの間で定着するまでには、いくつかの段階があったと思う。
最初に子どもたちを魅了したのは、モンスター的にキャラクター化されたミイラだ。1932年にユニバーサルが制作した『ミイラ再生』にはじまる「ミイラ映画」、特に59年のハマー・フィルム制作『ミイラの幽霊』などによって、ミイラは「吸血鬼」「半魚人」「狼男」などと並ぶ西洋妖怪「ミイラ男」として日本の子どもたちにも「恐怖の対象」となった。1961年には国産テレビドラマ『恐怖のミイラ』が多くの子どもたちにトラウマを与え、この流れから60~70年代の特撮ドラマやアニメなどには、「ミイラ男」をモチーフにしたキャラクターがやたらと登場するようになった。
さらに1965年、東京を皮切りに「ツタンカーメン展」が開催される。連日の「殺人的混雑」がニュースになるほど盛況で、洋服から雑貨まで、ヒエログリフ柄の商品が売れまくる一大エジプトブームが勃発。その余波のなかでオカルトブームが到来し、「ツタンカーメンの呪い」「ファラオの呪い」「王家の谷の呪い」などのタイトルを冠したエジプト絡みの児童書が続々と刊行されはじめる。
「ファラオの呪い」の話はさまざまな児童書、オカルト系のものだけではなく、多数の学習読みものにまで掲載されていたが、1976年に『月刊プリンセス』(秋田書店)に連載された少女マンガ『王家の紋章』(細川智栄子あんど芙~みん・作)の影響も非常に大きかった。この時期の小学生たちのなかには、エジプトといえば即座に「呪い」をイメージしてしまう子も多かっただろう。
ほどなくデニケンの「古代宇宙人来訪説」などの影響で、子ども文化におけるエジプトの話題もSF的なものが主流になる。また一方で「ピラミッドパワー」が子どもたちの間でも話題になり、スピリチュアル方向へも展開。子ども文化における「オカルト的古代エジプト観」もだいぶ様変わりした。動きまわる死霊としてのミイラとか、古典的心霊譚じみた「呪いネタ」はすっかり下火になったはずなのだが、実に半世紀を経た今年、「ファラオの呪い」(の噂)がメラメラと再燃したわけだ。
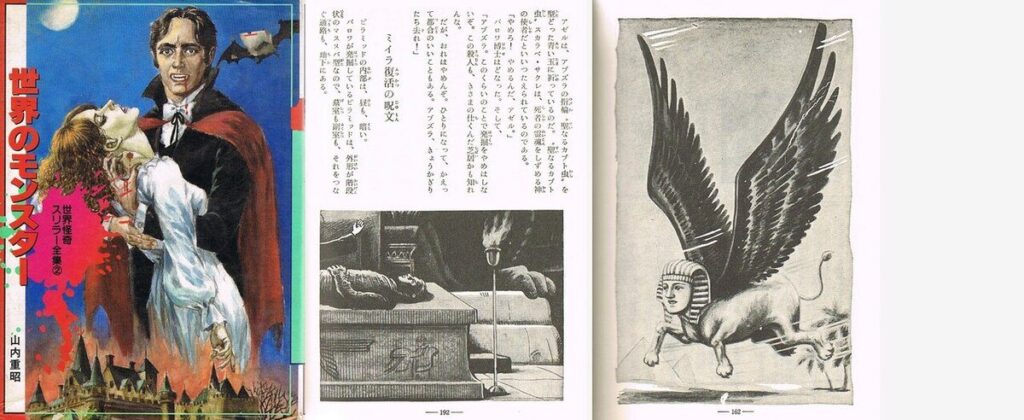
初見健一
昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。
ランキング
RANKING
おすすめ記事
PICK UP
関連記事
「ファラオの呪い」の正体を最新科学で考察! 古代エジプト人によって放射線の罠が仕掛けられていた説
かつてエジプトでツタンカーメン王の墓の開封に携わった20人以上が、後に不可解な体調悪化でさまざまな病状を発症して死亡した。「ファラオの呪い」として恐れられていたこの出来事が最新研究によって科学的に解明
記事を読む
怪物ミイラが生んだ”呪い・古代エジプト・即身仏”という隠れたブームたち/昭和こどもオカルト回顧録
昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想する。 今回のお題は「ミイラ」。いわゆるモンスターのミイラ男は、考古学にとどまらず子供文化からファッシ
記事を読む
「将門の首塚」と東京の定番怪奇スポット/昭和こどもオカルト回顧録
日本三大怨霊に数えられる平将門の祟りは、東京は大手町にある「首塚」の祟りを中心に語り継がれている。 昭和の時代、少年少女が恐れた東京の定番怪奇スポットを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想!
記事を読む
お父さんと争いごと 4コマ漫画「オカルとおさん」
月刊ムーで人気連載中の石原まこちん作「オカルとおさん」をwebムーでも公開!
記事を読む
おすすめ記事

