崖に向かって、押しつづける者とは…… ヤースー「喜屋武岬の霊史継承」/吉田悠軌・怪談連鎖
今もなお戦争の傷跡を色濃く残す島、沖縄。激戦地跡で、ユタの血を引く霊感芸人が体験した怪異とは。その記憶は世代を超えて受け継がれ、連鎖していく——。
記事を読む

夏休みは、子供たちがお盆と戦争という定番テーマを振り返るタイミングでもあった。筆者の戦争にまつわる怪談とともに、当時を振り返る。
子どもの頃から「一番好きな季節は?」と聞かれれば即座に「夏!」と答えていたのだが、さすがにここ数年の猛暑には辟易している。今年も連日の殺人的な暑さをなんとかやり過ごして、とにかく秋まで無事に生き延びたいものだと思うばかりで、昔のように「夏の情緒」を味わう余裕などまるでない。
子ども時代を思い出してみると、あの頃の夏は複雑で不思議な感慨を抱かせる季節だったと思う。ことに8月は特別だ。夏休みのまさにど真ん中、子どもたちにとってはプールに海水浴に家族旅行と、一年のうちで最もはしゃぎまくりたくなる眩しい季節、いわば光に満ちた「陽」の月である。
一方で、そこら中にうっすらと「死」の匂いが漂ってもいた。ひとつには「お盆」があるからで、ナスとキュウリで馬を作ったりする迎え火・送り火の習慣が多くの家庭でまだ行われていた当時、子どもたちも8月には「ご先祖の霊」を強く意識させられる。児童雑誌にも「霊」の話題があふれ、テレビでもこの時期は「心霊特番」が目白押しだった。8月は死の影に覆われた「陰」の月である(陰陽五行において夏は「陽」と決まっているが、そういう話をしているのではないのでご勘弁を)。
この「陽」と「陰」が微妙に重なった不思議な雰囲気は、近所の友人たちとこぞって参加した夏祭りや盆踊りにも濃厚に漂っていた気がする。そうした地域の祭礼的行事は数日前からワクワクしてしまうほど楽しいが、夏休みならではの非日常を堪能する楽しさのなかにいつも不吉な感じ、少し怖いような感じ、なんだかうら寂しいような感じがあった。
あの頃、町内の神社で開催されていた縁日の光景は今思い出すと幻のようだ。普段はひっそりと暗い境内のあちこちに黄色い鬼火のようなアセチレンランプが揺らぎ、見世物小屋とお化け屋敷は極彩色の泥絵の具で描いた毒々しい看板を掲げ、いつもは騒がしいだけのクラスの女子たちが薄化粧と浴衣姿ですっかり「化け」て、見知らぬ人のようなそぶりでそぞろ歩いている。真夏の宵に異空間へ迷い込んでしまったような気分になって、なぜだか心細さを感じることも多かった。
花火大会だってなにやら慰霊の儀式じみていた。玄関前の暗い路地で家族と楽しむささやかな花火も、はしゃぎながらはじめるものの、そのうちに「おもしろうてやがて悲しき」、最後の線香花火が消える瞬間は、毎度なんとも言い難い妙な気分になったものだ。
子どもたちの8月に「陰」を落としていたのは、「お盆」ばかりではない。8月は「終戦の月」だ。現在では「偏向教育」と呼ばれているらしい「戦後民主主義教育」がそれなりに徹底された状況で育った僕らは、日ごろから学校でも家庭でもさまざまな形で「反戦」を叩き込まれていたが、それをことさら意識させられるのが、やはり8月だった。宿題の読書感想文では課題図書の反戦児童文学作品を読まされてゲンナリし、テレビでも多種多様な「終戦特番」や「反戦映画」などが放映され、子ども向けのアニメやマンガにも戦争の話題が増え、見る度に鬱々とした気分になった。そんな傾向はあろうことか僕らが大好きな「お化けの世界」までをも浸食し、この時期に雑誌に掲載される「心霊特集」には必ずいくつかの戦争がらみの怪談が混じることになる。テレビの「心霊特番」にも「戦争怪談」は多かった。僕などは、南洋戦線の過酷さや東京大空襲の凄惨さなどを最初に知るきっかけになったのは、学校の授業などよりも「心霊特番」だったんじゃないかと思う。


僕らが首までどっぷり浸かっていたのは「戦争怪談」というより、戦後民主主義的「反戦怪談」と呼ぶ方がより正確なのだろう。「戦争怪談」にも長い歴史がある。その時代時代の戦争の性質や戦況、そして世情、つまり巷の人々が戦争をどう捉えてきたかによって、その趣きはガラリと変わる。「戦争怪談」もまた「世につれ……」なのだ。
例によって田中耕太郎センセイが蒐集した怪談集成本などから拾ってみると、例えば日清戦争の折には、霊峰高千穂峰に鎮座する霧島神宮付近に数万の「巨火」(火の玉の大群)が出現し、朝鮮半島に向かって飛び去った、という逸話が記されている。当時の人々は「神軍の遠征だ!」といろめきたったそうだ。さらに日露戦争の際にも東霧島山麓付近に同様の「巨火」が現れたそうだ。このときも「王師擁護の神軍の出現!」と九州地方では大きな話題になったと記録されている。
こんな話もある。やはり日露戦争中、とある一等兵が明治天皇から賜った勅語を前線の各隊に伝達するため、勅語の写しを入れた封筒の束を携えて進行していた。ところが敵の猛射を浴びて負傷してしまう。後に彼が握っていた封筒の束を調べてみると、空の封筒はすべて弾丸が貫通していたのに、勅語が入っていた封筒はまったくの無傷だったそうだ。
日中全面戦争が勃発した1937年には、より勇ましい「戦争怪談」が伝えられている。上海における激しい市街戦の最中、日本軍の戦車隊は「阿修羅のごとく」猛攻撃をしかけ、敵の野砲陣地を壊滅させた。その戦車の一台が味方の陣地へ悠々と引きあげてきたが、見ると乗組員はとっくに全員死亡しており、エンジンも破壊されていて動かない。操縦者もエンジンも失った戦車のあり得ない大活躍に、部隊内では「死んだ日本兵の霊が操縦していたのだ!」と噂になったという。
日清日露で大勝利、第一世界大戦を足がかりに大陸へと勢力を伸ばして満州国設立、日中戦争が勃発、そして膠着し、やがて太平洋戦争へ。そして真珠湾攻撃以降も大本営発表に浮かれていられた時点までは、「戦争怪談」には先述したような「戦意高揚怪談」の類が多く見られたようだ。戦後、こうした逸話は僕らの目に触れることはなくなり、代わりに無数に伝えられるようになったのが抒情的・悲劇的・厭戦的な「戦争怪談」である。なかでも家族の戦死に関する「虫の知らせ」、もしくは戦死した夫や息子が霊体となって帰ってくるというエピソードが圧倒的に多い。
夫が愛用していた茶碗が突然真っ二つに割れ、後に同時刻に彼が南洋で戦死したことが判明するとか、出征中の息子の「ただいま!」という声が玄関で聞こえ、家族が慌てて出ていくが誰もいない。翌日に息子の戦死が知らされるといった話だ。子ども時代の僕らがさんざん聞かされたこの種の話をいちいち挙げていけばきりがない。同じような話をあまりに繰り返し聞かされていた当時の僕らは、「戦争怪談」、いや「反戦怪談」にはほとほと食傷気味になっていた。どれも怪談としては「辛気臭くてつまらない」。それでもまた次の8月がめぐってくるたびに、僕らは「辛気臭くてつまらない」だけの「反戦怪談」をウンザリするほど聞かされることになった。それが子ども時代の僕らの夏だったのだ。
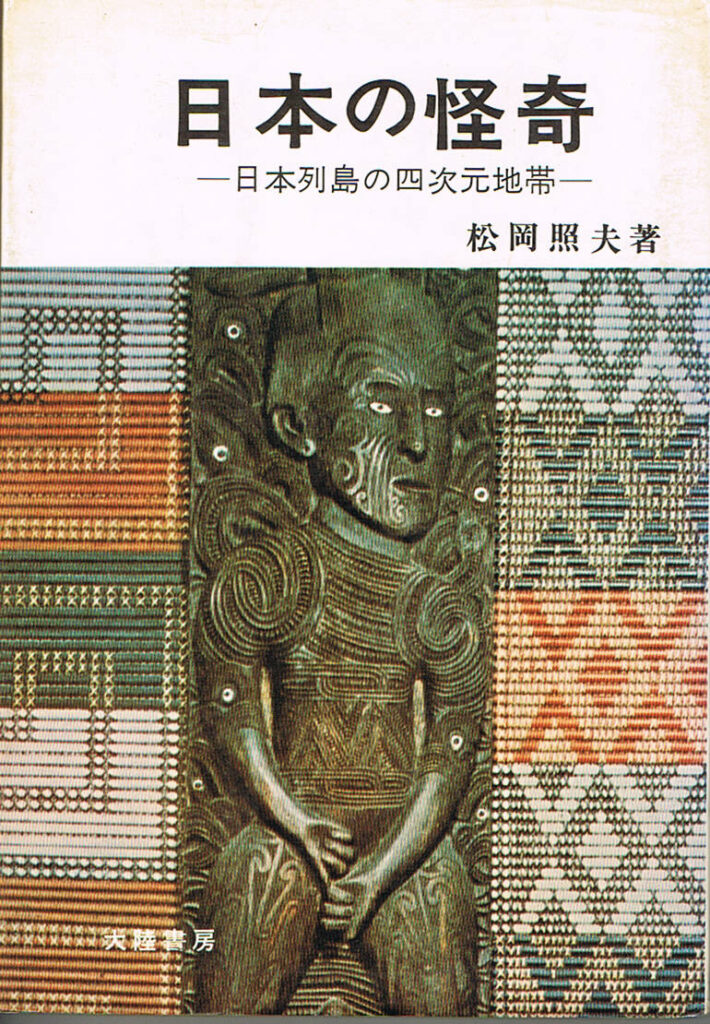
さて最後に、僕が通っていた小学校に伝わっていた「戦争怪談」を紹介してみたい。
僕の母校は戦前に竣工された鉄筋コンクリート3階建て。僕が入学した70年代なかばの時点で、すでになんとも古色蒼然としていて、お城か要塞のような雰囲気を持っていた。屋上には鐘楼(塔)があり、かつては校内に消防署が同居していたそうで、この塔が火の見やぐらとして利用されていた。東京都歴史的建造物に選定され景観意匠保存の対象となり、後に国の有形文化財に登録されている。
現在の目で見ると本当に趣きのある素晴らしい建物なのだが、あまりに荘厳で厳めしく、子どもの目にはかなり不気味に映った。特に屋上に屹立する鐘楼は印象的だ。塔への入り口になっている鉄の扉は封鎖されていて、「立ち入り禁止」の看板が掲げられている。こんな状況で、子どもたちがこの塔をめぐる「怪談」を生みださないはずがない。
「あの塔の窓に人影が見えた。防空頭巾をかぶった女の人が赤ちゃんを抱いていた」
塔の中に若いお母さんと赤ちゃんがいる……という話は、僕ら世代が入学するずっと前から生徒たちの間で代々語り継がれてきた噂だったらしい。戦時中、空襲を逃れて小学校に集まった近隣の人たちが、炎に包まれた塔で「蒸し焼き」になったという設定だった。これは根も葉もないデマで、以前に郷土資料で学校の歴史を調べてみてもよくわからなかったのだが、学校が近隣の避難所になった可能性はあるものの(その記録も発見できなかったのだけど)、空襲時にわざわざ塔のてっぺんに立て籠る人はいないだろう。
しかし、塔に潜む「防空頭巾をかぶった母子」というイメージは、強烈に僕らの心を刺激した。そして毎年必ず2、3回ほど、「〇組の〇〇さんが見たらしい!」というニュースが広まって、この怪談が校内で大ブームを巻き起こしていた。ブームの間は多くの子どもたちが休み時間の度に屋上に殺到し、塔の窓に目を凝らし続ける。わざわざ家からカメラや双眼鏡を持ってくるバカもいた。この状態が一週間ほど続いた後、みんな飽きてしまって、すっかり鎮静化する。そしてまた数カ月ほどたつと、突如「〇組の〇〇さんが見た!」というニュースが校内を駆け巡り、ブームが再燃するのである。6年間、こんなことの繰り返しだった。
そして僕も、一度だけ「塔の母子」を見たことがある!……ということにしておいてほしい(笑)。4年生だか5年生だかのときのブーム時の昼休み、僕は多くの子どもたちと一緒に塔の暗い窓に目を凝らし続けていた。20分ほどの昼休みの間中、みんなが押し黙ってひたすら塔を見あげているのだから、今思えばなんとも異様な光景だ。すると女子の一人が急に窓を指さして「あっ、いる! 見える!」と叫んだのだ。とたんにあちこちから「本当だ! 見えた見えた!」と呼応する声が聞こえた。その瞬間、僕も「うわ!」と声をあげてしまった。母子かどうかはわからない。女性かどうかもわからないが、暗い小さな窓をすっと誰かが横切った……ような気がしたのだ。
炎天下の屋上に長時間しゃがみ込んで、塔のてっぺんの小さな暗い窓を一心に凝視し続けていれば、そりゃあ何かを見てしまった気にもなるだろう。おまけに周囲でみんなが「見えた見えた!」と言いだせば、自分もすっかり「見えた!」つもりにもなると思う。

8月になっても「戦争怪談」など聞かれなくなって久しいが、今もあの小学校の子どもらは「塔の母子」の怪談を語り継いでいるのだろうか?……と気になって母校のことをあれこれ検索していたら、あの校舎が解体・建て替えの対象候補になっていることを知って驚いた。歴史的建造物として保存対象に認定されているので、そう簡単には解体できないようだが、現在、同区は小中学校の大規模な再編プロジェクトを進行しており、ともかく2034年以降に具体的な検討が行われることになるらしい。
「塔の母子」も、塔とともにきれいさっぱり消えてしまうことになるのかも知れない。すでに継承は途絶えているようだし、そもそも「そんなものは最初からいなかった」わけで、なんの意味もない感慨だと言われれば、もちろんそれまでの話だ。しかしそれでも、アホな僕らは儚い幻覚のような「塔の母子」によって、まがりなりにも毎年のように戦争とやらを意識させられてきたことだけは確かなのである。
初見健一
昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。
関連記事
崖に向かって、押しつづける者とは…… ヤースー「喜屋武岬の霊史継承」/吉田悠軌・怪談連鎖
今もなお戦争の傷跡を色濃く残す島、沖縄。激戦地跡で、ユタの血を引く霊感芸人が体験した怪異とは。その記憶は世代を超えて受け継がれ、連鎖していく——。
記事を読む
包帯男と戦争の影を従えて…怪人「トンカラトン」の増殖/吉田悠軌・怪談解題
前回(「トラウマ怪人トンカラトンの誕生吉田悠軌・怪談解題」)、オカルト探偵の調査によってみえてきたトンカラトン誕生前夜のようす。だがその先にはさらに大きな、怪談文化的バックグラウンドの広がりがあった。
記事を読む
開催されなかった「幻の万博」! 紀元二千六百年記念日本万国博覧会と神国大博覧会という歴史的事実
一年後に迫った大阪万博開催。しかし過去には、未開催に終わったいくつもの「幻の博覧会」があった…!
記事を読む
ケムトレイルもレプティリアンも……「陰謀論時代の闇」/ムー民のためのブックガイド
「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。
記事を読む
おすすめ記事

