今もなお奇跡が起きている! 聖母マリア出現の聖地 「ルールドの泉」の基礎知識
毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、フランス南部の小さな町で、少女が聖母マリアの導きで見つけた奇跡の水と、その発見の物語を取
記事を読む

自分がもうひとりの自分の姿を見たり、いるはずのない場所で自分の姿を目撃される?? 「ドッペルゲンガー」と呼ばれるこの不思議な現象を、洋の東西を問わず、体験した人物が少なからずいる。 その正体は、単なる幻覚か、幽体離脱か、あるいは一種のタイム・トラベルなのか?
目次
「ドッペルゲンガー」をご存じだろうか。ドイツ語で「二重の歩く者」という意味で、自分の姿を自分が見る、もしくはそこにいないはずの自分の姿が他者に目撃されるという現象だ。
古くから多くの人々の関心を引き、伝説や神話にも数多く登場。近代になってからは小説の題材として使われることも多い。また、歴史上多くの有名な人物が、自らのドッペルゲンガーを目撃したともいわれている。
本稿ではまず、さまざまな人物のドッペルゲンガー現象から紹介していくことにしたい。
「僕はこの影を見つめてゐるうちに第二の僕のことを思ひ出した。第二の僕、――独逸人の所謂 Doppelgaenger は仕合せにも僕自身に見えたことはなかつた。しかし亜米利加の映画俳優になつたK君の夫人は第二の僕を帝劇の廊下に見かけてゐた。(僕は突然K君の夫人に「先達てはつい御挨拶もしませんで」と言はれ、当惑したことを覚えてゐる。)それからもう故人になつた或隻脚の飜訳家もやはり銀座の或煙草屋に第二の僕を見かけてゐた。死は或は僕よりも第二の僕に来るのかも知れなかつた。若し又僕に来たとしても、――僕は鏡に後ろを向け、窓の前の机へ帰つて行つた」
これは『羅生門』『蜘蛛の糸』『杜子春』などの作品で知られる作家、芥川龍之介の遺稿のひとつとして、1927(昭和2)年に発表された『歯車』という作品の一節だ。
あくまでも小説ではあるが、なかなか興味深いことが書かれている。
主人公である「僕」は、「第二の僕」――すなわちドッペルゲンガーを見たことはないが、その「第二の僕」を見かけたという人には複数、会っている。そして「死」は「僕」ではなく、その「第二の僕」に先に来るかもしれない、と。
じつは芥川は、自身のドッペルゲンガーを見たことがあると、ある座談会で語っている。
それは彼の死の2か月前のことだった。講演旅行先の新潟で行われた座談会の席でドッペルゲンガーの体験があるかと問われた芥川は、こう答えている。
「あります。私は二重人格は一度は帝劇に、一度は銀座に現れました」
対談相手から、錯覚か人違いではないかと確認されると、次のように反論している。
「そういって了(しま)えば一番解決がつき易(やす)いですがね。中々そう云い切れない事があるのです。或人(あるひと)の話で、自分の部屋に入ったらちゃんと机に向かっている第二の自分が立ち上がって出て行ったので、母に話したらいやな顔をしたそうです。そしてまもなくその人は死んだそうです。その家は代々そうして二重人格が現れて人が死ぬんだそうです」(『芥川龍之介未定稿集』)
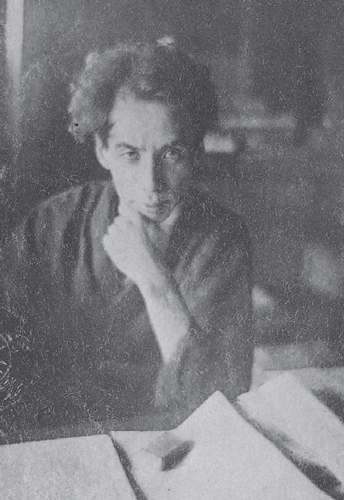
芥川のこの発言は、江戸時代に只野(ただの)真葛(まくず)が著した随筆『『奥州波奈志(ばなし)』の記述を意識したものと思われる。
同書は主に東北地方の怪異譚についてまとめられたものだが、そのなかにドッペルゲンガーと思しき話が見られるのだ。
それによると――。
北勇治という男が帰宅したとき、自分の部屋で机にもたれかかり、座っている男の姿が目に入った。無断侵入を怒鳴りつけようとしたのだが、どうも様子がおかしい。髪の結い方、着物や帯の柄、背格好が自分と寸分違わないのだ。勇治が顔を確認しようと近づくと、男は細く開いた障子の隙間から戸外へ飛びだし、消えてしまった。
食卓でこの話を聞いた義母は、何もいわずに眉をひそめた。あとで知ったのだが、北家では先代も先々代も、「もうひとりの自分」を見たあと、時間を置かずに死んだというのだ。勇治は婿養子だったので、それを知らなかったのである。そして勇治もまた、その年のうちに病を患い、亡くなったという。
芥川は間違いなく、この北勇治という男の話を意識していたと思われる。そしてドッペルゲンガーを見た自分も間もなく、この男のように死ぬのではないかと恐れていた。
実際、その2か月後、自ら命を絶ってしまったのだ。
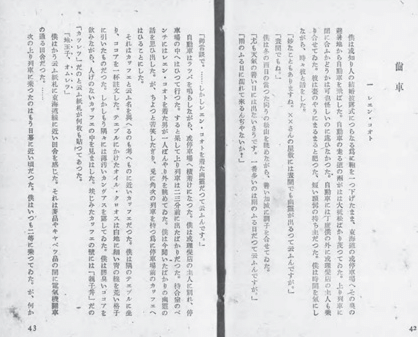
ちなみに芥川は1917(大正6)年に、『二つの手紙』という、3度も自分と妻のドッペルゲンガーを目撃してしまった大学教授の手紙が紹介される形式の短編小説も書いている。
このなかで芥川は、世界でもっとも有名なドッペルゲンガー体験者として、ドイツの文豪ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテと帝政ロシアのエカテリーナ2世の名を挙げている。
まず、エカテリーナ2世のケースから見てみよう。
ある晩のこと、寝室で休んでいたエカテリーナ2世のもとに、召使いがやってきた。召使いは彼女の顔を見てけげんな顔をする。問いただすと、彼女が玉座の間に入っていくのを見たので確認にきたというのだ。
エカテリーナ2世が玉座の間に行くと、確かに自分が玉座に座っている。だが、その姿はどことなくはかなげで、まるで幽霊のようだった。エカテリーナは即座に、衛兵に玉座に向かって発砲するように命じたという。
結果がどうなったのかは、わからない。だがエリカテーナ2世は、それからまもなく亡くなってしまったのである。

もうひとりのゲーテは、近代ドイツ文学を代表する文豪だ。
学生時代、ゲーテは大学近くのゼーゼンハイム村に住む牧師の娘フリードリケに恋をした。だが、卒業を機に故郷へ帰ることになったので、彼女に別れを告げるため、ゼーゼンハイム村を訪れることになる。
傷心を抱えたその帰り道。ゲーテは前方から馬に乗ってやってくる男とすれ違った。見ると、毛髪の色も目の色も鼻の形も、まさにゲーテと生き写しだった。唯一違っていたのは服装で、男は金色の縫い取りが入った青灰色の服を着ていた。
不思議なことに男は間もなく消えてしまい、ゲーテもそのことを忘れていたのである。
ところが――。
それから8年後、ゲーテは再びゼーゼンハイム村を目指して馬に乗っていた。同じ道を進んでいくうちに、自分の服を見て、ふとあの日のことを思いだした。
なんとそれは、8年前に見た自分の姿そのものではないか!
そうなのだ。ゲーテはあのとき、「8年後の未来の自分」を目撃していたのである。
ゲーテには友人のドッペルゲンガーの目撃体験もある。
それは1813年の冬のことだった。助手とワイマール公園を散歩していたゲーテは、友人のフリードリッヒ・ロホリッツの姿を見かけた。だが、どうも様子がおかしい。ロホリッツはゲーテのガウンをまとい、スリッパをはいているのだ。
「あれはロホリッツではないか。それにしても、なんという格好をしているのだ」
ゲーテの言葉に助手もその方角を見たが、だれもいない。「どこにもいませんよ。見間違いではないですか?」
怪訝に思いながらゲーテが帰宅すると、はたしてそこにはロホリッツが待っていた。しかも、ゲーテが見たままの奇妙な格好のままで、だ。
「いったいどうしたのだ?」
ゲーテの問いに、ロホリッツはこう答えた。
「ここに来る途中でずぶ濡れになったので、君のガウンを借りたんだ。待っている間にうたた寝をしてね。そう、ワイマール公園で君と会う夢を見たよ」
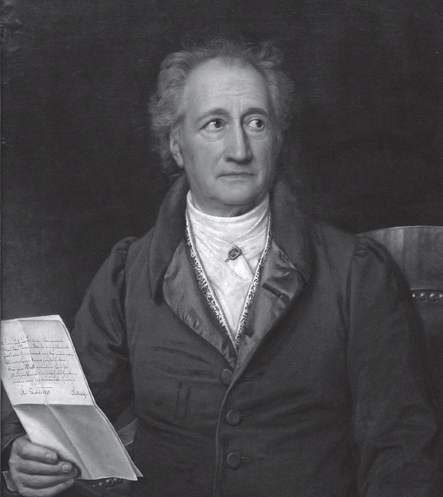
芥川が不安を感じていたように、自分のドッペルゲンガーを見た者は、間もなく死を迎えるといわれている。だが、それとは逆に、ドッペルゲンガーによって命を救われたケースもある。
第2次世界大戦中の1944年のことだ。ヨーロッパ戦線において、連合軍のある兵がドイツ軍の集中砲火を浴びて火だるまになった。その瞬間、なんと兵の体がふたつに分離した。本体は火だるまになって地面を転げまわっている。一方、分離したもう一体は宙に浮かび、こう叫んだ。
「近くに水たまりがある! そこに飛び込め!」
その叫びに導かれて、兵は水たまりに転がりこんだ。こうして兵は、一命をとりとめたというのである。
あるいはこんなケースもある。
1947年3月、春休みを終えたアメリカの大学生ゴードン・バーロウは、大学があるララミーまで約800キロの道のりを車で走っていた。
かなりの疲労を覚えてきたころ、運が悪いことに、天候が荒れてきた。視界をふさいでしまうほどの猛吹雪のなか、寒気と激しい疲労を感じたバーロウは車を停め、少し休むことにした。
時刻は夜の11時。通る自動車もない。バーロウは、凍死の恐怖を感じたという。
そのときのことだ。ヘッドライトに人影が映った。見ると軍服を着ている。その男はバーロウの自動車に近づくと、窓を軽く叩き、こういった。
「だいぶ疲れているようだな。運転を代わってやろうか」
疲労でぼやけた目で、バーロウは男の顔を見ていた。その軍服には見覚えがあった。第2次世界大戦に従軍中、自分が着ていたものとよく似ていたのだ。
いや、それどころか男の顔まで、自分とそっくりではないか。
だが、疲労はバーロウの思考能力をはるかに上回っていた。バーロウはのろのろと後部座席に移ると、そのまま泥のように眠り込んでしまったのだ。
やがてバーロウは目を覚ました。吹雪はすっかりおさまっている。周囲を見渡すと、目的地ララミーのすぐ近くのようだ。あれから2~3時間ほど、たっているのだろうか。
だが、運転席にはだれもいなかったのである。

このほか、歴史上の有名人では、アメリカの第16代大統領エイブラハム・リンカーンも自分のドッペルゲンガーを見たといわれている。
また、フランスの作家ギ・ド・モーパッサンは、自分のドッペルゲンガーの「口述筆記」によって小説を書くという体験をしている。
ある深夜、書斎で原稿を執筆していると、音もなく部屋の扉が開き、ひとりの男が入ってきた。男は机の反対側の椅子に座り、モーパッサンが執筆中の小説を口述しはじめたのだ。
モーパッサンは男の言葉のまま、筆記を続けた。
スポーツで「ゾーン」という言葉がある。集中力が極度に高まり、通常ではない状態に到達42することだ。このときはモーパッサンも、そのように受け止めていた。作家にとって、ペンに「言葉の神」が降りてくることは決して珍しくはないからだ。
モーパッサンは、一度も顔をあげることもなく、男の言葉のまま、夢中になって筆記を続けていた。だが、どうも様子がおかしいことに気づく。あまりにも言葉が鮮明なのだ。モーパッサンが顔をあげると、そこには自分自身の姿があったのである。

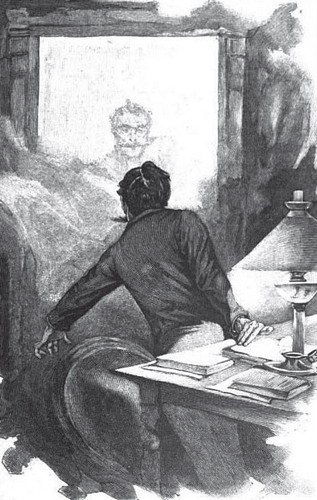
最後に比較的最近のケースも紹介しておこう。
2003年7月7日、アメリカのニューヨーク州在住の高校教師リサ・ステーシーのもとに、1枚の写真が送られてきた。
それは彼女の家の庭で撮られたもので、2台の車が写っていた。1台は彼女が現在乗っているもの、1台はかつて彼女が所有していたものだ。その古い車を購入した男性が、修繕して彼女に見せにきたとき、記念にと撮影して帰ったのである。
写真を見て、リサの母親がこういった。
「リサ、あなた、車のなかで何をしていたの?」
「何をいってるの? 私、車になんか乗っていないわよ!」
そういいながら写真を見たリサの手が震えた。奥にある車の後部座席の窓に、こちらを向いた女性の顔が写っている。リサの顔に間違いなかった。
だが、それは絶対にあり得ないことだった。
なぜならこの写真を撮影したのは、リサ本人だったのである。
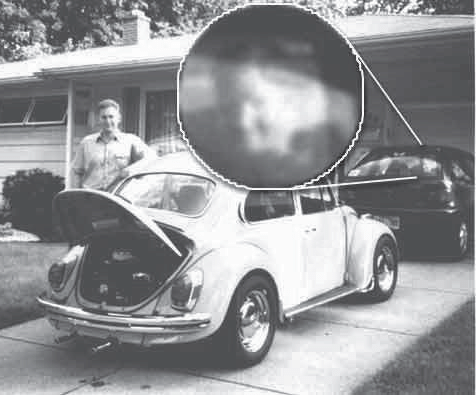
複数のドッペルゲンガー現象を見てきた。ここからは改めて、この不思議な現象について検証してみることにしよう。
まず、ドッペルゲンガーには、いくつかの特徴があるとされる。
●目撃されたり声をかけられたりしても、いっさい会話を交わさない。
●出現場所は限られていて、基本的に本人と関係のある場所にしか出現しない。
●ドアの開け閉めなどができることから、そこになんらかの「実体」があると考えられるのだが、それにもかかわらず忽然と消えてしまう。
●目撃すると、それは当人にとって「死の前兆」となる(ただし、すべての人がすぐに亡くなるわけではなく、なかには自らの命をドッペルゲンガーに救われたケースもある)。

こうした特徴を意識しながら、いくつかの説を確認してみよう。
まず、現代社会において最初に疑うべきは、心的疾患、すなわち脳による幻覚説だ。
心理学では、自分で自分の姿を見る症状を「自己像幻視」と呼ぶ。ただしこれはあくまでも視覚的な作用であり、独自の行動を取ることはない。つまり、本人の動きをまねる鏡像にすぎないのである。
だが、ごくまれに「ホートスコピー」と呼ばれる、自己をまねないケースが報告されている。この場合、本人との間に交流が発生することがあるのだが、そのときには敵対的な態度を示すことが多いといわれている。
しかし、いずれにしてもこれらは、あくまでも「脳内における幻覚」となる。であれば、他者が目にすることはないし、扉を開けたりすることはできないはずだ。
ましてや、アメリカの教師リサのように、ドッペルゲンガーが写真に写るなどということはあり得ない、ということになる。
次に、生きた人間の肉体から魂(の一部)が離れて自由に移動するものを「生き霊」というならば、ドッペルゲンガーは生き霊の仕業と考えることもできる。
ただ生き霊の場合は、強い執着を抱いている相手の前に姿を現すのが一般的だ。したがって、それを本人が目撃するというのは、不自然に思える。
問題は、本人の意志に関係なく、魂がふらふらと離れてしまうケースだ。確かに昔から日本では、ドッペルゲンガー現象を肉体から魂が離脱する「離魂病」の一種と考えてきたし、また魂が離れやすくなっている不安定な状態だからこそ、死期が近いと見なされたともいえる。
興味深いのは、臨死体験における幽体離脱だ。
臨死体験中の人物が、遠く離れた場所で目撃されることは、確かにある。しかし一般的には、肉体の自分を見ているのは霊体であって、あくまでも主体は霊体のほうにあるといえる。そこはドッペルゲンガーとは大きく異なる点だ。

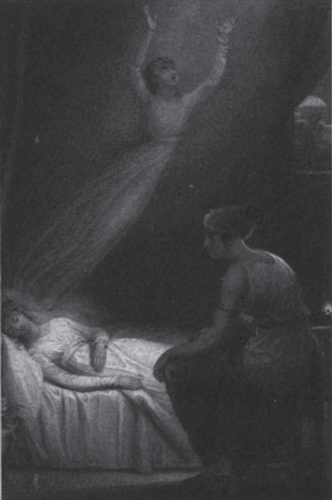
ほかには、ゲーテが8年後の未来の自分を見ていたことから、一種のタイム・トラベル現象とする説もある。もしくはパラレルワールドが関係していると考えることも可能だ。
さらにいえば、本人が気づかないうちにテレポーテーション(瞬間移動)していたという説明もある。
しかし、これらはいずれもかなり空想的な説明であり、現状では否定も肯定もできない。
とくにタイム・トラベル説では、『奥州波奈志』のように、ドッペルゲンガーが本人と寸分違わぬ姿をしていた場合、説明がつかないのである。
このようにドッペルゲンガーは、さまざまな側面を持つ現象だ。と同時に、心霊から超能力、超科学まで、ありとあらゆるオカルト分野にまたがった出来事でもある。その意味でも、きわめて重要かつ壮大な研究対象のひとつといえるのではないだろうか。
(月刊ムー2018年9月号掲載)
関連記事
今もなお奇跡が起きている! 聖母マリア出現の聖地 「ルールドの泉」の基礎知識
毎回、「ムー」的な視点から、世界中にあふれる不可思議な事象や謎めいた事件を振り返っていくムーペディア。 今回は、フランス南部の小さな町で、少女が聖母マリアの導きで見つけた奇跡の水と、その発見の物語を取
記事を読む
天王星が移動し、ATMや電子マネーにトラブルが発生!?/Love Me Do の「ミラクル・アストロロジー」2025年11月
アイドルの電撃婚や活動休止から大統領選の行方まで、さまざまな大事件を予言し、的中させてきたLove Me Doさんが、2025年11月8日から12月8日までの社会情勢と12星座の運勢を西洋占星術で占い
記事を読む
一粒万倍日やボイド時間をチェック! 2024年2月の開運カレンダー
2024年2月のラッキーデーがわかる! 大安などの吉日のほか、宝くじ購入によいとされる一粒万倍日や、金運にツキのある寅の日などをご案内。
記事を読む
凶を吉に、吉を大吉に転じる秘法と秘咒を公開!/大宮司朗の古神道開運秘伝(2)
霊学・古神道・道術の研究家であり、日本における玄学の第一人者・大宮司朗師による開運指南の第2弾。今回は、だれでも無理なく実践できる運気向上の秘法と秘咒をお伝えする。ぜひ2026年の開運に役立てていただ
記事を読む
おすすめ記事

