五島勉が仕掛けたもうひとつの「大予言」! 『ファティマの秘密』の低温ブーム/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録
あの五島勉がノストラダムスに続く新たな大予言として打ち出した『ファティマ・第三の秘密』。しかし、当時のこどもにはいまいちピンとこなかった?
記事を読む

昭和の時代、少年少女がどっぷり浸かった怪しげなあれこれを、“懐かしがり屋”ライターの初見健一が回想。 前回に続き、故五島勉氏の仕事を回想する。通俗作家として時代を切り裂いていった筆は、予言というテーマを掘り当てるーー。
現在では、というか70年代初頭以降は、五島勉といえばとにもかくにも「ノストラダムス」であり、この文脈以外で語られることはほとんどない。狂信者、陰謀論者、詐欺師……といったネガティブなパブリックイメージも、すべてこの文脈を踏まえたものだ。そこで、まずは一度この手垢のついた文脈から離れて、「五島勉とはなんだったのか?」ということについて考えてみたい。
彼が一応はプロの「文筆家」として活動するきっかけとなったのは、学生時代、小遣い稼ぎに雑誌に投稿したポルノ小説だったという。大学卒業以降は、主に女性週刊誌を中心にルポルタージュ記事の分野で活躍した。
昭和の時代の女性週刊誌の記事のエグさについては、同世代であれば説明不要だろう。目玉となる記事は、エロとグロに彩られたセンセーショナルなものばかり。「通俗」をはるかに超えた「露悪」である。当時、「エロ、グロ、ナンセンス」というフレーズをよく耳にしたが、女性誌の場合はここに「オカルト」も入ってくる。
この部分を細かく説明している紙幅はないが、80年代までの女性誌にはオカルト関連のトピックは柱の一つであり、猟奇的事件の詳細な(というか、ホラー風味に盛りまくった)ルポの延長として、超常現象や心霊事件などが扱われていた。メインメディアはあまり取りあげなった「コックリさん」や「口裂け女」のブームをあそこまで巨大なものにしたことにも貢献している。この傾向は平成に入ってからも残っていて、岐阜県富加町の「ポルターガイスト事件」の際、大々的に報じて事態のエスカレーションを招いたのも女性週刊誌だ。
ちょっと話が逸れるが、80年代初頭の日本でインディーズ系のパンクが台頭してきたころ、血まみれのパフォーマンスを展開していたスターリンやじゃがたらなどのバンドを最初に取り上げたのも、音楽誌ではなく女性週刊誌だった。性器を露出したり、生きた蛇を裂いたり、剃刀で自分の肉体を切り裂いたり、動物の臓物を客席にブチまけたりするライブの光景を、「頭のおかしい変態猟奇バンドの凶行とカルトな観客たちの異常な熱狂」といったノリで、ほとんどオカルト記事のようにオドロオドロしくルポしていた。これが80年代までの女性週刊誌の典型的ノリで、エロでグロでアンモラルなネタならなんでもよく、それらをさらに100倍くらいエグくして伝える……というのが昭和の女性週刊誌というメディアの「基本機能」のひとつだったのだ。
五島勉はこうした「下世話」なルポの取材を手当たり次第にこなしていたようだ。単行本化された彼のルポを見てみると、特に性の問題を扱ったものが多い。「乱れきった現代女性のセックス観」や娼婦の実態、そしてナマナマしい性犯罪のレポートなどである。僕ら世代の感覚からいうと完全に『金曜スペシャル』のノリなのだが、この60~70年代の通俗ジャーナリズムの空気はもともとヤコペッティの『世界残酷物語』(と彼がそれ以前に手掛けていた「夜もの」と呼ばれるイタリア産ドキュメント映画)など、一連のフェイクドキュメント映画の世界的大ヒットによって熟成されたもので、こうした方向は五島勉の個性によるものではなく、当時の週刊誌的現場やテレビの通俗ドキュメントの制作現場のメインストリームだった。
五島勉の個性ということをいうのであれば、彼の場合、敗戦後に多発した米軍による日本人女性暴行事件などを追及しており、そこから政治的・陰謀論的な方向へ多少接近する傾向が見られることだろう。
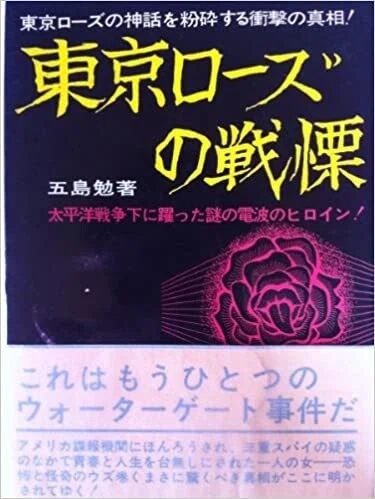
いずれにしても弱者、日陰者、被蹂躙者の立場に身を置き、その怨念のようなものを表現しつつ、しかしあくまで「通俗的娯楽読み物」として「おもしろおかしく」(と言ってしまうとミもフタもないが)描くという五島の下積み時代を見ていると、同じく女性週刊誌の現場でキャリアをスタートさせ、のちに昭和的反権力ルポライターの象徴、伝説の「ケンカ屋」となる竹中労を連想してしまうのだが、その文筆家としての出自は多少重なるものの、行き着く先はまったく別世界……というのがおもしろい。
おそらく五島勉という人には、強固なイデオロギーも、政治的信条も、なんらかの闘争への意思も、さしてなかったのだと思う。さらに言えば、オカルト的感性、ガチに神秘主義に参入するほどの「あちら側」への興味も、実は持ち合わせていなかったのだろう。これは彼への批判ではなく、要するに「狂信者、陰謀論者、詐欺師」といった批判は、まったく的外れだと思うのだ。
「五島勉とはなんだったのか?」という問いに対しては、徹頭徹尾「ルポライター」だったと答えるしかない。
そのときどきにセンセーショナルなトピックを嗅ぎ分け、それを「通俗的」に処理し、読者のゲスい好奇心を満足させる刺激的な形でスピーディーに提供していくルポライター。もっと言えば典型的な昭和の「売文屋」である。泥臭く、それなりに勘がよく、相応に剛腕な「売文屋」だ。彼はそういう書き手として、あくまで女性週刊誌流の処理のしかたで、ある意味では「無責任」にネタを集めて、加工して、バラ撒く。この作業をひたすらやり続けた人だったのではないか。
一時期、彼はルポライターから小説家への転身を図っている。「未亡人製造機」と揶揄された欠陥戦闘機をめぐる『死のF104』、デパート業界内で女スパイが「007」ばりに暗躍するハチャメチャなスパイ小説『BGスパイ デパートを燃やせ』などを手掛けるのだが、どれもふるるわず。結局、その後もあまり脈絡のないルポ作品を書き続けている(やはりエロ関連が多く、ほかに某宗教団体のプロパガンダ的なものも書いている)。僕ら世代が子ども時代、五島勉の「著者紹介」でよく見かけて違和感を覚えた『コイン利殖入門』なんてものを出したのもこのころだ。
まぁ、鳴かず飛ばず……という感じだったこの時代に(といっても、ルポライターとしてはそれなりの活躍だろう。彼はおそらく雇われルポライターとして駆けずりまわる状況から抜け出して「著作家」になりたかったのだと思う)、五島は祥伝社にひとつの企画を持ち込む。
テーマは「予言者」。各時代の著名な「予言者」を10人セレクトして紹介し、「予言」というものを総括的に語る本の企画だった。
ところが、編集者から「10人をまとめて語るよりも、このノストラダムスだけでまるごと1冊つくってはどうか?」とアドバイスされる。これで彼のその後の運命は決定する。あとは誰もがご存じの通りだ。
僕には『ノストラダムスの大予言』もまた、それ以前に五島氏が出していた性愛ネタなどの雑多なルポ作品となんら変わるところのない、女性週刊誌記事的な「露悪ルポ」のノリで書かれているように見える。刺激に満ちた内容をひととおり楽しんだら読み捨て、捨てればきれいさっぱり忘れてしまう「キオスクの新書」。いわゆる昭和的「飛ばし記事」の伝統的なタッチだ。見世物小屋的娯楽には正しい「無責任」が内容にも文体にも色濃い。
ところが、これがテーマ的にも、状況的にも、時代的にも、決定的な誤算だった。それになにより、記録的に「売れてしまった」ということが最大の誤算だった……。
次回は、この五島勉の「誤算」という観点から70年代の「ノストラダムスブーム」を回顧してみたい。
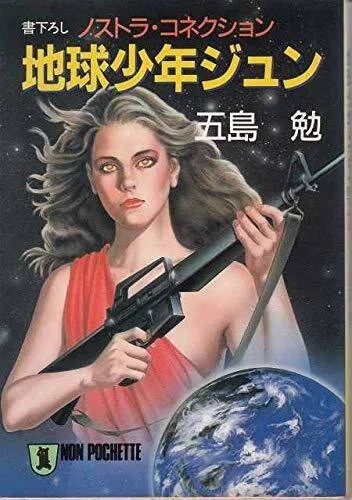
初見健一
昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。
ランキング
RANKING
おすすめ記事
PICK UP
関連記事
五島勉が仕掛けたもうひとつの「大予言」! 『ファティマの秘密』の低温ブーム/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録
あの五島勉がノストラダムスに続く新たな大予言として打ち出した『ファティマ・第三の秘密』。しかし、当時のこどもにはいまいちピンとこなかった?
記事を読む
70年代オカルトの大衆化と超古代史”ガチとの遭遇”/ムー前夜譚(2)
70年代の大衆的オカルトブーム最後の花火として1979年に打ち上げられた「ムー」。ではそもそも70年代に日本でオカルトがブームとなった背景は? 近代合理主義への対抗が精神世界という言葉以前の現実問題だ
記事を読む
実践超能力「ダウジング」が70年代こどもオカルトの源流だった! マンガから水道局までのブームを回想/初見健一
“懐かしがり屋”ライターの初見健一が、昭和レトロ愛好視点で当時を回想。今回は、オカルトキッズがこぞって試した「ダウジング」で、70年代子どもオカルトの源流へと遡る。
記事を読む
昭和のオカルト的「秘密結社本」の歴史を振り返る/初見健一・昭和こどもオカルト回顧録
昭和のオカルト少年たちを興奮させたキラーワード「秘密結社」。当時のこどもたちは、いつから、何を通してこの話題を知り、楽しむ(?)ようになったのか。昭和「秘密結社本」の系譜をひもとく。
記事を読む
おすすめ記事

