「お札をはがしてくれ……」竹内義和が霊からお願いされた怪談からの連鎖/吉田悠軌・怪談連鎖
土地に根づいた怪異・怪談と、個人が体験する一回性の怪現象。それは相反するようでありながら、ときに補いあい、連鎖することがあるようだ。
記事を読む
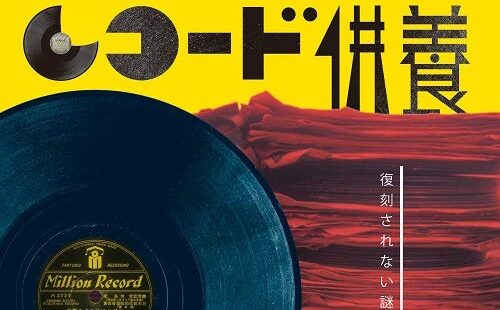
「私にも聞かせて」「せんぱ~い」……制作者も知らずに録音されてしまった死者(?)の声の事例は数知れず。語り継がれる心霊レコードを振り返る。まずは邦楽から!
レコードやCDに記録された楽曲に奇妙な声や音が録音されている……というのは70年代の怪談の定番ネタで、一時期は夏になるとテレビや週刊誌などで盛んに特集されていた。
いや、昭和の時代に盛りあがった懐かしネタというだけでなく、昨今も周期的にweb上などで話題になっているようだ。近頃ではEVP(Electronic Voice Phenomenon)と総称されることが多いらしいが、今回と次回はこの現象を取りあげてみたい。前編は「邦楽編」として僕ら世代が子ども時代から親しんだおなじみのネタを中心に考察し、次回「洋楽編」では欧米のポップミュージックにまつわるさまざまな噂を紹介する。
というわけで、さっそく「邦楽編」の本題に入りたいところだが、とにかくこの種の現象に関しては、先述した通り我々世代にはすっかりおなじみの定番ネタがいまだにコスられまくっている状況なので、多くの人がすでに「聞き飽きた!」という気分になっているかも知れない。あまり新鮮味を感じにくいトピックではあるのだが、ともかく70年代なかばから昭和末期までの間に話題になった事例を、ド定番から少々マイナーなものまで、時系列に沿って見ていこう。
その前に、「この世ならぬ声・音が録音媒体に記録される」という発想はいつごろからあるのか?ということに少し触れておきたい。
一般的には、1901年にアメリカの民俗学者が録音したシベリアのシャーマンのドラム演奏に「霊の声が入っていた」という事例が知られており、これが端緒とされているようだ。上記のEVP(Electronic Voice Phenomenon)は本来、現世に残存する「霊の声」を電気的に記録する試みといった意味であり、20世紀初頭の近代スピリチュアリズム勃興の時期に盛んに研究されていたという。トーマス・エジソンが「死後の世界」と交信するための特殊な音響機器を開発していた、という話も有名だ。
日本でも1930年代に『霊界通信』と題されたレコードが発売されている。霊媒師・亀井三郎が死者の魂を自分に憑依させ、その声を聞かせる実験を記録した実況録音ものだったらしい。解説を担当しているのが、かの浅野和三郎。現在は謎のトンデモ音源を集めたオムニバスCD『レコード供養 復刻されない謎の音盤たち』で聴くことができる。

前置きが長くなったが、前置きついでもう少し脱線させていただきたい。
僕がこの種の「心霊レコード」ネタに触れるたびに思い出すのは、内田百閒の小説『サラサーテの盤』だ。幻想文学とも怪談ともつかない独自の夢幻的怪異譚の多い百閒作品のなかでも、その不穏さで強烈に印象に残る傑作である。この作品に登場するのが、パブロ・デ・サラサーテが自ら「ツィゴイネルワイゼン」を演奏している1904年録音のSPレコード。演奏の途中でサラサーテがなにか聞き取れない言葉をささやく「謎の声」が録音されてしまっており、作品としては「できそこない」、しかし「珍品」としてマニアの間では有名な盤だったという。
小説の主人公は、このレコードを病死した親友から借り受け、借りたことをすっかり忘れてしまっている。ある夜、死んだ友の未亡人が家にやって来て、あのレコードを返してくれと言う。未亡人はどこか様子がおかしく、話もなにやら噛みあわない。彼女が一緒に連れてきた幼い娘は、なぜか主人公を怖れているらしく、執拗に避ける。後日、部屋を探してレコードを見つけ出した彼は、それを未亡人宅へ持っていく。彼女は彼を小さな座敷に通すと、おもむろに蓄音機でレコードを鳴らしはじめる。例のサラサーテの声が聞こえる箇所にさしかかったところで、主人公は違和感を覚えた。なにを言っているのかわからぬサラサーテの声が「いつもの調子より強く」聞こえたような気がしたのだ。すると突然、一緒に聞いていた未亡人が蓄音機に向かって身を乗り出し、レコードの声に応えるように「いえ、いえ、違います」と口走って泣きはじめる……というところで小説はぷつりと途切れる。
別に「霊の声」の話でも「EVP」の話でもないのだが、「録音された声」が持つ、なにか根源的な不気味さのようなものを突きつけられるようで、何度読んでもヒヤリとしてしまう。これを翻案した鈴木清純の映画『ツィゴイネルワイゼン』では、不明瞭だったはずのサラサーテの言葉を主人公がはっきりと聞き取ってしまうという形に改変されており、この展開も恐ろしかった。
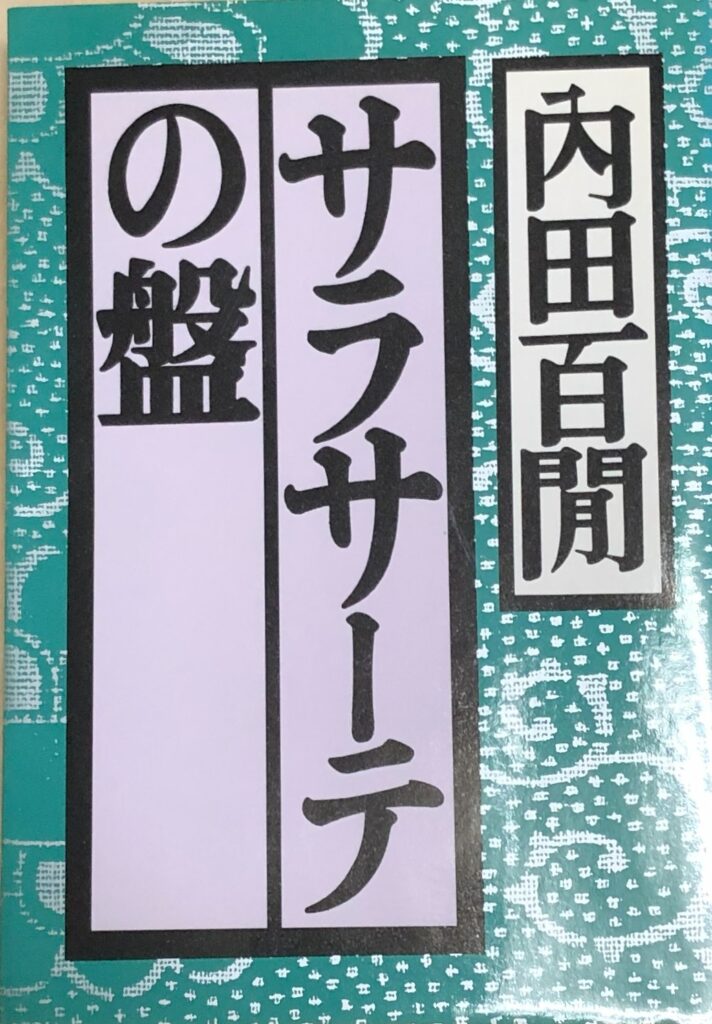
さて、ようやく本題である。
そもそも今回取りあげる「レコードに霊の声」というネタが怪談のジャンルとして定着するきっかけとなったのは、今もさまざまなメディアで語られ続けている1975年「かぐや姫解散コンサート」の音源ということになるのだろう。「私にも聞かせて」という、おなじみのアレである。
この音源は商品化されておらず、個人がカセットテープに録ったものを、解散コンサートからほどなくして『南こうせつのオールナイトニッポン』で放送したことで全国に知れ渡ることになった。当初、南こうせつも番組スタッフも謎の声には気づいておらず、あくまで通常のライブ音源として紹介した。しかし放送後、番組に「変な声が入ってたぞ!」というハガキが殺到。これによって事件(?)は大ブレイクし、テレビや雑誌など、あらゆるメディアが報じるようになった。テレビ番組などでは音響専門家による詳細な検証が行われ、近年も声の謎を解き明かそうという試みはさまざまな形で行われているようだが、今のところ合理的な説明はつかないということになっている。
僕ら世代は子どもの頃からさんざん聞かされてきたわけだが、今あらためて聞いてみても確かに絶大なインパクトがある。ライブ中のMCの途中、観客の拍手に重なるようにして女性の震えた声で「私にも聞かせて(もしくは「聞かせろ」)」という台詞がはっきり入っているのだが、さまざまな検証で解説されている通り、会場の音を拾うマイクの位置と声との距離感が非常に奇妙だ。また、逆再生しても同じように「私にも聞かせて」と聞こえる、もしくは人によっては「私もそこに行きたかった」と聞こえるという話も有名で、これもテレビなどで何度も検証された。
僕の場合は「私もそこに行きたかった」と聞こえるのだが、こういう現象、つまり本来は意味のないはずの情報(音や声なども含めて)から意味を読み取ってしまう(空耳のような形で)は「パレイドリア(Pareidolia)現象」として知られているが、そうした説明だけでは少々割り切りにくいようにも思う。
後に「南こうせつのオールナイトニッポン」に「あれは私の友人の声です。彼女はコンサートに行きたがっていましたが、病気で亡くなってしまいました」といった内容のハガキが届いたとか、コンサートに行く途中に交通事故で亡くなった少女がいたといったエピソードが語られるようになったが、これらについても裏取りができているものはないようだ。
この「かぐや姫事件」(?)の第一人者として知られているのが、関西の伝説のラジオ番組『北野誠のサイキック青年団』や、国際的な人気を博したアニメ映画『パーフェクトブルー』の原作者として知られ、現在は怪談師としても活躍する作家・竹内義和氏。竹内氏は「かぐや姫解散コンサート」のマスターテープを所有しており、彼はこのカセットテープ自体をめぐってもさまざまな怪異を体験しているらしい。また、竹内氏が音源を最初に耳にしたのが『あなたの知らない世界』だったと回想しているので、僕ら世代の多くがこのネタを最初に知ったきっかけも同番組だったのかも知れない。
「かぐや姫」の騒動があって以降、「このレコードにも霊の声が入ってるゾ!」という話をたびたび耳にするようになり、80年代になると定番ネタをズラリと紹介するだけで雑誌の特集が組めるほどになっていたと思う。資料を精査したわけではないが、こうした特集をやたらと目にするようになったのは、僕の記憶では80年代なかばから90年代初頭ごろだったと思う。そうしたもののなかから、ひとまず昭和時代に限定して話題になったものを羅列してみよう。
岩崎宏美「万華鏡」1979年
「男性のうめき声が聞こえる」という当時の鉄板ネタで、子どもの頃の僕らはテレビに岩崎宏美が出てくるだけで「怖い!」と思うようになってしまった。しかし、現在は「NGテイクのコーラスがミックス時に消去しきれずに残ったもの」ということで、一応は解決済みになっているらしい。
オフコース「YES-YES-YES」1982年
「女性がなにかつぶやいている声が聞こえる」と、これも当時はかなり話題になった。先述の「かぐや姫事件」と噂がミックスされ、声は「私にも聞かせて」と言っているという説もあり、やはりオフコースのコンサートに行く途中に事故で死んだ少女がいたといった尾ヒレの逸話も語られていた。しかし、声は意図的に入れたSEだったそうで、台詞は「ねぇ、私のこと好き?」だったようだ。
オフコース「言葉にできない」1982年
「フェイドアウト前にお経が聞こえる」と紹介されることが多かった。これもSE的に入れた小田和正の英語のささやきだったとされている。オフコースはなぜかこの種のネタの常連で、「一億の夜を越えて」(1980年)に「女性のすすり泣きが聞こえる」という噂もあった。要するにさまざまなSEや声をトラックに入れることが多く、誤解を生みやすかったということなのだろう。
中森明菜「ミックジャガーに微笑みを」1986年
酒井法子「恋のさなか」1989年
どちらの曲にも「まったく同じ音」が入っている、と噂された珍しい事例。両曲とも街頭の騒音がSEとして入っているのだが、ドシン!という衝撃音に続き、女性の声で「痛い……」というささやきが聞き取れる、とされている。両者の共通の友人だった岡田有希子の霊では?と語られることが多かった。どちらもさまざまなSEを多用しており、あらためて聞いてみてもよくわからない。そのつもりで聞いてみると確かに聞こえる……ような気もする。
中島みゆき「涙」1988年
「『死ね』とつぶやく男の声が聞こえる」として有名だった。「あんないい人、いやしないもの」という歌詞の「しない」に重なって、確かに「死ね」という声が重なっているようにも聞こえる。ディレイかリバーブのエコーのせいのようにも思えるが、これに関しては定説がないようだ。
レベッカ「MOON」1988年
「心霊レコード」としてはおそらくこれが最も有名だろう。いまだにラジオやwebでたびたび紹介されるので、若い世代にも知られる超定番のネタである。「せんぱ~い」と呼びかける女の声が聞こえるというもので、これをめぐって当時はさまざまな眉唾なストーリーが語られていた。実際はエフェクターを通したボーカルのNOKKOの声だとディレクターが種明かしをしている。

90年代以降も『笑っていいとも』で大きな話題になったB’zの曲(異音が聞こえるほか、再生するたびに内容が変わるとされた)など、この種のネタは定期的に「新作」(?)が登場し、昨今でもあれこれの話題にことかかないようだ。盤が消えて配信が主流になっても事情は変わらないようで、今後も「霊の声」は意図せず録音され続けるのだろう。
この現象がジャンル化したのは、先述した通り端緒となった「私にも聞かせて」が当時はあまりに衝撃的だったからということが大きいと思うが、「意図せず記録されてしまった霊」という発想は、「かぐや姫騒動」の前年にブーム化した「心霊写真」が先行している。中岡俊哉が巻き起こした「心霊写真」ブームが下地になったことによって、「視覚的に霊が記録されるなら、聴覚的にも記録されるだろう」ということへの「納得度」(?)はより高まっていたような気がする。
かつて写真・写真機は不吉なものとされ、「写真に撮られると死ぬ/魂を奪われる」といった迷信が流布した。それはおそらく「遺影」などからの連想で、写真が「死者の面影を残すもの」という印象が強かったからだろう。レコード盤・録音機にも同じようなイメージがあったのかも知れない。有名な「ビクターの犬」に添えられるフレーズ「His Master’s Voice」は「死んでしまった飼い主の声」という意味合いで、「この蓄音機はイヌが反応するほどに亡き飼い主の声をリアルに再生できます」と説明するものだ。あの首を傾げた犬は、死者の声を聞いているのである。
時間の経過とともにはかなく消えていくはずのものを強制的に固定し、永遠に残るものとして所有する。こうした行為に、僕らの感性はなにかしら無意識の罪悪感や、説明不能な不穏さを感じるようにできているのかも知れない。

初見健一
昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。
関連記事
「お札をはがしてくれ……」竹内義和が霊からお願いされた怪談からの連鎖/吉田悠軌・怪談連鎖
土地に根づいた怪異・怪談と、個人が体験する一回性の怪現象。それは相反するようでありながら、ときに補いあい、連鎖することがあるようだ。
記事を読む
君は自分のCDに幽霊の声が録音されていたことはあるか?/大槻ケンヂ「医者にオカルトを止められた男」
霊の声が聞こえる。確かに歌ったはずなのに、自分の声ではなくなっていた。音響版の人怖怪談がオーケンを襲う。
記事を読む
楳図かずおと1970年代の子どもたち/昭和こどもオカルト回顧録
少女ホラー、怪奇マンガ、ギャグマンガという枠をこえて「楳図マンガ」ともいうべき作品世界を築いた巨匠を振り返る。思えば、時代を超えるどころか時代を感じさせない作品と作家ではなかったか……?
記事を読む
ホワイトハウスは幽霊に取り憑かれている! 元シークレットサービスが明かす歴代大統領の幽霊との遭遇
かねてより“出る”と噂されている米ワシントンD.C.にあるアメリカ合衆国大統領官邸「ホワイトハウス」だが、新たな証言者が決定的な暴露発言を行っている。長年ホワイトハウスで大統領の護衛任務に就いていた女
記事を読む
おすすめ記事

