ついに「ビッグフットの死骸」発見・回収に成功! 新たな生態も続々判明、一般公開も開始!
米ニューヨーク州の山地でビッグフットの死骸が発見された! 一般公開されている愛称「ダック」は、果たして本物なのか!?
記事を読む
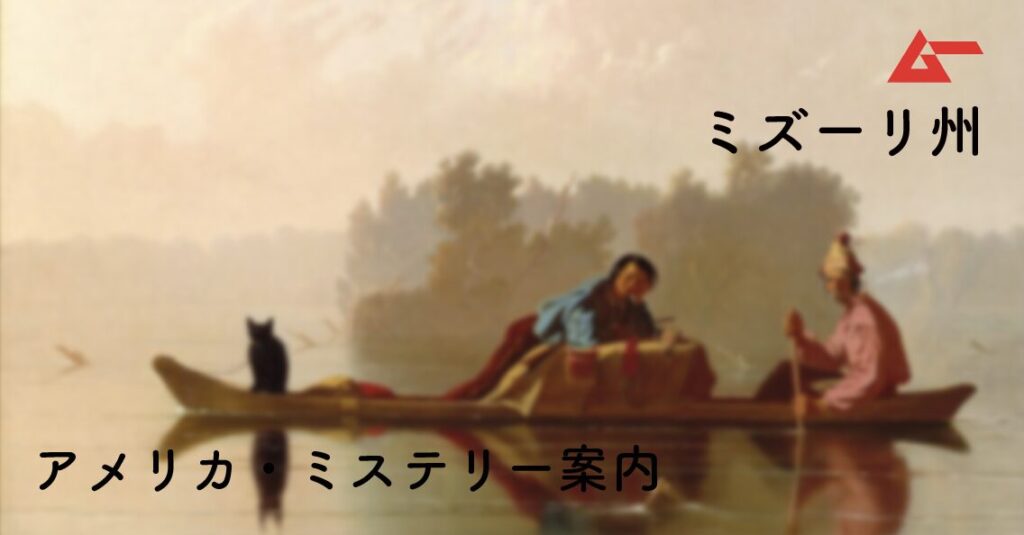
超常現象の宝庫アメリカから、各州のミステリーを紹介。案内人は都市伝説研究家の宇佐和通! 50年ほど前、ミズーリ州で発生した異形の巨大生物騒動から読み解く、アメリカのフォークロア、コミュニティ、そして文化の形成過程。
ニュージャージー州のジャージーデビル。ミシガン州のドッグマン。アイダホ州のシャーリー。そしてルイジアナ州のルーガルー。この連載では、いくつかの州のアイコン的な伝説のモンスター、あるいは地元の伝承で語り継がれてきたUMAを紹介してきた。今回紹介するミズーリ州の「モモ」はそれほど知名度はないかもしれないが、リストアップするにふさわしい存在だ。
アメリカ中西部に位置するミズーリ州には、ミシシッピおよびミズーリのアメリカ国内の二つの大河が流れ、州の歴史、経済そして文化に大きな影響を与えた。文化および経済の中心地はセントルイスで、ランドマークとなっている壮麗な建造物“ゲートウェイ・アーチ”は世界中からやってくる観光客で賑わっている。
ミズーリ州は「ショウ・ミー・ステート」というちょっと変わったニックネームで呼ばれている。州選出の下院議員ウィリアム・D・ヴァンダヴァーが1899年に演説で「私はミズーリ出身だ。あなたは私に証拠を見せなければならない」と語ったことに由来する。この発言が広まり、ミズーリ州の人々の疑い深い性格を表すために使われるようになった。何ごとにも慎重でコンサーバティブな気質のミズーリ州民によって長い間語り継がれている「モモ」の物語は、どんな内容なのか。

モモが注目を集め始めたのは1972年の夏、場所はミズーリ州ルイジアナというミシシッピ川沿いの小さな町だ。7月11日、兄弟二人が自宅の庭で遊んでいると、家の中にいた姉が突然の叫び声をあげ、家の隣に広がる森を指さしている。そちらを見ると、森の縁に大きな黒い毛むくじゃらの謎の生物が立っている。身長は約2メートルで、長い黒髪に覆われた大きな頭はカボチャのような形だった。オレンジ色の光る目で兄弟をじっと見つめている。特に印象的だったのは、耐えがたいほど強烈な臭いを放っていたことだ。
南部フロリダ州でもスカンクエイプという名のUMAに関する話が伝えらえているが、こちらに関しても目撃報告が爆発的に増加したのが70年代だった。もうひとつ共通しているのは、スカンクエイプというニックネームの由来ともなった強烈な臭気だ。「腐敗した動物の死骸」「硫黄」「スカンク臭」などと形容される悪臭を放つ同じ種のUMAの異なる個体がミズーリ州とフロリダ州に同時期に生息していたということなのだろうか。
兄弟の目撃談はすぐに町や近隣に広まり、新たな目撃談や奇妙な声、謎の足跡、特有の悪臭などが相次いで報告されるようになった。住民たちは「森の中に巨大な影を見た」「夜に不気味なうなり声が聞こえた」と口々に語り、恐れを隠さなくなる。当時地元の消防署で署長を務めていたリチャード・アラン・マリー氏までもが「私も最初はただの噂だと思っていたが、勤務時間内に奇妙な生物を見た」というコメントを地元新聞に残している。
時間の経過と共に話が大きくなり、目撃情報や奇妙な足跡、不自然な形で残されている動物の死体の発見などが報告されると、未確認生物の専門家や研究者、そしてハンターがルイジアナに集まり始めた。ほどなく20人規模の捜索がも組織され、周辺の森をくまなく探したが、モモと思われる生物を捕獲することはできなかった。捜索の過程でいくつか足跡が発見され、未知の霊長類が残したものという見解が出たが、科学的な裏付けをとることはできなかった。
そもそも小さな街で起きた子供による奇妙な生物の目撃事件だったものが、たちまち地域全体、さらには州や全国メディアでも取り上げられるレベルの大騒動となった。新聞記者やテレビ局、好奇心旺盛な観光客が押し寄せ、「モンスター騒動」が繰り広げられることになった。ペットの失踪、不思議な足跡、森から聞こえる奇声——さまざまな話が街中に広がり、地元の商店ではモンスターグッズが販売され、子どもたちは森に恐怖と興奮を覚え、手がかりを探し始める者も出た。こうしたエピソードのひとつひとつがモモの存在感を高め、色々な方向性の脚色が加えられるようになったのだ。
ところが、冬を迎える頃になるとあれほど熱狂的だったモモ熱が急速に冷え始める。目撃報告の絶対数も一気に激減した。1972年以降も時折目撃が報告され続けたが、わずか数ヶ月の熱狂の後、モンスターは地元住民の記憶から消え、存在の証拠も見つからず、ましてや捕まえることもできなかった。それでも地元で生まれた話として残り、サマーキャンプやハロウィンの時だけ話題になり、家族の思い出話や地域の民話とひもづける形で今も語り継がれている。
モモ現象にはさまざまな解釈を加えることができるだろう。
ひとつの指標として示すことができるように本質をまとめるなら、「町全体が共同で恐怖を体験し、物語として共有していく力」ということになるだろうか。これはまさに、アーバンフォークロアの基本的性質だ。また、モモ伝説は地域の自然や文化と深く結びついており、「森の向こうに何かがいるかもしれない」という想像力を育てるものともいえる。いずれにせよ、存在すら確認できなかったモモは人間の不安や未知への恐れを象徴するものであり、時に子どもたちが勇気を奮い立たせるきっかけとなり、コミュニティの連帯を語り継ぐものとなった。
直接的な目撃が激減した今でもモモは文化的な影響を与え続けている。州内最大都市セントルイスの遊園地では、1973年から1994年までモンスターの名前を冠した人気アトラクションが運営されていた。2019年には『Momo: The Missouri Monster』が公開され、1972年の事件に対する再考察が実現している。
モモの物語は、小さな事件が民間伝承/都市伝説という形で永続的な文化遺産へと昇華していくプロセスをつまびらかにするものにほかならない。怖い森での出来事が町全体を巻き込む騒動となり、捜索隊やメディア報道へと発展し、モンスターハントというより広いカルチャーに組み込まれた。
毎年夏になると、焚火の周りで同じ話が語られる。「森の向こうに何かがいるかもしれない」「オレンジ色の目が見えて、ひどい臭いがしたら、モモが近くにいるのかもしれない」——伝説を今日まで生き続けさせている原動力の源は、フォークロアを語る人たちと聞く人たちのイマジネーションが交わる時に生まれるエネルギーではないだろうか。
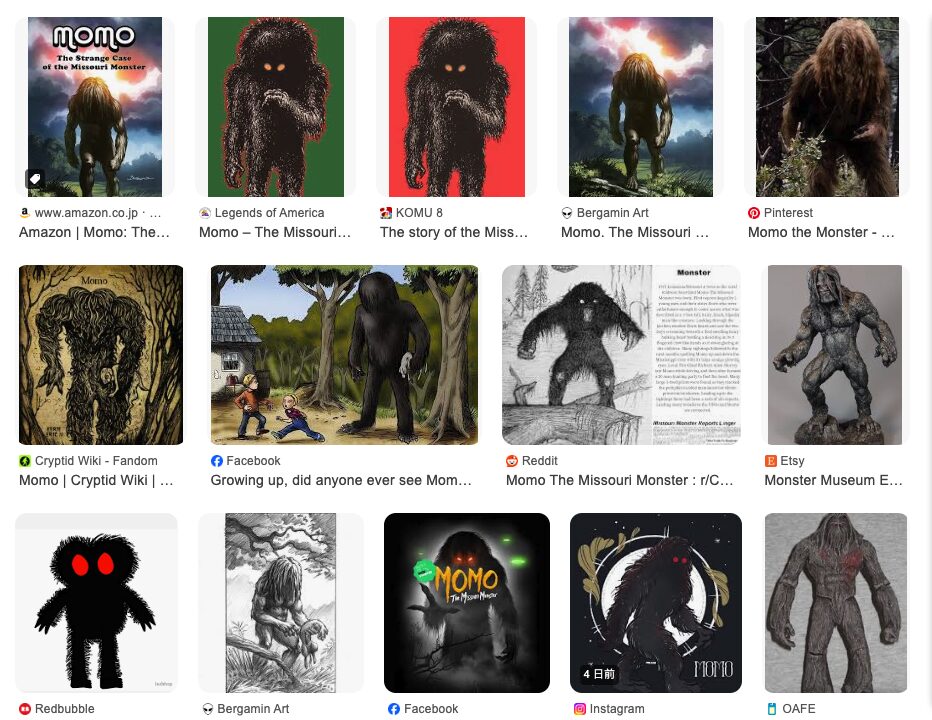
宇佐和通
翻訳家、作家、都市伝説研究家。海外情報に通じ、並木伸一郎氏のバディとしてロズウェルをはじめ現地取材にも参加している。
関連記事
ついに「ビッグフットの死骸」発見・回収に成功! 新たな生態も続々判明、一般公開も開始!
米ニューヨーク州の山地でビッグフットの死骸が発見された! 一般公開されている愛称「ダック」は、果たして本物なのか!?
記事を読む
正体はわれわれの祖先か、絶滅した異人類か? 獣人UMAビッグフット研究最前線/南山宏
2021年4月24日、アメリカで、森林に姿を消す巨大な獣人を女性が目撃するという衝撃の事件が起きた。獣人とは、もちろんビッグフットである。アメリカに限らず、古くから報告が続くビッグフット、そしてその近
記事を読む
心霊スポット多数の「オールド・ルイビル」は幽霊に会える街/ケンタッキー州ミステリー案内
超常現象の宝庫アメリカから、各州のミステリーを紹介。案内人は都市伝説研究家の宇佐和通! 目指せ全米制覇!
記事を読む
「天の逆手」の呪いは現代に受け継がれている!怪談「裏拍手」と古神道の呪術
いまやメジャーな怪談、都市伝説のひとつである「裏拍手」。知られるようになったのは10年ほど前だが、その恐怖のルーツは神話にまでさかのぼりうるものだった。 『教養としての最恐怪談』著者が、裏拍手に隠され
記事を読む
おすすめ記事

