凶宅の再現に驚く「加門七海の風水探見」/ムー民のためのブックガイド
「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。
記事を読む
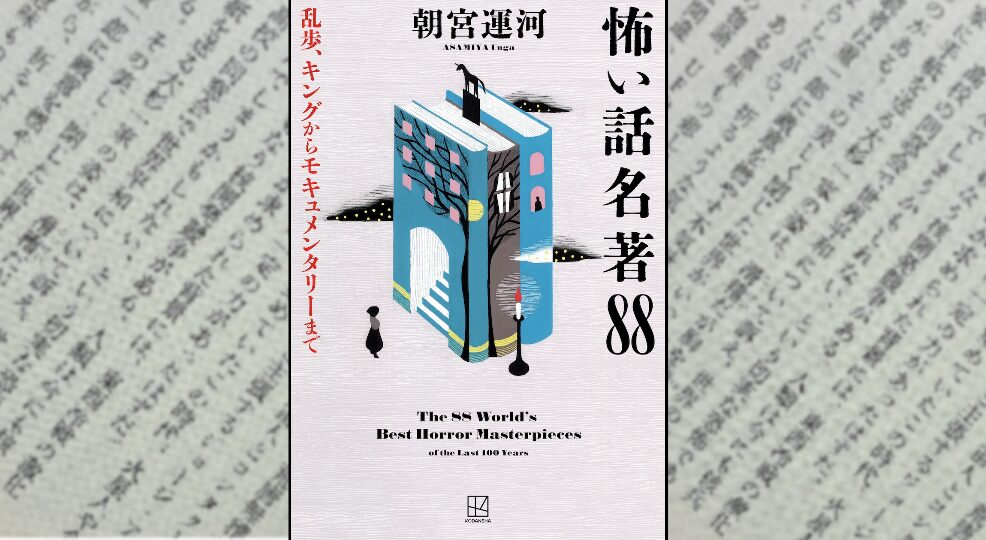
100年間の「怖い話」から88冊を厳選したコアなガイドブックが誕生! 今回さらにここから、オカルトファンに刺さる珠玉の3選をピックアップ!あなたは全て読んだことある?
目次
いま、「怖い話」が大ブームです。怪談、都市伝説から、モキュメンタリー(フェイクドキュメンタリー)やいわゆる“因習村”のような民俗ホラーまで、ジャンルもテイストも百花繚乱。ついには小泉八雲夫妻が主人公のドラマまではじまって、もはや意識せずともどこかで「怖い話」に触れてしまう時代に突入。古参の怪談マニアは、こんな世の中がやってくることを予想できたでしょうか?
ところで、いったい日本人はいつからホラーを読み、恐怖を求めてきたのでしょうか? そんな疑問にヒントを与えてくれるブックガイド『怖い話名著88』が発売されています。
本書は、1920年代から現代まで、この100年間に世に出された「怖い話」から88冊を厳選したもの。江戸川乱歩の『人間椅子』、夢野久作『ドグラ・マグラ』といった名作中の名作から、日本にも影響を与えた海外ホラーまで幅広い作品がとりあげられています。
著者はホラー・怪奇幻想小説を専門に研究してきたライターの朝宮運河氏で、それぞれの作品について読みどころが紹介され、「主題、物語性、感動、余韻、登場人物」の5つの項目で魅力を分析したチャートがつけられているのもありがたいところ。プロの鑑識眼とチャートを目安にして自分の興味にあった作品が選べる、入門書として最適の一冊です。

今回、この『怖い話名著88』から特別に、ムー愛読者「ムー民」やオカルトファンに刺さりそうな作品を3冊ピックアップさせてもらいました。88からさらによりすぐりの3選、すべて知っていたら、あなたはかなりの「怖い話通」かも?
『美しい星』三島由紀夫、1962年
ジャズやロック、ハリウッド映画。20世紀はさまざまな大衆文化を生み出したが、UFOも間違いなく20世紀を代表する文化現象の一つだ。1947年にアメリカ人ケネス・アーノルドが「空飛ぶ円盤」に遭遇して以来、世界各地でUFOの目撃が相次ぎ、さらには宇宙人とコンタクトしたと自称する人まで現れた。その奇妙なストーリーは世界を魅了し、フィクションに取り入れられていく。
三島由紀夫の長編『美しい星』も、UFOの時代という背景抜きには生まれなかったものだ。埼玉県飯能に暮らす大杉一家は、去年の夏、それぞれが別の天体からやってきた宇宙人であるという事実に気がついた。父の重一郎は火星人、母の伊余子は木星人、息子の一雄は水星人、娘の暁子は金星人なのだ。荒唐無稽な設定に感じるかもしれないが、実際に宇宙人とコンタクトし、空飛ぶ円盤に乗せてもらったと主張するジョージ・アダムスキーの著作が注目を集めていたこの時代、火星人や金星人という単語には一定の力があったはずだ。
こうした物語が求められた背景には、東西冷戦の激化とそれにともなう核開発競争がある。人類は今にも核兵器で滅んでしまうかもしれない、という切実な恐怖である。高校の同窓会で世界平和について訴え、世界の政治家に手紙を送る大杉一家の姿は、滑稽だが胸を衝かれるものがある。その美しく閉じた世界がいつ破綻するのか、読者は重一郎に敵意を燃やす不気味な男たちの登場にはらはらしながら、祈るような気持ちでページを捲ることになる。ある意味もの悲しく、ある意味では恐ろしい宇宙人視点の物語。UFO文学というジャンルがあるとすれば、本書は間違いなくその傑作だ。
魅力分析
主題(テーマ)★★★★★
登場人物(キャラクター)★★★★
余韻(モメンタム)★★★★
感動(インプレッション)★★★
物語性(ストーリー)★★★★★
『龍は眠る』宮部みゆき、1991年
日本のホラー小説を考えるうえで、スティーヴン・キングの存在はとてつもなく大きい。特に1990年前後に書かれた国産ホラーにはキングの影響がそこかしこに見て取れる。宮部みゆきもキング流のモダンホラーを試みた作家の一人で、その成果は本書や『クロスファイア』のような超能力を扱ったサスペンスとして表れた。
関東に大型台風が接近していた9月の夜、東京に車を走らせていた事件記者の高坂は、雨の中立ち住生していた少年・稲村慎司を拾う。二人を乗せた車はやがて、蓋のずれたマンホールに差しかかる。暗い穴のそばには子ども用の黄色い傘と、わが子を探す父親の姿。翌朝、慎司は意外な事実を口にする。彼は人や物の記憶を読み取れるサイキックであり、マンホールの蓋をずらした犯人が見えたのだと。ところが後日、高坂の職場に慎司の従兄を名乗る若者・織田直也が訪ねてきて、慎司の能力はトリックだと明かす。果たして超能力は存在するのか。
本書における超能力者の扱いは、たとえばキングの『キャリー』や『デッド・ゾーン』と似通っている。特別な力は恩寵ではなく、むしろ呪いではないかという見方である。そして『デッド・ゾーン』の予知能力者が孤独に苦しめられたように、本書のサイキックたちもそれぞれに葛藤する。そのリアルで血の通ったキャラクター造形が大きな読みどころだ。物語は直也の失踪と、何者かの高坂への脅迫という二つの事件を軸に、緊迫したムードで展開していく。その二つが意外な形で繋がる結末部分、高坂がついに超能力の存在を確信するシーンには胸を衝かれる。週刊誌主導の超能力バッシングという、70年代オカルトブームの負の歴史を扱っているのも、注目しておきたいポイントだ。
魅力分析
主題(テーマ)★★★
登場人物(キャラクター)★★★★★
余韻(モメンタム)★★★★
感動(インプレッション)★★★★★
物語性(ストーリー)★★★★
『祝山』加門七海、2007年
国土のおよそ7割を占める山は、日本人にとってもっとも身近な異界である。それゆえ人々は山を崇め、畏れて、さまざまな物語を伝えてきた。『祝山』はそんな山の怪異譚の現代バージョンだ。
ホラー作家の鹿角南のもとに、しばらく連絡が途絶えていた友人の矢口朝子からメールが届く。職場の同僚と肝試しに行って以来、奇妙なことが立て続けに起こっているという。矢口たちが出かけたのは山の中にある工場跡地。住居だったらしい木造家屋に足を踏み入れると、畳を突き破って掛木が生い茂り、仏間には位牌が残されていた。その後、怖くなって神社で祝詞を唱えた、現場ではオーブがたくさん撮れた、などと興奮して語る矢口たちの姿に、鹿角の心は冷めていく。かれらはオカルトにかぶれているだけなのだ。しかしメンバーの一人・若尾からの相談を受けて、鹿角はやや考えを改める。若尾によれば肝試しの夜以来、職場の雰囲気がおかしくなり、彼女自身は怖い夢に悩まされているというのだ。この山の怪異は伝染する。気づいた頃にはもう、災いは鹿角のそばまでやってきていた。
自らも豊富な心霊体験を持ち、数多くのホラーや怪談を発表してきた加門七海だが、本書ではあえて幽霊を描いていない。本書が描いているのは人知の及ばぬ山の霊異そのものだ。奇妙な偶然や悪い夢、常軌を逸した矢口らの言動の背後から、じわじわと禍々しい山の気配が伝わってくる。物語の後半では関わりを避けていた鹿角も、問題の山を訪ねることになるのだが、もちろん除霊による解決などは用意されていない。この世界には人間には手出しのできない領域がある。それを悟るべきだと、後味の悪いラストは告げているようだ。
魅力分析
主題(テーマ)★★
登場人物(キャラクター)★★★★
余韻(モメンタム)★★★★
感動(インプレッション)★★
物語性(ストーリー)★★★
・・・
書評を読むだけで、どれもすぐに作品を手に取りたくなってきませんか? この他にあと85もの「怖い話」が紹介されている『怖い話名著88』。書評のほかに、『ぼぎわんが、来る』の澤村伊智、『近畿地方のある場所について』の背筋との対談も収録されたボリューミーな一冊です。
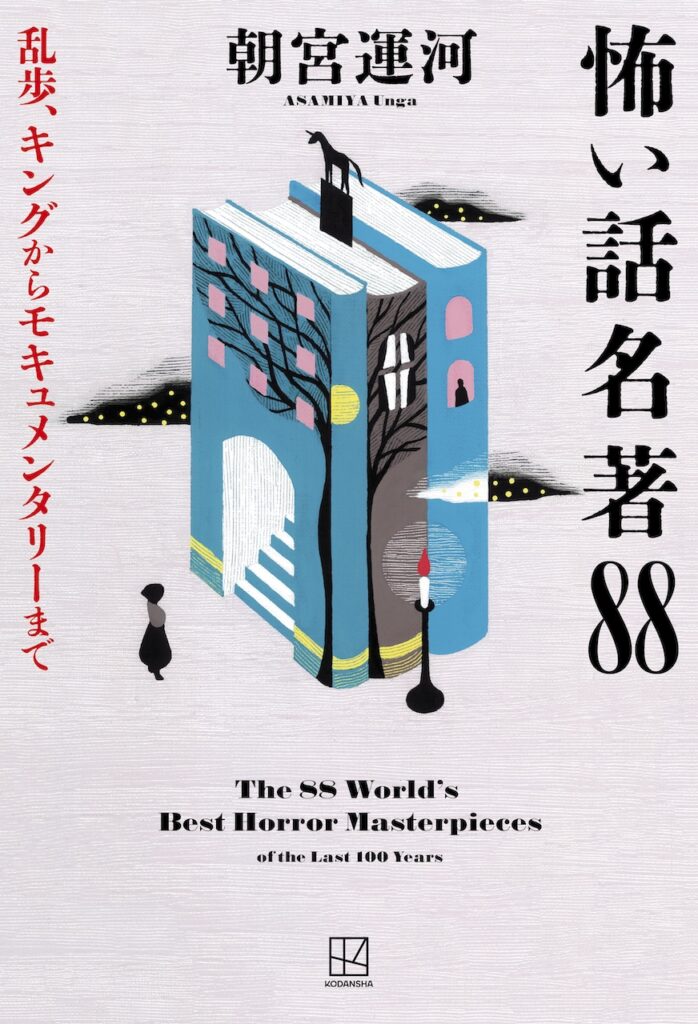
『怖い話名著88 乱歩、キングからモキュメンタリーまで』(朝宮運河著、税込1,540円、講談社)
webムー編集部
関連記事
凶宅の再現に驚く「加門七海の風水探見」/ムー民のためのブックガイド
「ムー」本誌の隠れ人気記事、ブックインフォメーションをウェブで公開。編集部が選定した新刊書籍情報をお届けします。
記事を読む
「姥捨て」の伝承は異界への畏怖から生まれた!?「楢山節考」「デンデラ」に見る“境界”を越える物語
老いた親を山に捨てる――各地に残る「姥捨て伝承」は、老いへの恐怖という人間の普遍的心理と山への畏れを映し出してきた。伝承と創作の交点から、その物語を紐解いていく。
記事を読む
稲川淳二も驚嘆!「教養としての名作怪談 日本書紀から小泉八雲まで」発売
気鋭の怪談研究家が名作怪談を解体する。
記事を読む
書物占い・ビブリオマンシーが妖怪を暗示!? ムー的まんが道のねじれ/石原まこちん・漫画ムーさんぽ
都市伝説ウォッチャーの漫画家・石原まこちんが、さんぽ気分で深みを目指すルポ漫画。目指すは秘密結社……なのだが、その扉はなかなか開かない。そこで、次の取材先を占いで探ることにした。 今回は、麻布十番でし
記事を読む
おすすめ記事

