「お化け」は世につれ…怪談の時代性と賞味期限についての回想/昭和こどもオカルト回顧録
怪談といえば落ち武者や生首……というのはもう古い? 怪談の昭和スタイルを回顧する。
記事を読む
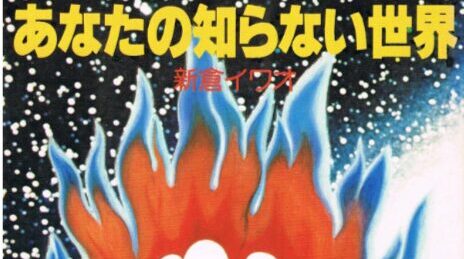
夏休みにぼんやりテレビを眺めている子供たちは、しばしば「恐怖の実体験」を目の当たりにした。現在のテレビ番組表から消えた心霊特番「あなたの知らない世界」を振り返る…。
夏が近づくと思い出すのは、小学生時代の夏休みに必ず見ていた「あなたの知らない世界」、そして「見なきゃよかった!」と後悔しながら、眠れないままに過ごした暑苦しい熱帯夜の記憶である。
「あなたの知らない世界」とは、1968年に放映開始された日テレ系の『お昼のワイドショー』の心霊特集企画。史上初の心霊特番であり、視聴者から募った体験談を「再現フィルム」としてドラマ化するというスタイルは、映像で見せる「実話系怪談」の定番手法を確立した。
初回の放映は1973年。当初は一回限りの単発企画だったが、予想をはるかに超えた反響があり、その後は夏休みのお盆の時期に放映される風物詩的なコーナーになった。79年からは毎週木曜日のレギュラー企画に格上げされ、87年に『お昼のワイドショー』の放映が終了した後も『午後は〇〇おもいっきりテレビ』に引き継がれる。
このエポックメイキングな番組を「発明」したのが、『笑点』を立ちあげたプロデューサーとしても知られる新倉イワオ氏。彼は日本心霊科学協会理事を務めた人物でもあるが、1968年に自ら心霊現象を体験したことを期に、従来は放送業界で忌避されがちだった幽霊ネタをテレビに、しかも昼時の主婦向け番組に持ち込んだ。
前代未聞の試みに局内の反対意見も多かったそうだ。当時のテレビ業界は、というかエンタメ業界全般がそうだったらしいが、現在よりもいわゆる「縁起をかつぐ」傾向が強かった。「死」にまつわるコンテンツなどは「験が悪い」とされ、芝居や映画などでも怪談ものを手掛ける際はお祓いを受けるのが一般的だった。ましてテレビ番組の場合はスポンサーの意向が重要になる。「縁起の悪い」内容の番組は、スポンサーから嫌われてしまうリスクがあるわけだ。水木しげるの『墓場の鬼太郎』がテレビアニメ化される際、「『墓場』なんていうタイトルの番組だとスポンサーが逃げてしまう」と判断され、『ゲゲゲの鬼太郎』に改称されたのは有名な話である。
しかし、新倉イワオはなんとか上層部を説得し、いわば一回限りの実験的企画としての放映を実現した。これがまさかの大反響を得て、結果として「心霊特番」というジャンルを開拓し、テレビ史を変える伝説的な企画となったわけだ。
反響のほとんどは視聴者からの「私の体験も紹介してほしい」というものだったという。新倉はじめ、スタッフは「これほど膨大な数の人が心霊体験をしているのか!」と驚いたそうだ。ある意味『あなたの知らない世界』は、ちょっと他人には言いにくい奇妙な体験談の「はけ口」のような場を、初めてテレビの世界に作りだしたとも言えるのだろう。

この成功により、テレ朝『アフターヌーンショー』、日テレ『2時のワイドショー』、フジ『3時のあなた』、TBS『3時に会いましょう』など、各ワイドショーも心霊特集で追随する。一時期はお盆の時期の真っ昼間のテレビが「幽霊だらけ」状態になっていた。
「あなたの知らない世界」で紹介されたエピソードでもっとも有名なのが、キャシー中島の体験談だろう。例の小坪トンネルでの怪現象である。その後も何度となく心霊特番で取りあげられ、「クルマのフロントガラスに手形がつく」といった現象や、「体験者のひとりは発狂して現在も入院している」といったオチは、あちこちでパクられまくって今では怪談の定石のようになっているが、「あなたの知らない世界」で初めて見たときは本当に総毛立つほど怖かった。
僕は子ども時代から数々の心霊番組や、それなりの本数のホラー映画を見まくってきた方だと思うが、「生涯最恐!」のトラウマ的恐怖映像は、やはり『あなたの知らない世界』の「再現フィルム」で目にした一場面である。どこかのホテルか旅館の巨大な厨房の隅に開かずの扉(使われていない貯蔵室だか冷蔵庫)があり、あるときにその扉が開いて、真っ白な顔をした女が上半身をのぞかせる……というだけの短い逸話だった。
その唐突感と、女の霊体の人形のような異物感がめちゃめちゃ怖くて、見たときは「ギャッ」と声をあげて目を覆ってしまった。大人になった今でも、体調の悪いときなどはこのシーンがふいにフラッシュバックすることがある。
また、ごくまれにだったが(予算の都合だったのかも知れない)、「再現フィルム」ではなく、「再現紙芝居」(?)で視聴者の体験談をまとめて紹介することもあった。フリップに描いた劇画調のイラストとナレーションで、文字通り紙芝居スタイルで霊体験を語っていくのである。妙に古臭い感じのイラストのタッチのせいか、このパターンも異様な雰囲気の話が多かったと思う。
覚えているのは、夫婦(だかカップル)がクルマで渋谷の道玄坂を走っていると、いつの間にか人里離れた山深い道に迷い込み、長い長い石段の上に真っ赤な鳥居の神社を目にする……というだけの話。これを見てからしばらくは、道玄坂を歩いていると異次元に迷い込みそうで怖かった。
これらについては、同じシーンを覚えている人がいないかと何度か本や雑誌に書いたことがあるのだが、同じ思い出を共有している人とはなかなか出会えない。実は「あなたの知らない世界」は、局にもほとんど資料が残っておらず、フィルムもすでにジャンク済みで、まともな「記録」と呼べるものが存在しないのだ。今まで2回ほど取材したことがあるが、やはり「放映リスト」のようなものもすでに廃棄されているらしい。もうリアルタイム世代の記憶の中にしか、あの数々の「恐怖」は存在しないのである。
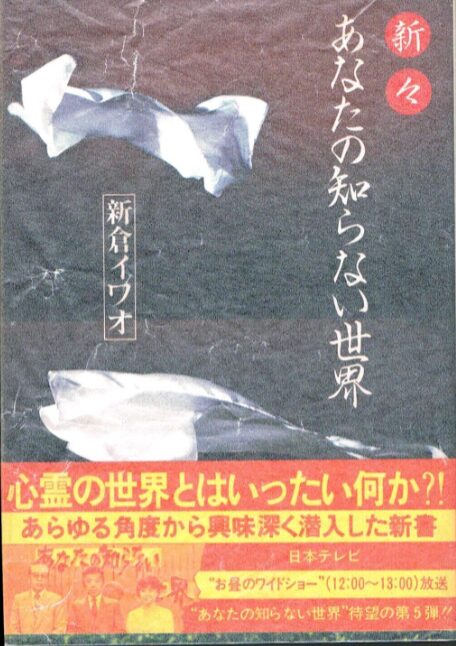
「あなたの知らない世界」は、テレビ業界だけではなく、映画業界にも絶大な影響を与えている。
Jホラーの勃興は、おそらく「あなたの知らない世界」がなければ起こらなかっただろう。80年代はホラー映画といえば米国産のスプラッター、スラッシャー系ばかりだったが、これに対してあくまで「実話系心霊譚」にこだわって制作されたのが、90年代初頭のオリジナルビデオ版『ほんとにあった怖い話』シリーズだった。今も語り継がれる鶴田法男監督の『夏の体育館』『霊のうごめく家』など、このシリーズの傑作エピソードがJホラーブームのトリガーになったといわれているが、これらの作品の構造と感触は、僕ら世代にとってはまさに「あなたの知らない世界」の復活だった。鶴田監督は子ども時代に見た同番組の影響について直接コメントしているし、清水崇や黒沢清、高橋洋、さらにJホラー以前から「実話系心霊譚」を模索し続けていた小中千昭なども、直接間接に「あなたの知らない世界」から多大な影響を受けていると思う。
「あなたの知らない世界」を見た日の夜の狂おしいような寝苦しさは、いまだに忘れられない。子ども部屋の隅に誰かがジッと立っているような気がして、ただでさえ寝苦しい熱帯夜に何度も布団の中で寝返りを打ち、汗びっしょりになってひたすら恐怖に耐えたものだ。そして「もうあんな番組は見ないっ!」と後悔するのだが、なぜか翌日になるとまた見てしまう。その夜にまたもや布団の中で震えながら「もう見ない!」と決心するも、やはり翌日のお昼にはテレビの前に座っている……。
「あなたの知らない世界」が放映される夏休みの数日間は、夜な夜な後悔を繰り返す日々だった。
また、これはあくまで蛇足だが、「あなたの知らない世界」には「眠れなくなる」こと以外に、もうひとつ困ったことがあった。番組初期は、なぜか「私のヌード、見てください」といった妙なコーナーとセットになっていたのだ。今では考えられない下世話な企画だが、視聴者の「若奥さん」から希望者を募って、応募してきた人のヌード写真をプロのカメラマンが撮影し、それを紹介するというもの。真昼間、心霊話の直後にいきなり「素人の裸」を見せる、という異様な構成だったのである。ウチは「あなたの知らない世界」を毎年家族で見ていたので、この生々しい「ヌード写真コーナー」の気まずさはあまりにキツかった。
(2021年7月23日記事を再編集)
初見健一
昭和レトロ系ライター。東京都渋谷区生まれ。主著は『まだある。』『ぼくらの昭和オカルト大百科』『昭和こども図書館』『昭和こどもゴールデン映画劇場』(大空出版)、『昭和ちびっこ怪奇画報』『未来画報』(青幻舎)など。
関連記事
「お化け」は世につれ…怪談の時代性と賞味期限についての回想/昭和こどもオカルト回顧録
怪談といえば落ち武者や生首……というのはもう古い? 怪談の昭和スタイルを回顧する。
記事を読む
70年代の心霊特番から「Jホラー」ブームへ受け継がれた伝播性の恐怖/昭和こどもオカルト回顧録
映像作品での恐怖体験を振り返る3回目。作り物とわかっていても怖い、作り物だから怖くない。トラウマ化する条件はなんだったろうか。
記事を読む
昭和心霊特番のトラウマ「呪われた肖像画」の曖昧な記憶/昭和こどもオカルト回顧録
昭和のテレビで放映された「恐怖映像」は子どもたちにトラウマを残すことも多かった。筆者の記憶にある夏の日の番組も……? 老婦人の肖像画の番組、見た記憶はありませんか?
記事を読む
闇夜に野獣の襲撃! 鬼の子孫が営む「小仲坊」での危機体験/松原タニシ超人化計画「鬼の子孫」(2)
奈良県の山奥には、鬼の子孫が営む宿坊があるという。超人を求めて宿坊を訪ねたタニシを、危機一髪のピンチが襲う!
記事を読む
おすすめ記事

