怪談で涼をとりましょうーー無気味で不吉な犬の怪異集/妖怪補遺々々
暑い日が続きます。そこで今回は、黒史郎から暑気払いの怪談をお届け。それも、妖怪や幽霊譚ではなく、むしろそれらよりも強そうな〝犬〟にまつわる怪異な話を補遺々々しました。ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家
記事を読む
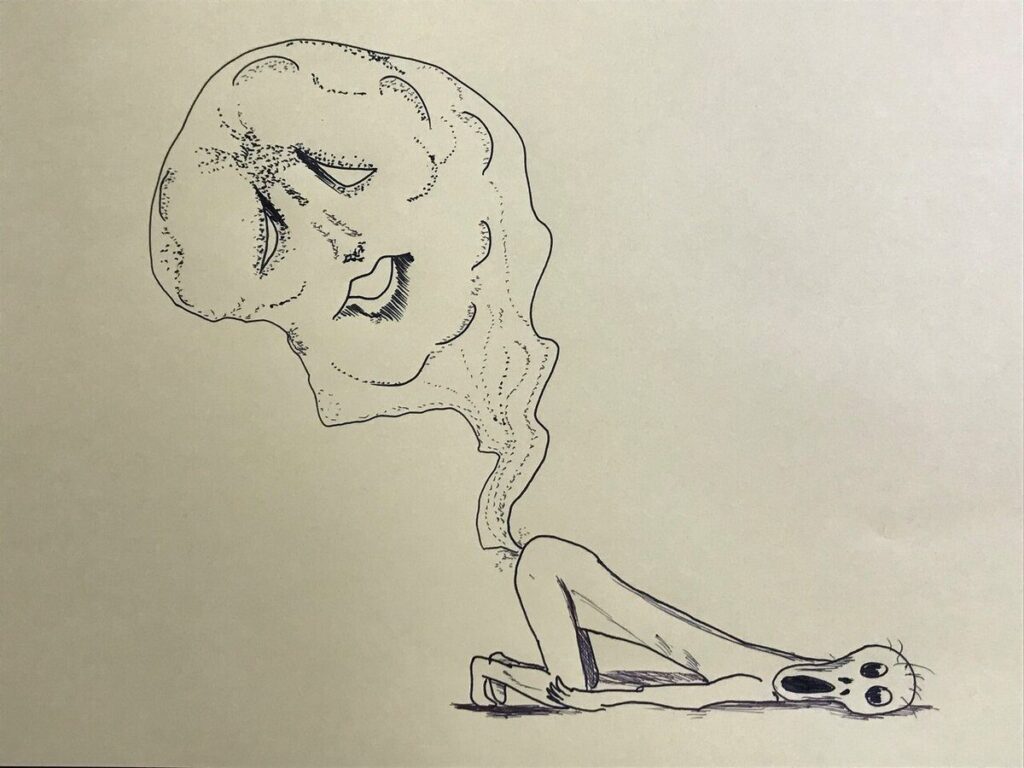
〝妖怪放屁放屁〟3部作、ついに完ケツ! 歴史に埋もれるべくして埋もれた放屁譚を大発表します! 屁をこくとき、だれもが妖怪になるのです。 ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残されながらも人々から“忘れ去られた妖怪”を発掘する、それが「妖怪補遺々々」だ!
かつて私たちの国には、屁の名人と呼ばれる人々がいました。「曲屁福平」「屁國先生」「屁又」「放屁太夫」と名乗り、呼ばれていた彼らは、曲芸としての屁を使いこなす達人たちでした。連続で屁を放つ「梯子屁(はしごべ)」、屁で長刀(なぎなた)の形を表わす「長刀屁」、音より臭気を重んじる技「鼬の一聲啼(いたちのひとこえなき)」、蛇に呑まれる蛙の鳴き声と最後に呑みこまれる様を音で表現する「蛇の蛙呑み」、笹の葉の上を渡る虻(あぶ)の羽音を真似し、最後に笹葉をすべり落ちる様で締める「虻の笹渡り」など――彼らが芸として披露していた屁は、その音の大きさ、発射数、においなどで観衆を楽しませる立派な技術であり、日々の訓練と努力の賜物といえるでしょう。
しかし、ファンタジーな世界の「屁をする者たち」の屁は違います。
昔話「屁放り嫁」のような殺傷力を有する屁、人の尻では到底鳴りえない不思議な音を響かせる「鳥呑み爺」の屁、これらは訓練や努力では獲得できない異能であり、こういった昔話の放屁者は異能者であることが多いのです。
先の2話は、各地に類話が見られる異屁譚の代表例といえる昔話ですが、わが国にはまだまだ不思議な放屁譚がございます。
「西の大屁こき」と「東の大屁こき」がおりました。
ある日、西の大屁こきが東の大屁こきの家へ、「屁こき競べ」を挑みにやってきました。
しかし、東の大屁こきは留守にしており、家では婆さんがひとりで留守番をしています。
この婆さん、家の中を歩きながら屁をひるのですが、そのたびに敷いてある蓆(むしろ)が2、3枚めくれあがります。それを目の当たりにした西の大屁こき、「婆さんでさえ、この屁なのだから、東の大屁こき本人が戻ってきたら、とてもじゃないが叶わない!」と恐れをなし、「また来る」といい残して帰ろうとしました。その帰り際、彼は一発していくのですが、なんと、その屁の勢いで藁屋根の片側が、めくれ上がってしまいます。
それからすぐに東の大屁こきが帰ってきて、「この屋根はどうしたことか」と婆さんにたずねました。婆さんは今あったことを伝え、「ほれ、向こうの道を曲がりかけているあれが、西の大屁こきだ」と伝えました。
「それは怪しからん、早く手杵を持ってこい」
東の大屁こきは受け取った手杵を自分の尻に当てて、一発、屁を放ちました。
すると、東の大屁こきの、ものすごい屁の勢いで手杵が飛んでいって、西の大屁こきに見事命中――こうして、西の大屁こきは、死んでしまったということです。
この「大屁こき」は、奥原国雄の郷里、島根県八束郡秋鹿村で採集された昔話です。
「おれが日本一の大屁こきだ」「なにを、おれこそ日本一の大屁こきだ」と、屁をブーブーやりあう楽しい闘いが見られるのかと思いきや、まさかの殺害エンドでした。しかも、殺し方がひどすぎます……。屁の音で競い合って決着をつけるわけにはいかなかったのでしょうか。
次は、だれもが幸せになる屁のお話をご紹介いたします。
長野の諏訪湖の南にある大熊(おおぐま)という所に、大きな屁をする平太(へいた)という男がいました。あまりに屁ばかりするので「へっぴりの平」と呼ばれていた彼は、食事以外は朝から晩までごろごろと家で寝ている怠け者。その腹は狸のようにふくらんでおり、だからなのか、いつも彼は苦しく、屁をすると少しは楽になるので屁ばかりするのです。
しかも、その屁はものすごく大きなもので、家は地震のようにぐらぐらと揺れました。屁の風で家の中の物がみんな庭まで吹き飛ばされ、人も柱に捕まらなければ飛ばされてしまうほどでした。
そんな、へっぴりの平にとうとう我慢できず、家の人は彼にこういいました。
「お前は家にいてもなんにもできないから、どっかへ行ってくれ」
しかたなく平は家を出て、あてもなく村の中を歩いてまわります。
やがて諏訪湖に出ると、隣村の船着き場があり、大勢の人が岸から舟を押し出そうとしているところでした。しかし、たくさんの米を積んでいるので、大人の男が何人がかりでも、その舟はびくともしません。そのうえ舟は泥にがっちりとはまってしまっているので、動く気配がまったくないのです。
その様子を見ていた平は、アハハハと笑いました。
「なんだなんだ、そんなに集まっても舟ひとつ動かせないなんて。オラなら、屁で押し出してやるわ」
これには舟を押していた人たちも怒ってしまいます。
「それなら屁でやってみろ。もし押し出せたら千両出してやる。だが、もしできなかったら、そんときはただじゃおかねぇぞ」
隣村の人たちに詰め寄られた平は、着物の裾をポイッとめくると諏訪湖の中に入って、舟に尻を向けてしゃがみました。すると褌を片側に寄せ、息をフーッとたくさん吸い込むと、顔を金時のように赤くして……
「ブーブーブーブゥーブゥーブーブーブーブゥーのブウーブゥッ」
とても長い屁を放ちました。
するとどうでしょう。
舟はグ、グ、グ、グーと岸から離れていくではありませんか。これには隣村の人たちも驚いて開いた口が塞がりません。
こうして約束どおり、へっぴりの平は黒塗りの千両箱をもらいました。それを担いで帰ると、家の人には驚かれるやら喜ばれるやら。さっきは出ていけといったのに、今度は、ずっと家にいてくれと頼まれます。
平は「こんなに大金はいらない」と、村の人たちに小判を1枚ずつ配って回り、空になった千両箱を家の鶏の餌箱にしてしまいました。
その後も彼は、家のゴミを屁できれいに吹き払ったり、田を荒らすスズメを屁でブーッと脅して追い払ったりして、村人たちから喜ばれ、敬われる存在になったということです。
「へっぴりの平」の屁は、家を揺るがすほどの威力があるため、誤った使い方をすれば彼は人々から恐れられ、忌み嫌われる存在となっていたことでしょう。しかし、彼はその力を人のために使うことを覚え、人から愛される存在となれたのです。彼の放つ屁は、恥ずかしくもなく、迷惑にもならない、人々に笑顔を作る幸せの屁でした。
屁が肉眼で見えるものだったら、人類の歴史は大きく変わっていたことでしょう。先の昔話も、また違った物語になっていたはずです。
屁は見えないもので、形のないものというのが一般常識のようですが、屁を音やにおいや、もたらす被害だけでなく、ヴィジュアルで伝える逸話もあります。
唐樹という人があるとき、こんな疑問を抱きました。
「そういえば、屁の形を知らないな、どんなものだろう」
すると、そばにいたお爺さんが、このようにいいました。
「その形を、私はよく知っていますよ」
なんと、そのお爺さんは、あるはずのない屁の形を見たことがあるというのです。
お爺さんによると、最近温泉に行ったとき、まさに放屁の姿が現れたのだそうです。その形は玉のようで、光っており、手に取ろうとすると陽炎のように消えうせてしまい、後には、ただ臭いにおいのみが残るとのことでした。
これを聞いた唐樹は頷いて、次のような歌を詠んだそうです。
《連城の玉にも似たるはうひぞと 湯來天下に傳ふ屁奇なり》
連城の璧(たま)とは、趙の恵文王の持つ宝石のことで、泰の昭王が15の城と交換したいと申し出たほどのお宝です。つまり、とてもすごい宝の玉ということです。
湯船の中で放屁すると泡が現れますが、まさか、お爺さんはそのことをいっているのでしょうか。それとも、湯の外で、そのような不思議で美しい屁が尻からこぼれ出たのでしょうか。
最後は、岐阜県の「屁こくばさ」という短いお話をご紹介します。
昔々、おじいさんとおばあさんがおりました。
おじいさんは山へ草刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。
おばあさんは大きな屁をこきました。
おじいさんは山で、くさかったといいます。
――以上です。
だからなんだよ、と苦笑いしてしまう内容ですが、よく読むととんでもない話です。
川にいるおばあさんの放った屁が、山にいるおじいさんの鼻にまで届いたのですから。
おじいさんの鼻に屁が届くまでには、かなりの距離と時間があったはず。普通の屁なら鼻に届くどころか、発されてすぐ空気に拡散され、屁は跡形も残らないはずです。においもすぐに消えてしまうでしょう。それでも「くさかった」のですから、ひりこぼされた直後のおばあさんの屁は、とんでもないにおいだったのではないでしょうか。生物兵器級の毒性とまではいきませんが、至近距離で浴びていたら、ただではすまないでしょう。
ただ、この話は「臭かった」と「草刈った」をかけたダジャレをやりたかっただけの昔話だと思われますので、そこまで深刻に考えることではありませんし、妖怪の話でもありませんので、この辺でやめておきます。
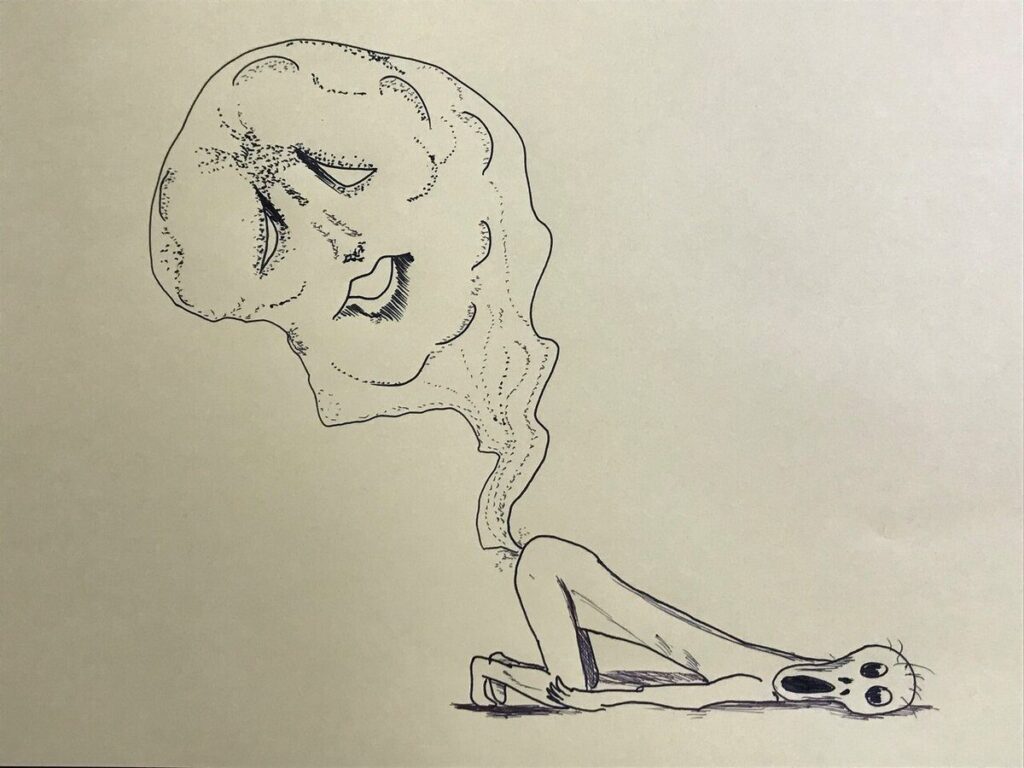
参考資料
岩田達治『秦野の民話』
「飛騨の民話」『日本の民話』未來社
竹村良信『諏訪のむかし話』信濃教育会出版部
野村純一編著『柳田國男未採択昔話聚稿』
福富織部『屁と褌』
(2021年6月2日記事を再編集)
黒史郎
作家、怪異蒐集家。1974年、神奈川県生まれ。2007年「夜は一緒に散歩 しよ」で第1回「幽」怪談文学賞長編部門大賞を受賞してデビュー。実話怪談、怪奇文学などの著書多数。
関連記事
怪談で涼をとりましょうーー無気味で不吉な犬の怪異集/妖怪補遺々々
暑い日が続きます。そこで今回は、黒史郎から暑気払いの怪談をお届け。それも、妖怪や幽霊譚ではなく、むしろそれらよりも強そうな〝犬〟にまつわる怪異な話を補遺々々しました。ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家
記事を読む
皿を割って現れ、皿を欲して現れ、皿を投げるために現れる「皿」の怪/妖怪補遺々々
今月のテーマは「皿」にまつわる幽霊たち! なぜそうなったのかは後ほど明らかになることとして、皿の幽霊もよくぞこんなにというほど補遺々々されています。ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録に
記事を読む
溺死や落ち武者の霊や祟りを名に遺す…ちょっと怖い地名の昔話/妖怪補遺々々
地名には、その土地で起きた出来事と紐づいたものがあります。しかもそれは災害だったり事故だったり事件だったりと、ゾクリとするものが由来の場合も! ホラー小説家にして屈指の妖怪研究家・黒史郎が、記録には残
記事を読む
CIAは日本でも情報操作を行っている! ニセ情報やトレンド操作で形成するリアルな世論/宇佐和通
米国の内外にかかわらず世論を操作し、世界を自らの望む形に変えようと活動するCIA。いったいこれまで日本はどのように操られてきたのか――?
記事を読む
おすすめ記事

